2010年01月10日
命あるものへの倫理~熊本動物愛護センターの取り組み~
新年が明けました。なんと1年2ヶ月ぶりの投稿になります。諸事情でこのシリーズも開店休業の状態ですが、今年はなんとか再開できるようにしたいと思っています。
ここ数年、全国ネットで熊本出身の方々の活躍が目立ちますね。スポーツ界、エンターテイメント界では言うまでもなく、特に映画界では、「おくりびと」の脚本家・小山薫堂さん、「ワンピース」の原作者・尾田栄一郎さんなど。いつかインタヴューできる日が来ればと思います。
さて、新年。このような著名人ではなく、今回は行政面で全国の注目を集めている、熊本市動物愛護センターを取り上げます。
日本が高齢・少子社会になるのに伴って、人間とペットが共生するためのスタイルが浸透しています。それは犬に限っても1960年の190万頭から、今では600万頭を数える程になり、一方で、日本での保健所の殺処分数は、約年間50万匹に及ぶと言われています。
特に犬や猫の場合、繁殖しすぎて対応に困って飼育を放棄する人々も増えているようですね。それでも、多少の心ある人は動物保護センターに持ち込んでいきます。その結果が年間50万匹の殺処分というのですから驚きです。
 そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)
そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)
<ペット事情1-ペットと生活 基本編ライフスタイルポータル>
http://www.lifestyle-portal.jp/pet/pet_01_01.html
1998年度の殺処分969匹というのは、引き取った動物の約81%にあたります。そして2007年度の78匹というのは約17%にあたり、10年間で1/10以下に減少させたわけですね。どんな対応をしてきたのかというと、センターが打ち出した方針は「安易にセンターで引き取らない」というものでした。
職員の皆さんが、飼い主に命の大切さを説き、思い直してもらうという異色の対応です。「あなたがやっていることは、命のあるものでも年を取ったら捨てていいと子供に教えているのと同じだ。それでもいいのか」と、飼った以上は最後まで面倒をみるということを説くんだそうです。
<命の重さ説き犬の殺処分激減、熊本市動物愛護センター>
http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/kumamoto/20090329-OYS1T00419.htm
<頑張る行政!_生存率77.7パーセント熊本市動物愛護センター>
http://www.animalpolice.net/jititai/ganbarujititai/kumamoto_city2008/index.html
熊本市では2007年に慈恵病院で新生児を親が匿名で養子に出すための「こうのとりのゆりかご」を始めました。これには今も賛否両論ありますが、これまでに同院に預けられた子供の人数は昨年9月時点で51名。少なくとも亡くなったかもしれない51の命が救われたことは確かなことです。
ペットと人間を並立して論じることは不遜なことかもしれませんが、熊本市動物愛護センターの職員の皆さんが訴えていることは、命あるものへの人間としての普遍の倫理なのですね。
<画像>
(1/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター
http://www.youtube.com/watch?v=I6OdACq8-VE
(2/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター
http://www.youtube.com/watch?v=RROV9SeROyg&NR=1
<熊本動物愛護センターの努力>
http://www.youtube.com/watch?v=LB87HRuW6gk
ここ数年、全国ネットで熊本出身の方々の活躍が目立ちますね。スポーツ界、エンターテイメント界では言うまでもなく、特に映画界では、「おくりびと」の脚本家・小山薫堂さん、「ワンピース」の原作者・尾田栄一郎さんなど。いつかインタヴューできる日が来ればと思います。
さて、新年。このような著名人ではなく、今回は行政面で全国の注目を集めている、熊本市動物愛護センターを取り上げます。
日本が高齢・少子社会になるのに伴って、人間とペットが共生するためのスタイルが浸透しています。それは犬に限っても1960年の190万頭から、今では600万頭を数える程になり、一方で、日本での保健所の殺処分数は、約年間50万匹に及ぶと言われています。
特に犬や猫の場合、繁殖しすぎて対応に困って飼育を放棄する人々も増えているようですね。それでも、多少の心ある人は動物保護センターに持ち込んでいきます。その結果が年間50万匹の殺処分というのですから驚きです。
 そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)
そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)<ペット事情1-ペットと生活 基本編ライフスタイルポータル>
http://www.lifestyle-portal.jp/pet/pet_01_01.html
1998年度の殺処分969匹というのは、引き取った動物の約81%にあたります。そして2007年度の78匹というのは約17%にあたり、10年間で1/10以下に減少させたわけですね。どんな対応をしてきたのかというと、センターが打ち出した方針は「安易にセンターで引き取らない」というものでした。
職員の皆さんが、飼い主に命の大切さを説き、思い直してもらうという異色の対応です。「あなたがやっていることは、命のあるものでも年を取ったら捨てていいと子供に教えているのと同じだ。それでもいいのか」と、飼った以上は最後まで面倒をみるということを説くんだそうです。
<命の重さ説き犬の殺処分激減、熊本市動物愛護センター>
http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/kumamoto/20090329-OYS1T00419.htm
<頑張る行政!_生存率77.7パーセント熊本市動物愛護センター>
http://www.animalpolice.net/jititai/ganbarujititai/kumamoto_city2008/index.html
熊本市では2007年に慈恵病院で新生児を親が匿名で養子に出すための「こうのとりのゆりかご」を始めました。これには今も賛否両論ありますが、これまでに同院に預けられた子供の人数は昨年9月時点で51名。少なくとも亡くなったかもしれない51の命が救われたことは確かなことです。
ペットと人間を並立して論じることは不遜なことかもしれませんが、熊本市動物愛護センターの職員の皆さんが訴えていることは、命あるものへの人間としての普遍の倫理なのですね。
<画像>
(1/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター
http://www.youtube.com/watch?v=I6OdACq8-VE
(2/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター
http://www.youtube.com/watch?v=RROV9SeROyg&NR=1
<熊本動物愛護センターの努力>
http://www.youtube.com/watch?v=LB87HRuW6gk
2008年11月02日
ブラジルのピカソと呼ばれた画家・マナブ間部
久しぶりの投稿です。先ほど、TKUで「夢の足跡・画家マナブ゙間部~ブラジルと日本に架けた虹~」を見ました。マナブ間部については、昨年の9月に初めて知りました。そのときのことを以前書いたものがありましたので、ここに加筆し転載させてもらいます。
先日、県立劇場を訪れた際、館内に大きな抽象画が飾られていました。その大きさに圧倒されながら、「フーン」と頷くだけの私。その後、その画家の名前も、作品名も忘れていました。そして、今日一幅の「群像」という絵を観て、「あっ」と思いました。この「ヒト」の描き方が県立劇場にあった絵と同じです。画家の名はマナブ間部。熊本県生まれの日系ブラジル移民でした。間部さんは、こんなことを語っています。

「芸術とは何だ」 「私は何のために絵を描くのか」。そんなことを考えたある日からもう三十年が過ぎた。である。考えて良かった。農夫が画家になった。私の人生が変った。牧場の小川でランバリーやバーギレを釣り、小さな椰子の実やゴヤバを食べながら小鳥を追いまわして遊んだ少年の日の想い出は、私の生涯忘れることの出来ない抒情詩である。
赤いコーヒーの実、緑の葉、青い奥地の空の色は、今もなおカンバスの上にひろがり、汗と埃にまみれて、赤土を耕した青年の日の夢は、六十歳の今日も同じく、塗っては削り、削ってはまた描く制作魂であり闘志である。
無限の夢を追い、美の世界を遊丈する。美を極め芸術を追求することは常に自己との戦いである。制作の苦しみと喜び。何が私をこんなに夢中にさせたのか。美である。美がだんだん大きく、ひろく見えてくる。この命燃え尽きるまで、どのくらい掴めるだろう。
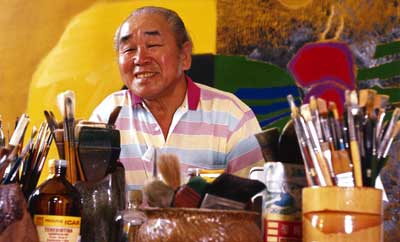
七歳で傘の絵を描き、十歳で秋の風景を写生した。二十二歳の頃カンバスに果物や植民地風景を油絵で描き始め、1953年頃から画面に色彩や形を考えるようになった。1958年、爆発するように抽象画が始まり、希望と興奮に真紅の血潮は画面に脈打ち始める。
「そうだ、作品は生の記録だ」。その日から私の生命は、人の子として何にも勝る父母の愛情に恵まれて育ち、人の子の親としてその喜びも悲しみも知る大宇宙の天地と悠久の歴史の流れの中に在りて、この小さな生命、夢大きく理想の世界を目差して羽ばたきながら、毎日を力一杯生きる。(間部 学 1985/公式サイト)

マナブ間部さんがブラジルへ渡ったのは、私の父が3歳のとき。そこで抽象画を描き始めたのが、私が生まれた年です。私の本籍地は、網田町、間部さんの生まれは不知火町。父は、1931年3月、満州(現中国東北部)大連に生まれ、終戦間もなく熊本に帰ってきました。日本は1931年の満州事変以後、満蒙開拓移民を本格的に入植させていますが、父はそれよりも半年前に生まれていますので、先遣団だったのだと思います。日本への帰国がもう少し遅れていたら、父は残留孤児になっていた可能性が高かったといいます。
昭和初期、方や中国に夢を求めて旅立った日本人がいて、一方でブラジルへ渡った日本人がいた。明治、大正と西洋を追いかけるように走った日本でしたが、農村は貧しく、大日本帝国政府は海外への移民を奨励していました。1920年代に入ると、それまで最大の日本人移民の受入国であったアメリカにおける日系人に対する人種差別の激化と、それに伴う黄禍論の勃興などにより日本人移民の受け入れを実質禁止したこともあり、ブラジルが最大の日本移民受入国となったそうです。

日本が移民の輸出国だった。今ではとても信じられないことですが、中国、アメリカ、ブラジルへと何十万人の日本人が旅立ちました。満州だけは、恵まれていたようですが、当時の日本人はそれぞれの土地で苦労を重ね、その働きぶりは当地の人々を驚かせたといいます。今年はブラジル日系移民100周年ということで、イベントが行われていましたね。
今世界はグローバル化し、特に金融の世界では一蓮托生式のマネーゲームの網の中に巻き込まれています。当時の日本人の苦労を思えば、今の景気低迷などまだまだ軽いものだと、このドラマを見て思いました。どんなに貧しくとも、夢を持って生き続けたマナブ間部さんの生涯をかいま見て、私はまだまだユルイなと感じた次第です。
マナブ間部(1924年9月14日-1997年9月22日)は「日系ブラジル移民でありブラジルを中心に活動した。間部学。熊本県不知火町(現在の宇城市)の宿屋を営む間部家に生まれた。1934年(昭和9年)10歳のときに父・宗一と母・ハルと共に『ラプラタ丸』でブラジルへ移民。両親と共にリンス市ビリグイのコーヒー農園で働きながら育つ」。
「1945年にコーヒー園が霜のために全滅し野良仕事が暇になったことから、油絵の具を使って厚紙や板きれに絵を描き始めた。1950年にサンパウロ作家協会展に入選し、1951年に国展入選。1951年に新潟出身のよしのと結婚。1953年から静物や人物をテーマにし、その物体の形をつよい線で描き、それで画面構成を作る画風となった」。
「1956年から7年間をかけて、間部いわく『非具象構成派』とする絵を描き続ける。1957年にはコーヒー園を売却し、サンパウロ市に移住。専業画家となった。生活のためにネクタイの染色や看板も描いたという。1959年4月、『レイネル賞展』でレイネル賞を受賞。同年9月に第5回サンパウロ・ビエンナーレ展で国内最高賞を授章した。その10日後には『第1回パリ青年ビエンナーレ展』で受賞。この2つの受賞がアメリカ・タイム誌に『MABE黄金の年』として取り上げられた。このことがきっかけで絵も売れ始めたという」。
「1960年6月、第30回ヴェネツィア・ビエンナーレでフィアット賞を受賞。1961年から196年にかけて、ローマ、パリ、ワシントン、ヴェネツィア、ミラノと個展を巡回。同年アルゼンチン・コルドバで開催された『南米ビエンナーレ』で絵画部1位入賞。1979年1月には作品を積んだヴァリグ・ブラジル航空機が成田国際空港を離陸後に遭難し作品の多数が失われたこともある。間部はその後14年かけて喪失した1点1点を画き直したという」。
「1993年12月、日本経済新聞に『私の履歴書』を連載。1997年(平成9年)6月に東京で開催された個展は美智子皇后も鑑賞に訪れている。画風は初期は具象画、後期は暖かな色調・筆の抽象画でブラジルのピカソとよばれた。宇城市不知火美術館に作品が所蔵されている。アンティークマニアであり、アメジストの原石を所有していた。世界お宝ハンティング 勝負は目利きの取材で来た柴俊夫、ちはるにローマンガラスを五万円で譲った。鑑定額は四十万円だった」。(ウィキペディア)
先日、県立劇場を訪れた際、館内に大きな抽象画が飾られていました。その大きさに圧倒されながら、「フーン」と頷くだけの私。その後、その画家の名前も、作品名も忘れていました。そして、今日一幅の「群像」という絵を観て、「あっ」と思いました。この「ヒト」の描き方が県立劇場にあった絵と同じです。画家の名はマナブ間部。熊本県生まれの日系ブラジル移民でした。間部さんは、こんなことを語っています。

「芸術とは何だ」 「私は何のために絵を描くのか」。そんなことを考えたある日からもう三十年が過ぎた。である。考えて良かった。農夫が画家になった。私の人生が変った。牧場の小川でランバリーやバーギレを釣り、小さな椰子の実やゴヤバを食べながら小鳥を追いまわして遊んだ少年の日の想い出は、私の生涯忘れることの出来ない抒情詩である。
赤いコーヒーの実、緑の葉、青い奥地の空の色は、今もなおカンバスの上にひろがり、汗と埃にまみれて、赤土を耕した青年の日の夢は、六十歳の今日も同じく、塗っては削り、削ってはまた描く制作魂であり闘志である。
無限の夢を追い、美の世界を遊丈する。美を極め芸術を追求することは常に自己との戦いである。制作の苦しみと喜び。何が私をこんなに夢中にさせたのか。美である。美がだんだん大きく、ひろく見えてくる。この命燃え尽きるまで、どのくらい掴めるだろう。
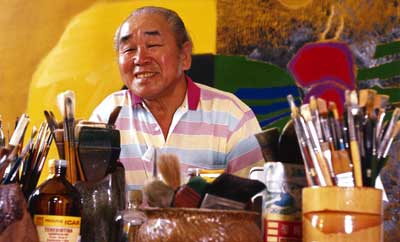
七歳で傘の絵を描き、十歳で秋の風景を写生した。二十二歳の頃カンバスに果物や植民地風景を油絵で描き始め、1953年頃から画面に色彩や形を考えるようになった。1958年、爆発するように抽象画が始まり、希望と興奮に真紅の血潮は画面に脈打ち始める。
「そうだ、作品は生の記録だ」。その日から私の生命は、人の子として何にも勝る父母の愛情に恵まれて育ち、人の子の親としてその喜びも悲しみも知る大宇宙の天地と悠久の歴史の流れの中に在りて、この小さな生命、夢大きく理想の世界を目差して羽ばたきながら、毎日を力一杯生きる。(間部 学 1985/公式サイト)

マナブ間部さんがブラジルへ渡ったのは、私の父が3歳のとき。そこで抽象画を描き始めたのが、私が生まれた年です。私の本籍地は、網田町、間部さんの生まれは不知火町。父は、1931年3月、満州(現中国東北部)大連に生まれ、終戦間もなく熊本に帰ってきました。日本は1931年の満州事変以後、満蒙開拓移民を本格的に入植させていますが、父はそれよりも半年前に生まれていますので、先遣団だったのだと思います。日本への帰国がもう少し遅れていたら、父は残留孤児になっていた可能性が高かったといいます。
昭和初期、方や中国に夢を求めて旅立った日本人がいて、一方でブラジルへ渡った日本人がいた。明治、大正と西洋を追いかけるように走った日本でしたが、農村は貧しく、大日本帝国政府は海外への移民を奨励していました。1920年代に入ると、それまで最大の日本人移民の受入国であったアメリカにおける日系人に対する人種差別の激化と、それに伴う黄禍論の勃興などにより日本人移民の受け入れを実質禁止したこともあり、ブラジルが最大の日本移民受入国となったそうです。

日本が移民の輸出国だった。今ではとても信じられないことですが、中国、アメリカ、ブラジルへと何十万人の日本人が旅立ちました。満州だけは、恵まれていたようですが、当時の日本人はそれぞれの土地で苦労を重ね、その働きぶりは当地の人々を驚かせたといいます。今年はブラジル日系移民100周年ということで、イベントが行われていましたね。
今世界はグローバル化し、特に金融の世界では一蓮托生式のマネーゲームの網の中に巻き込まれています。当時の日本人の苦労を思えば、今の景気低迷などまだまだ軽いものだと、このドラマを見て思いました。どんなに貧しくとも、夢を持って生き続けたマナブ間部さんの生涯をかいま見て、私はまだまだユルイなと感じた次第です。
マナブ間部(1924年9月14日-1997年9月22日)は「日系ブラジル移民でありブラジルを中心に活動した。間部学。熊本県不知火町(現在の宇城市)の宿屋を営む間部家に生まれた。1934年(昭和9年)10歳のときに父・宗一と母・ハルと共に『ラプラタ丸』でブラジルへ移民。両親と共にリンス市ビリグイのコーヒー農園で働きながら育つ」。
「1945年にコーヒー園が霜のために全滅し野良仕事が暇になったことから、油絵の具を使って厚紙や板きれに絵を描き始めた。1950年にサンパウロ作家協会展に入選し、1951年に国展入選。1951年に新潟出身のよしのと結婚。1953年から静物や人物をテーマにし、その物体の形をつよい線で描き、それで画面構成を作る画風となった」。
「1956年から7年間をかけて、間部いわく『非具象構成派』とする絵を描き続ける。1957年にはコーヒー園を売却し、サンパウロ市に移住。専業画家となった。生活のためにネクタイの染色や看板も描いたという。1959年4月、『レイネル賞展』でレイネル賞を受賞。同年9月に第5回サンパウロ・ビエンナーレ展で国内最高賞を授章した。その10日後には『第1回パリ青年ビエンナーレ展』で受賞。この2つの受賞がアメリカ・タイム誌に『MABE黄金の年』として取り上げられた。このことがきっかけで絵も売れ始めたという」。
「1960年6月、第30回ヴェネツィア・ビエンナーレでフィアット賞を受賞。1961年から196年にかけて、ローマ、パリ、ワシントン、ヴェネツィア、ミラノと個展を巡回。同年アルゼンチン・コルドバで開催された『南米ビエンナーレ』で絵画部1位入賞。1979年1月には作品を積んだヴァリグ・ブラジル航空機が成田国際空港を離陸後に遭難し作品の多数が失われたこともある。間部はその後14年かけて喪失した1点1点を画き直したという」。
「1993年12月、日本経済新聞に『私の履歴書』を連載。1997年(平成9年)6月に東京で開催された個展は美智子皇后も鑑賞に訪れている。画風は初期は具象画、後期は暖かな色調・筆の抽象画でブラジルのピカソとよばれた。宇城市不知火美術館に作品が所蔵されている。アンティークマニアであり、アメジストの原石を所有していた。世界お宝ハンティング 勝負は目利きの取材で来た柴俊夫、ちはるにローマンガラスを五万円で譲った。鑑定額は四十万円だった」。(ウィキペディア)
2008年06月19日
イグサと菜の花に賭けるアグリ・ファンタジスタ、岡初義(23)
去る4月19日、第17回目のゲスト・西田ミワさんの主催で熊本ブロガー交流会が行われました。その宴席で正面に座っておられた男性がいらっしゃいました。自然に話を始めて、名刺を頂くと肩書きに「織り師」とありました。何を織っておられるのか尋ねると、「畳です、イグサを織っています」と。それからイグサにまつわる話から始まり、うかがう内容に惹かれるように聞き込んでいくうちに、いつのまにかインタヴューを申し出ていました。

そんな訳で、今回のゲストは「織り師」岡初義さん(51)です。インタヴューは4月22日、岡さんの八代市鏡町にあるご自宅で行いました。当日は、西田ミワさんと交流会の二次会でご縁ができた夢子さんにも同行していただくという両手に花の状態の車中でした。ナビのない私の車で、おおまかな地図と菜の花畑を頼りに向かいましたが、一度だけ通り過ぎたものの、無事到着しました。

表題の「アグリ・ファンタジスタ」は、私が勝手につけた造語です。ずば抜けた技術を持ち、創造性に富んだ、予想外のプレーを見せる天才的なサッカー選手を「ファンタジスタ」と呼ぶそうですが、岡さんのお話や仕事ぶりを実際に見て、その発想力と行動力に敬意を込め、私は岡さんをあえて「アグリ・ファンタジスタ」と呼びたいと思います。まずは、岡さんが取り組んできたイグサの世界を見ておきます。
~日本の文化は、古来、中国大陸からの伝承をもとにしたものが多いのですが、畳は大和民族の生活の知恵が生み出した固有のもので、湿度が高く、気象の変化が激しい日本の風土に、最も適した敷物として育てられ、継承されてきました。瑞穂の国にふさわしく、稲わらを利用して床をつくり、野生のいぐさを改良して畳表を織り、畳という素晴しい敷物をつくりあげたわけです。旧漢字でたたみを「疊」と書きます。これは田圃からとれる稲わらを交互に積み重ねたとの意味があります。~(全国畳産業振興会HP)
畳表は「くまもと表(おもて)」と「びんご表」がわが国では双璧だといいます。残念ながら全国的には「びんご表」の方が有名なのだそうです。熊本県のい業は、興善寺城(八代市竜峰)城代・相良伊勢守の与力であった岩崎主馬忠久公が、現在の八代郡千丁町大牟田の上土(あげつち)城主になったおり、領内の古閑淵前に永正2年(1505)、いぐさを栽培させ、製織を奨励したことが始まりとされています。一方、広島県で生産されるびんご畳表は天文、弘治(1532-57年)の頃だといいますから、「くまもと表」が日本の畳表の草分けなんですね。

岡さんはこの伝統ある八代で数少なくなったイグサ生産者のお一人です。ご承知のようにイグサは今でも八代市が全国トップの生産地ですが、近年の日本における需要の低下は関係者の方々には死活問題で、その凋落ぶりは目に余るものがあります。数年前に生産者の方の自殺が相次ぎ、この小さな町村で十数名にのぼったことも記憶に新しいところです。
「イグサの日本における主な産地は熊本県八代地方であり、国産畳表の8~9割のシェアを誇る。他には石川県・岡山県・広島県・高知県・福岡県・佐賀県・大分県でも見ることができる。一方で近年、中国などの外国産の安価なイグサが輸入され(セーフガードまで発動した)、全流通量に対し国産畳表は3~4割ほどのシェアがあり、また住宅の洋室化とも相まってイグサ生産農家の減少が危ぶまれていたが、近年になり自然素材、健康志向の高まりによりその価値に注目が集まっている」。(ウィキペディア)

この記事にあるように、近年になりイグサに注目が集っていることは事実でしょうが、2005年以降の栽培面積は1631ヘクタールと十年前の約五分の一に減少していて、面積縮小に歯止めがかからないのが現状です。そんな苦境にあるイグサ生産の当事者である岡さんですが、岡さんの発言や行動には夢がいっぱい詰まっていました。今回は、苦境にあっても夢を追いかける、まさにこのブログの表題を文字通り邁進する岡さんにお話をうかがったわけです。(1631ヘクタール≒東京ドーム350個分)
岡さんは昭和32年2月13日のお生まれで、岡家七代目の当主です。奥様と長男、次男、長女の三人のお子様がいらっしゃいます。岡さんの活躍は県内外に知れ渡っていて取材もたくさん受けられています。その模様は後述するサイトのリンクを張っておりますのでそちらをチェックしていただきたいと思います。このブログでは、岡さんの人となりについて多少なりとも迫っていければと思います。
岡さんの人生観を知る上でエポックメイキングな出来事があります。それは、岡さんがこれまで三度も死に直面していることです。最初はその人生の始まりで、出生時に1800gの未熟児だったこと。未熟児は、一般に、出生時の体重が2500グラム未満をいうそうですが、1500グラム未満を極小未熟児、1000グラム未満を超未熟児ともいうそうですから、岡さんは極小未熟児に近かった。医療体制の整った今と違い、52年前ですから、おのずとその生死は危ぶまれたといいます。
次に、幼稚園の頃。近所の川で遊んでいた子供たちを橋の欄干から見ていた岡さんは、突然誰かに突き落とされてしまいます。岡さんはその川に投げ出されました。岡さんにこの間が記憶は全くなく、気づいたら自宅の布団で寝ていたそうです。
そして三度目は中学生の頃。蜆貝を採りに一人で出かけたとき、岡さんは勢い余って深水にはまってしまい、そこから抜け出せない状態になって気を失ってしまいました。周囲には誰もいなかったことは記憶にあるそうですが、この深水から自力で出た記憶がないといいます。このときも気づいたら土手の上で寝ていたそうです。幼稚園、中学生時代のいずれの場合も、記憶を失って意識が戻るまでのプロセスが岡さん自身にとって謎なのです。私たちにも謎です。
このような三度の隣死体験から岡さんの中で、「自分は生かされている」という認識を持たれるようになります。そして、生きていることを積極的に楽しもう、そのためには自分がやりたいことを周囲にわかるように「旗をあげる」ようにしよう、という積極的な活動につながっていきます。岡さんの仕事の核となる、い業での伝統的な「中継ぎ表」という畳の織り、これを復活させることは、その一つでした。

~畳表の伝統折である中継ぎ表は、備後地方(広島県・福島県)長谷川右衛門(1532~57)が発明し、幕府へ献上表として納めています。権力の象徴として畳は、台座、寝具としても使用されておりました。2日で1畳しかできません。現在、日本畳表手織り伝統技術者は全国で2人だけとなり備後いぐさを使用し1日~2日かけて1畳分の畳表が織られます。本場びんごいぐさ・減農薬・無農薬表を利用して、手織りオーダー可能です・・・~(有限会社 健康畳植田HP)
この二人とは、広島県福山市の広川広志さん(63)と、もうお一人が岡さんなのです。岡さんの「織り師」の肩書きはこの「中継ぎ表」織りのことを指しています。2005年、京都市上京区京丹波町にある京都御苑内に京都迎賓館が開館しました。その迎賓館に「桐の間」があって、ここの畳が「中継ぎ表」で250枚織られていますが、岡さん全国文化財畳保存会の会員として参加されました。この「中継ぎ表」を2000年熊本県「くらしの工芸展」で、飾ることをイメージしタペストリーとして出展され、みごと、い草部門でグランプリを受賞されました。

一般の畳では、日焼け防止と乾燥の時間を早めるために、専用の自然の泥(「染土(せんど)」と言います)を溶かした液にいぐさを浸してから乾燥する方法が考え出されました。これを泥染め(どろぞめ)と言います。この泥染めにより、新しい畳独特の香りと色が出てくるといいます。しかし、岡さんはこの土染めをしません。これによって畳の目につまった土を拭き取る作業が必要なくなるといメリットがありますが、「色」「ツヤ」「肌触り」すべてが染土した畳とは違って、本来のイグサの良さを出すためです。また、減農薬栽培を行うことによって、環境にも健康にも優しい畳となりまるわけです。
岡さんの師匠は勿論お父様ですが、もう一人、農林水産大臣賞を五回授賞した名古屋の河野栄さん(享年79)という方がいらっしゃいました。この河野さんでさえ染土したイグサを作っておられた程です。無染土畳表という技術がいかに高いレベルのものかがうかがい知れます。ちなみに、河野さんはかなり前に八代の岡家を訪ねたことがあるそうで、父上との交流もあったようです。一方、河野さんの晩年には彼を氏と仰ぐ仲間とともに岡さんは名古屋まで田植えの手伝いに行かれたそうですが、事情を知らない近所の人々から、「河野さんが外人部隊を連れてきた」と噂されたといいます。
苦境を強いられるイグサ生産の現状にあって、岡さんはこうした正統派のイグサを作り続け、さらにはご本人が「畳表の逆襲」と語る「香雅美(かがみ)草」の商品開発などを手がけてきました。しかし、このイグサ業の苦境の原因が主に中国産の輸入に原因だと思っていた私は、岡さんから別の要因を教えてもらいました。

「昔は冠婚葬祭のときには必ず畳換えをやったものです。日本の畳需要は実は7億畳あるんです。畳のニーズが減った理由には、中国産の輸入増といった外的要因がありますが、一般家庭でお客などの外の人を部屋に人を入れないようになったことも要因の一つです。物を買い過ぎで、特に畳の部屋が物置に化してしまっているんですね。これでは、畳換えをしようとは思わないでしょう」
「また、住宅建築でもリフォームでも、以前は畳を中心に考えた京都(京間)式でしたが、現在では建物を中心に考えた建築様式になってしまっています。イグサから和紙、PP(ポリプロピレン)への転換も進んでいますしね。全国の畳屋さんにももっと頑張って欲しいとお思いますよ」と、岡さんは淡々と語られましたが、その表情には複雑な気持ちを滲ませておられました。
岡さんにはイグサの生産者として、やれるだけのことはやってきたという自負がありました。年々縮小するマーケットの中で、イグサ生産者でいることの難しさを肌に焼き付けながら、織り師としてのプライドを持ちつつ、さらにはイグサの二次製品づくりにも着手しました。しかし、岡さんの脳裏には、果たしてこの先何年続けているだろうかという切実な緊迫感に苛まれない日はありません。そんなある日、お父様の逝去を境に、岡さんの中で長らく眠っていた生産者としての初心が芽生えたのでした。
それは、お父様が亡くなった次の年、平成11年に父上が「夢枕に立った」ことで始まりました。岡さんはこれまでもなんとなく、堆肥代わりに菜の花の残菜を使うことで自然の農業が可能になり、その田んぼでできたお米がとても美味しいということを聞いて知ってはいました。夢枕で父上が「今年の菜の花は良うできた。今年はお米もい草良う出来るバイ」と岡さんに語りかけます。
菜の花を作ってないのに、なぜそんなことを?と訝る岡さんは、これはきっと「菜の花を作りなさい」ということなのかもしれないと思ったそうです。そして、その日から間もなくして、「母の実家の妹さんの息子が畝を作ったんだけれど、今、その田んぼが空いていて勿体ないという話になりました。聞けばそこは祖母の実家の近くでもあったんですね。それなら、そこに菜の花を植えてみようかということになった」のです。

初めて岡さんとお会いしたその席で見せていただいたのが、持参されたファイルに張られていたたくさんの菜の花畑の写真でした。岡さんが手がけた「ごろっとやっちろ菜の花畑」、そこに今年3月に600万本の菜の花が咲き誇りました。ファイルの写真はそのときの写真でした。岡さんの視野には2011年の九州新幹線の全面開通が入っています。3年後の春に新幹線が八代を通過するとき、車窓から見えるのは30haの「ごろっとやっちろ菜の花畑」に咲き誇る1200万本の菜の花の黄色い絨毯の一面です。東京ドーム6.4個分の菜の花畑です。岡さんの新たな挑戦は、既に9年目を迎えました。さらに3年後にそれは、「ごろっとやっちろ菜の花畑」として大きな花を咲かせるのです。
岡さんの5月30日付のブログで菜種の収穫が無事終わったことが報告されていました。この収穫から「菜種あぶら」が生まれ、「幻の菜の花ハチミツ」が生まれます。そしてその残菜は「菜の花米」の肥料として土に栄養を与えるのです。無駄が一切ない、循環型の農業の営みが、新幹線沿線を菜の花畑にするという大きな夢とつながっていることを知るとき、岡さんの汗と笑顔に本物の生産者の気概を見るのです。

岡 初義さんへのアクセスは次のアドレスで。
「ファミリーファーム OKA」(http://www2.ocn.ne.jp/~farm-oka/)
「九州新幹線沿線は、菜の花畑」(http://blog.livedoor.jp/nanohana33/)
「FMK EVENING JOURNAL」(http://www.fmk.fm/journal/06_10_11.html)

そんな訳で、今回のゲストは「織り師」岡初義さん(51)です。インタヴューは4月22日、岡さんの八代市鏡町にあるご自宅で行いました。当日は、西田ミワさんと交流会の二次会でご縁ができた夢子さんにも同行していただくという両手に花の状態の車中でした。ナビのない私の車で、おおまかな地図と菜の花畑を頼りに向かいましたが、一度だけ通り過ぎたものの、無事到着しました。

表題の「アグリ・ファンタジスタ」は、私が勝手につけた造語です。ずば抜けた技術を持ち、創造性に富んだ、予想外のプレーを見せる天才的なサッカー選手を「ファンタジスタ」と呼ぶそうですが、岡さんのお話や仕事ぶりを実際に見て、その発想力と行動力に敬意を込め、私は岡さんをあえて「アグリ・ファンタジスタ」と呼びたいと思います。まずは、岡さんが取り組んできたイグサの世界を見ておきます。
~日本の文化は、古来、中国大陸からの伝承をもとにしたものが多いのですが、畳は大和民族の生活の知恵が生み出した固有のもので、湿度が高く、気象の変化が激しい日本の風土に、最も適した敷物として育てられ、継承されてきました。瑞穂の国にふさわしく、稲わらを利用して床をつくり、野生のいぐさを改良して畳表を織り、畳という素晴しい敷物をつくりあげたわけです。旧漢字でたたみを「疊」と書きます。これは田圃からとれる稲わらを交互に積み重ねたとの意味があります。~(全国畳産業振興会HP)
畳表は「くまもと表(おもて)」と「びんご表」がわが国では双璧だといいます。残念ながら全国的には「びんご表」の方が有名なのだそうです。熊本県のい業は、興善寺城(八代市竜峰)城代・相良伊勢守の与力であった岩崎主馬忠久公が、現在の八代郡千丁町大牟田の上土(あげつち)城主になったおり、領内の古閑淵前に永正2年(1505)、いぐさを栽培させ、製織を奨励したことが始まりとされています。一方、広島県で生産されるびんご畳表は天文、弘治(1532-57年)の頃だといいますから、「くまもと表」が日本の畳表の草分けなんですね。

岡さんはこの伝統ある八代で数少なくなったイグサ生産者のお一人です。ご承知のようにイグサは今でも八代市が全国トップの生産地ですが、近年の日本における需要の低下は関係者の方々には死活問題で、その凋落ぶりは目に余るものがあります。数年前に生産者の方の自殺が相次ぎ、この小さな町村で十数名にのぼったことも記憶に新しいところです。
「イグサの日本における主な産地は熊本県八代地方であり、国産畳表の8~9割のシェアを誇る。他には石川県・岡山県・広島県・高知県・福岡県・佐賀県・大分県でも見ることができる。一方で近年、中国などの外国産の安価なイグサが輸入され(セーフガードまで発動した)、全流通量に対し国産畳表は3~4割ほどのシェアがあり、また住宅の洋室化とも相まってイグサ生産農家の減少が危ぶまれていたが、近年になり自然素材、健康志向の高まりによりその価値に注目が集まっている」。(ウィキペディア)

この記事にあるように、近年になりイグサに注目が集っていることは事実でしょうが、2005年以降の栽培面積は1631ヘクタールと十年前の約五分の一に減少していて、面積縮小に歯止めがかからないのが現状です。そんな苦境にあるイグサ生産の当事者である岡さんですが、岡さんの発言や行動には夢がいっぱい詰まっていました。今回は、苦境にあっても夢を追いかける、まさにこのブログの表題を文字通り邁進する岡さんにお話をうかがったわけです。(1631ヘクタール≒東京ドーム350個分)
岡さんは昭和32年2月13日のお生まれで、岡家七代目の当主です。奥様と長男、次男、長女の三人のお子様がいらっしゃいます。岡さんの活躍は県内外に知れ渡っていて取材もたくさん受けられています。その模様は後述するサイトのリンクを張っておりますのでそちらをチェックしていただきたいと思います。このブログでは、岡さんの人となりについて多少なりとも迫っていければと思います。
岡さんの人生観を知る上でエポックメイキングな出来事があります。それは、岡さんがこれまで三度も死に直面していることです。最初はその人生の始まりで、出生時に1800gの未熟児だったこと。未熟児は、一般に、出生時の体重が2500グラム未満をいうそうですが、1500グラム未満を極小未熟児、1000グラム未満を超未熟児ともいうそうですから、岡さんは極小未熟児に近かった。医療体制の整った今と違い、52年前ですから、おのずとその生死は危ぶまれたといいます。
次に、幼稚園の頃。近所の川で遊んでいた子供たちを橋の欄干から見ていた岡さんは、突然誰かに突き落とされてしまいます。岡さんはその川に投げ出されました。岡さんにこの間が記憶は全くなく、気づいたら自宅の布団で寝ていたそうです。
そして三度目は中学生の頃。蜆貝を採りに一人で出かけたとき、岡さんは勢い余って深水にはまってしまい、そこから抜け出せない状態になって気を失ってしまいました。周囲には誰もいなかったことは記憶にあるそうですが、この深水から自力で出た記憶がないといいます。このときも気づいたら土手の上で寝ていたそうです。幼稚園、中学生時代のいずれの場合も、記憶を失って意識が戻るまでのプロセスが岡さん自身にとって謎なのです。私たちにも謎です。
このような三度の隣死体験から岡さんの中で、「自分は生かされている」という認識を持たれるようになります。そして、生きていることを積極的に楽しもう、そのためには自分がやりたいことを周囲にわかるように「旗をあげる」ようにしよう、という積極的な活動につながっていきます。岡さんの仕事の核となる、い業での伝統的な「中継ぎ表」という畳の織り、これを復活させることは、その一つでした。

~畳表の伝統折である中継ぎ表は、備後地方(広島県・福島県)長谷川右衛門(1532~57)が発明し、幕府へ献上表として納めています。権力の象徴として畳は、台座、寝具としても使用されておりました。2日で1畳しかできません。現在、日本畳表手織り伝統技術者は全国で2人だけとなり備後いぐさを使用し1日~2日かけて1畳分の畳表が織られます。本場びんごいぐさ・減農薬・無農薬表を利用して、手織りオーダー可能です・・・~(有限会社 健康畳植田HP)
この二人とは、広島県福山市の広川広志さん(63)と、もうお一人が岡さんなのです。岡さんの「織り師」の肩書きはこの「中継ぎ表」織りのことを指しています。2005年、京都市上京区京丹波町にある京都御苑内に京都迎賓館が開館しました。その迎賓館に「桐の間」があって、ここの畳が「中継ぎ表」で250枚織られていますが、岡さん全国文化財畳保存会の会員として参加されました。この「中継ぎ表」を2000年熊本県「くらしの工芸展」で、飾ることをイメージしタペストリーとして出展され、みごと、い草部門でグランプリを受賞されました。

一般の畳では、日焼け防止と乾燥の時間を早めるために、専用の自然の泥(「染土(せんど)」と言います)を溶かした液にいぐさを浸してから乾燥する方法が考え出されました。これを泥染め(どろぞめ)と言います。この泥染めにより、新しい畳独特の香りと色が出てくるといいます。しかし、岡さんはこの土染めをしません。これによって畳の目につまった土を拭き取る作業が必要なくなるといメリットがありますが、「色」「ツヤ」「肌触り」すべてが染土した畳とは違って、本来のイグサの良さを出すためです。また、減農薬栽培を行うことによって、環境にも健康にも優しい畳となりまるわけです。
岡さんの師匠は勿論お父様ですが、もう一人、農林水産大臣賞を五回授賞した名古屋の河野栄さん(享年79)という方がいらっしゃいました。この河野さんでさえ染土したイグサを作っておられた程です。無染土畳表という技術がいかに高いレベルのものかがうかがい知れます。ちなみに、河野さんはかなり前に八代の岡家を訪ねたことがあるそうで、父上との交流もあったようです。一方、河野さんの晩年には彼を氏と仰ぐ仲間とともに岡さんは名古屋まで田植えの手伝いに行かれたそうですが、事情を知らない近所の人々から、「河野さんが外人部隊を連れてきた」と噂されたといいます。
苦境を強いられるイグサ生産の現状にあって、岡さんはこうした正統派のイグサを作り続け、さらにはご本人が「畳表の逆襲」と語る「香雅美(かがみ)草」の商品開発などを手がけてきました。しかし、このイグサ業の苦境の原因が主に中国産の輸入に原因だと思っていた私は、岡さんから別の要因を教えてもらいました。

「昔は冠婚葬祭のときには必ず畳換えをやったものです。日本の畳需要は実は7億畳あるんです。畳のニーズが減った理由には、中国産の輸入増といった外的要因がありますが、一般家庭でお客などの外の人を部屋に人を入れないようになったことも要因の一つです。物を買い過ぎで、特に畳の部屋が物置に化してしまっているんですね。これでは、畳換えをしようとは思わないでしょう」
「また、住宅建築でもリフォームでも、以前は畳を中心に考えた京都(京間)式でしたが、現在では建物を中心に考えた建築様式になってしまっています。イグサから和紙、PP(ポリプロピレン)への転換も進んでいますしね。全国の畳屋さんにももっと頑張って欲しいとお思いますよ」と、岡さんは淡々と語られましたが、その表情には複雑な気持ちを滲ませておられました。
岡さんにはイグサの生産者として、やれるだけのことはやってきたという自負がありました。年々縮小するマーケットの中で、イグサ生産者でいることの難しさを肌に焼き付けながら、織り師としてのプライドを持ちつつ、さらにはイグサの二次製品づくりにも着手しました。しかし、岡さんの脳裏には、果たしてこの先何年続けているだろうかという切実な緊迫感に苛まれない日はありません。そんなある日、お父様の逝去を境に、岡さんの中で長らく眠っていた生産者としての初心が芽生えたのでした。
それは、お父様が亡くなった次の年、平成11年に父上が「夢枕に立った」ことで始まりました。岡さんはこれまでもなんとなく、堆肥代わりに菜の花の残菜を使うことで自然の農業が可能になり、その田んぼでできたお米がとても美味しいということを聞いて知ってはいました。夢枕で父上が「今年の菜の花は良うできた。今年はお米もい草良う出来るバイ」と岡さんに語りかけます。
菜の花を作ってないのに、なぜそんなことを?と訝る岡さんは、これはきっと「菜の花を作りなさい」ということなのかもしれないと思ったそうです。そして、その日から間もなくして、「母の実家の妹さんの息子が畝を作ったんだけれど、今、その田んぼが空いていて勿体ないという話になりました。聞けばそこは祖母の実家の近くでもあったんですね。それなら、そこに菜の花を植えてみようかということになった」のです。

初めて岡さんとお会いしたその席で見せていただいたのが、持参されたファイルに張られていたたくさんの菜の花畑の写真でした。岡さんが手がけた「ごろっとやっちろ菜の花畑」、そこに今年3月に600万本の菜の花が咲き誇りました。ファイルの写真はそのときの写真でした。岡さんの視野には2011年の九州新幹線の全面開通が入っています。3年後の春に新幹線が八代を通過するとき、車窓から見えるのは30haの「ごろっとやっちろ菜の花畑」に咲き誇る1200万本の菜の花の黄色い絨毯の一面です。東京ドーム6.4個分の菜の花畑です。岡さんの新たな挑戦は、既に9年目を迎えました。さらに3年後にそれは、「ごろっとやっちろ菜の花畑」として大きな花を咲かせるのです。
岡さんの5月30日付のブログで菜種の収穫が無事終わったことが報告されていました。この収穫から「菜種あぶら」が生まれ、「幻の菜の花ハチミツ」が生まれます。そしてその残菜は「菜の花米」の肥料として土に栄養を与えるのです。無駄が一切ない、循環型の農業の営みが、新幹線沿線を菜の花畑にするという大きな夢とつながっていることを知るとき、岡さんの汗と笑顔に本物の生産者の気概を見るのです。

岡 初義さんへのアクセスは次のアドレスで。
「ファミリーファーム OKA」(http://www2.ocn.ne.jp/~farm-oka/)
「九州新幹線沿線は、菜の花畑」(http://blog.livedoor.jp/nanohana33/)
「FMK EVENING JOURNAL」(http://www.fmk.fm/journal/06_10_11.html)
2008年05月22日
緑のコンサル事業に挑む「植木町の植木屋」池富猛(22)
今年2/20に行われた商工会の交流会。この交流会では既に第14回のゲストにお迎えした広瀬生夫さんとお会いするご縁に恵まれました。その交流会の際、私に名刺交換を申し出てくれた方がいました。物腰が柔らかく、大変礼儀正しい方でした。お年を聞くとまだ29歳。にもかかわらず、事業歴は3年とのことで私の方が恐縮してしまいました。
という訳で、第22回目のゲストは、IGL(アイ・ジー・エル)代表の池富猛さん(29)です。池富さんの事業は、観葉植物・草花のリース、販売、管理からスペース・ガーデン・箱庭の制作、管理、ガーディング工事までと、いわば、緑のトータルコンサルティング事業を手がけられています。お話をうかがったのは、玉名合同庁舎のロビー。ここに池富さんの観葉植物が納められています。写真はそのツピタンサス。

池富さんは、長崎は佐世保のご出身。お父様が観葉植物の店を経営されており、早い時期からご自分も観葉植物でビジネスを行うことを決めていました。ただし、「兄がいて、家業は兄が継ぐだろうということと、親子といえども観葉植物に対する見方が違うということを実感して、独立することを考えていました」という独立精神に富んだ青年です。
地元の高校を卒業した池富さんは、経営者になるという明確な目的を持って、1997年、東京経済大学の経営学部に進学。卒業後の2002年1月にアメリカのミネソタ州にあるバラ造り農園にiiP(インターナショナル・インターンシップ・プログラム)を利用して研修生となります。ここで1年2ヶ月の間、修行の時間を過ごされました。
iiPとは、日本と世界の国々との国際交流を目的に設立された、米国国務省認定の団体です。iiPの本部は、米国ワシントン州シアトル。1979年10月、米国コロラド州政府教育庁により16名の日本人公立高校教師が教育視察団として招聘されたことからプログラムがスタート。現在,東京事務所を拠点とし、米国ワシントン州に米国事務所を持ち、国際的レベルで教育、文化、職業交流活動を展開。以来30年近くにわたり、15,000人以上の日本人が世界各地に派遣されているそうです。
アメリカへの旅立ちは池富さんにとってははじめての海外。アメリカで観葉植物を学ぶという本分を携え、英語に自信もないまま、降り立ったのはミネソタへのトランジットとなるイリノイ州のシカゴ空港でした。しかしそこで移民局のチェックに遭い、3時間程足止めを食ってしまうというハプニングに遭います。池富さんは片言の英語で懸命に説明しますが、研修生であることをなかなか理解してもらえず、ミネソタへの乗り継ぎの時間は迫っています。トランジット便のチケットを見せても担当官は余裕の様子。そのときの模様を池富さんは次のように語ってくれました。
移民局の控え室で待機していたら、「日本人なら日本語喋ってみろ」と英語で聞かれ、「こんにちは」なんて話していたら、部屋の後ろから日本語を話すことの出来るアメリカ人の方が来てて、色々と質問をされながら説明をし、通訳的なことをして頂いたおかげでホストの方にも連絡を取っていただき、乗り継ぎ便の案内、手荷物の引き渡し当をしていただいてなんとかミネソタ便に乗り込むことが出来ました。ですが、ビザは観光ビザを取得していたので、恐らくテロ発生後だった事から書類だけでは通らなかったのだと思います。
IIPに話したときにも「今まで語学不足でも書類だけで許可は下りてたのに、そんな事は一度も無かった」とのことでしたし。ついでに、滞在許可はその時に半年しか貰えずに、延長申請をした思い出があります。
ここで池富さんが過ごしたミネソタ州について見ておきましょう。アメリカでは、ハワイ州とアラスカ州を除いた隣接48州のなかで、最北端に位置する州。寒いことで有名で、「アメリカの冷蔵庫」の異名があるのがミネソタ州です。池富さんはなぜ、数あるアメリカの州の中で、この最北端の地を選んだのか?それは、北海道より以北に育つ北方地域の植物について学ぶためでした。

ミネソタ州(Minnesota MN)は、米国中西部の北、カナダ国境に接する州。州の東にはスペリオル湖があり、州の南北をミシシッピ川が流れている。東側はウィスコンシン州に、西側はノースダコタ州とサウスダコタ州に、南側はアイオワ州に接している。州都はセントポール市。ミシシッピ川を挟んだ隣の都市であるミネアポリス市と合わせて「ツインシティーズ」と呼ばれている。ミネソタの名前はダコタ族(アメリカ・インディアン)の「空の色に染まった水」を意味する言葉から取られている。
たどり着いたホストファミリーはイスラエルからの移民だったそうです。池富さんは与えられた時間を有効に使いたいという一身で、休みもろくに取らず働いたそうです。見かねたご主人が、たまには休んだらどうだと、休みをなかば強引に与えました。池富さんは休暇先で「ランドスケープ」式の造園事業を目にしますが、山一つを庭に見立てたその事業にアメリカの造園家の規模の大ききに驚いたそうです。池富さんが滞在したホストファミリーや休暇について、池富さんに直接語ってもらいます。

滞在先はミネソタ州のセントポールから車で30分走った所にある[30分と言っても、法定速度65マイル(時速100キロ近い)でしたから、それなりの距離はありました。]、ヘイスティングス(Hastings)という田舎町でした。1年ほど前にミネソタで橋の崩落事故がおきましたが、自分もよくトゥインシティーに行く時など通っていたので驚いてホストに電話したのを覚えています。
ホストは、サム・ケデム(Sam Kedem)さんで、ポーランド人で17歳年下の奥さんのレイチェルさん。娘さんが居るらしいのですが、日本の京都の大学で講師(生徒?)をされていたみたいで、一度もお会いしたことはありません。日本に帰ってから連絡をと思っていたのですが、シカゴの大学に行かれたということで行き違いになりました。
と同時に、スロバキアから、これはミネソタ独自の制度であるMAST(ミネソタ アグリカルチャー スチュウデント トレイニィ-)という農業訓練生制度を利用して、渡米してそこのホストにお世話になっていたマーティンと、ホストの奥様の甥っ子でウクライナ人のアレックスと五人で生活していて、国際色豊かな環境でした。
休暇は二回とって、一度目は両親を誘ってアメリカ東部のボストン、ニューヨーク、ワシントンなどをその当時自分が所有していた車で周遊しました。そこでは、唯の観光と世間見物で終わりました。二度目は、近くの農場に研修に来ていたポーランドとチェコの友人と一緒に西海岸に行き、ラスベガス空港で車を借り、サンフランシスコややロサンゼルス等を回りました。
ここで、国立公園に何ヶ所か行き、ヨセミテ国立公園のセコイア杉の巨木(直径3メートル以上)に迫力を受けました。箱根の縄文杉を越す木々を見たのはここだけです。後、ランドスケープガーデンを見たのは、サンディエゴの庭師の所です。自分の家が丘陵地の頂上にあり、目下の自然は先祖が木や花を植えて、自分はそれを守ってきたのだと言うことでした。
2003年4月、ミネソタでの研修を終え帰国した池富さんは、佐世保の実家に戻り、お父様の経営する会社で実務を学びました。観葉植物を中心にした緑のトータルコンサルティング事業へ向けて、学生時代からまさにまっしぐらの道のりです。そして、満を持して2005年3月にIGL(アイ・ジー・エル)を設立されます。26歳での開業でした。
開業地に選んだのは植木町。「実家が佐世保を拠点に長崎、佐賀、福岡と展開していたので、私は熊本以南のマーケットで勝負しようと思っていました」と考えていた、そんな矢先、最初に注文を貰ったのが玉名のお客様でした。そこで、玉名にも熊本にも近いということで植木町が有力候補に挙がったのでした。「植木の植木屋って面白いんじゃないか、ということもありました」。
そして、池富さんは昨年4月に結婚され、今年2月24日にはご長男・大稀(だいき)君がお生まれになりました。奥様は小学校の同級生で、二人が25歳のときに病院で偶然に再会。池富さんはその病院へ観葉植物を納めていました。奥様はその病院に入院されていたのです。そのとき池富さんは奥様を励ますつもりで「そのうち飯でも食いに行くか?」と声をかけて分かれました。
それから仕事に邁進する池富さんは、奥様に声をかけたことなどなかば忘れていた頃、奥様と街中で再び偶然に出会うことになります。そのとき奥様から「いつ、ご飯食べに行くの?」と言われたのをきっかけに交際が始まり、昨年、二人は結ばれることになりました。私は以前、「偶然という名の運命」という自作の曲を書いたことがありますが、このようなケースをそう呼んでいます。
池富さんは現在、600坪の敷地を自分の手で造成中です。そこに観葉植物栽培用のビニールハウスを三棟建てる計画です。2010年の完成を当面の目標にしているそうです。現在の顧客は80軒。これを熊本県内全域で150~200軒まで伸ばしたいというのが池富さんの当面の目標。「ここまではなんとか一人でやっていける。そこから先に、南九州への展開が見えてくるんです」とあくまで自然体の池富さんは語ります。
池富さんにいただいた資料に、観葉植物の効用には、汚染物質浄化作用、カビ・バクテリア等の繁殖抑制作用、マイナスイオン作用、視覚作用、香り作用、エッジ効果、アートセラピー・アグリセラピー、フラシーボ効果があると書かれています。池富さんの夢は、オフィスや個人宅の室内空間を植物で潤う庭として提供すること。「きれいな植物で空間を演出し、空気清浄にも役立ち、香りも楽しんでもらえたらと思っています」と池富さんは語ります。

この資料にはそれぞれの効用について詳しいレポートがありますが、その中で、空気の清浄と汚染物質の除去が実は絶妙な関係にあることが書かれています。アメリカ航空宇宙局(NASA)が宇宙船の換気について研究した折、植物が光合成を行う際、同時に室内の汚染物質を吸収するということがわかったというのです。これ以上の情報開示は池富さんの著作権を侵害することになりますので、興味のある方は直接池富さんにお問合せくださいね。
そして、池富さんはこれから植物に電気を通して大きくする研究を行いたいそうです。雷の後に植物が大きく元気に育つことがあるそうで、これはイオンの影響によるものではないかというのが、池富さんの仮説です。とにかく、池富さんはこの植物、庭づくりに関してまっしぐらに進まれています。しかも、その姿は実に自然体です。

私は池富さんに、創業から16年で東証一部上場を果したワタミ㈱の渡邉美樹社長の姿を見ます。渡邊さんとは今から20年前に求人広告の担当営業マンとしてお付き合いさせていただきました。「夢に日付を入れる」で有名な渡邊さんのポリシーはその頃から生きていて、16年後の上場も日付が入れられていました。池富さんは当面10年計画で事業を展開されていますが、きっと10年後のIGLは南九州一円のオフィスや個人宅を観葉植物で彩ってくれているのではないかと思います。
池富さん、IGLへのアクセスは下記まで。

IGL(アイ・ジー・エル/Indoor Green Leading)/緑のトータルコンサルティング
代表 池富 猛
〒861-0154 熊本県鹿本郡植木町大字那知
TEL(096)215-3210
FAX(096)215-3218
取材が終わって別れ際に、池富さんから思わぬプレゼントをいただきました。「ピレア グラウカ」というイラクサ科の植物です。池富さん、ありがとうございました。ちゃんと育ててますよ。
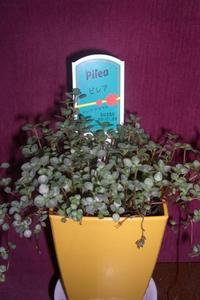
という訳で、第22回目のゲストは、IGL(アイ・ジー・エル)代表の池富猛さん(29)です。池富さんの事業は、観葉植物・草花のリース、販売、管理からスペース・ガーデン・箱庭の制作、管理、ガーディング工事までと、いわば、緑のトータルコンサルティング事業を手がけられています。お話をうかがったのは、玉名合同庁舎のロビー。ここに池富さんの観葉植物が納められています。写真はそのツピタンサス。

池富さんは、長崎は佐世保のご出身。お父様が観葉植物の店を経営されており、早い時期からご自分も観葉植物でビジネスを行うことを決めていました。ただし、「兄がいて、家業は兄が継ぐだろうということと、親子といえども観葉植物に対する見方が違うということを実感して、独立することを考えていました」という独立精神に富んだ青年です。
地元の高校を卒業した池富さんは、経営者になるという明確な目的を持って、1997年、東京経済大学の経営学部に進学。卒業後の2002年1月にアメリカのミネソタ州にあるバラ造り農園にiiP(インターナショナル・インターンシップ・プログラム)を利用して研修生となります。ここで1年2ヶ月の間、修行の時間を過ごされました。
iiPとは、日本と世界の国々との国際交流を目的に設立された、米国国務省認定の団体です。iiPの本部は、米国ワシントン州シアトル。1979年10月、米国コロラド州政府教育庁により16名の日本人公立高校教師が教育視察団として招聘されたことからプログラムがスタート。現在,東京事務所を拠点とし、米国ワシントン州に米国事務所を持ち、国際的レベルで教育、文化、職業交流活動を展開。以来30年近くにわたり、15,000人以上の日本人が世界各地に派遣されているそうです。
アメリカへの旅立ちは池富さんにとってははじめての海外。アメリカで観葉植物を学ぶという本分を携え、英語に自信もないまま、降り立ったのはミネソタへのトランジットとなるイリノイ州のシカゴ空港でした。しかしそこで移民局のチェックに遭い、3時間程足止めを食ってしまうというハプニングに遭います。池富さんは片言の英語で懸命に説明しますが、研修生であることをなかなか理解してもらえず、ミネソタへの乗り継ぎの時間は迫っています。トランジット便のチケットを見せても担当官は余裕の様子。そのときの模様を池富さんは次のように語ってくれました。
移民局の控え室で待機していたら、「日本人なら日本語喋ってみろ」と英語で聞かれ、「こんにちは」なんて話していたら、部屋の後ろから日本語を話すことの出来るアメリカ人の方が来てて、色々と質問をされながら説明をし、通訳的なことをして頂いたおかげでホストの方にも連絡を取っていただき、乗り継ぎ便の案内、手荷物の引き渡し当をしていただいてなんとかミネソタ便に乗り込むことが出来ました。ですが、ビザは観光ビザを取得していたので、恐らくテロ発生後だった事から書類だけでは通らなかったのだと思います。
IIPに話したときにも「今まで語学不足でも書類だけで許可は下りてたのに、そんな事は一度も無かった」とのことでしたし。ついでに、滞在許可はその時に半年しか貰えずに、延長申請をした思い出があります。
ここで池富さんが過ごしたミネソタ州について見ておきましょう。アメリカでは、ハワイ州とアラスカ州を除いた隣接48州のなかで、最北端に位置する州。寒いことで有名で、「アメリカの冷蔵庫」の異名があるのがミネソタ州です。池富さんはなぜ、数あるアメリカの州の中で、この最北端の地を選んだのか?それは、北海道より以北に育つ北方地域の植物について学ぶためでした。

ミネソタ州(Minnesota MN)は、米国中西部の北、カナダ国境に接する州。州の東にはスペリオル湖があり、州の南北をミシシッピ川が流れている。東側はウィスコンシン州に、西側はノースダコタ州とサウスダコタ州に、南側はアイオワ州に接している。州都はセントポール市。ミシシッピ川を挟んだ隣の都市であるミネアポリス市と合わせて「ツインシティーズ」と呼ばれている。ミネソタの名前はダコタ族(アメリカ・インディアン)の「空の色に染まった水」を意味する言葉から取られている。
たどり着いたホストファミリーはイスラエルからの移民だったそうです。池富さんは与えられた時間を有効に使いたいという一身で、休みもろくに取らず働いたそうです。見かねたご主人が、たまには休んだらどうだと、休みをなかば強引に与えました。池富さんは休暇先で「ランドスケープ」式の造園事業を目にしますが、山一つを庭に見立てたその事業にアメリカの造園家の規模の大ききに驚いたそうです。池富さんが滞在したホストファミリーや休暇について、池富さんに直接語ってもらいます。

滞在先はミネソタ州のセントポールから車で30分走った所にある[30分と言っても、法定速度65マイル(時速100キロ近い)でしたから、それなりの距離はありました。]、ヘイスティングス(Hastings)という田舎町でした。1年ほど前にミネソタで橋の崩落事故がおきましたが、自分もよくトゥインシティーに行く時など通っていたので驚いてホストに電話したのを覚えています。
ホストは、サム・ケデム(Sam Kedem)さんで、ポーランド人で17歳年下の奥さんのレイチェルさん。娘さんが居るらしいのですが、日本の京都の大学で講師(生徒?)をされていたみたいで、一度もお会いしたことはありません。日本に帰ってから連絡をと思っていたのですが、シカゴの大学に行かれたということで行き違いになりました。
と同時に、スロバキアから、これはミネソタ独自の制度であるMAST(ミネソタ アグリカルチャー スチュウデント トレイニィ-)という農業訓練生制度を利用して、渡米してそこのホストにお世話になっていたマーティンと、ホストの奥様の甥っ子でウクライナ人のアレックスと五人で生活していて、国際色豊かな環境でした。
休暇は二回とって、一度目は両親を誘ってアメリカ東部のボストン、ニューヨーク、ワシントンなどをその当時自分が所有していた車で周遊しました。そこでは、唯の観光と世間見物で終わりました。二度目は、近くの農場に研修に来ていたポーランドとチェコの友人と一緒に西海岸に行き、ラスベガス空港で車を借り、サンフランシスコややロサンゼルス等を回りました。
ここで、国立公園に何ヶ所か行き、ヨセミテ国立公園のセコイア杉の巨木(直径3メートル以上)に迫力を受けました。箱根の縄文杉を越す木々を見たのはここだけです。後、ランドスケープガーデンを見たのは、サンディエゴの庭師の所です。自分の家が丘陵地の頂上にあり、目下の自然は先祖が木や花を植えて、自分はそれを守ってきたのだと言うことでした。
2003年4月、ミネソタでの研修を終え帰国した池富さんは、佐世保の実家に戻り、お父様の経営する会社で実務を学びました。観葉植物を中心にした緑のトータルコンサルティング事業へ向けて、学生時代からまさにまっしぐらの道のりです。そして、満を持して2005年3月にIGL(アイ・ジー・エル)を設立されます。26歳での開業でした。
開業地に選んだのは植木町。「実家が佐世保を拠点に長崎、佐賀、福岡と展開していたので、私は熊本以南のマーケットで勝負しようと思っていました」と考えていた、そんな矢先、最初に注文を貰ったのが玉名のお客様でした。そこで、玉名にも熊本にも近いということで植木町が有力候補に挙がったのでした。「植木の植木屋って面白いんじゃないか、ということもありました」。
そして、池富さんは昨年4月に結婚され、今年2月24日にはご長男・大稀(だいき)君がお生まれになりました。奥様は小学校の同級生で、二人が25歳のときに病院で偶然に再会。池富さんはその病院へ観葉植物を納めていました。奥様はその病院に入院されていたのです。そのとき池富さんは奥様を励ますつもりで「そのうち飯でも食いに行くか?」と声をかけて分かれました。
それから仕事に邁進する池富さんは、奥様に声をかけたことなどなかば忘れていた頃、奥様と街中で再び偶然に出会うことになります。そのとき奥様から「いつ、ご飯食べに行くの?」と言われたのをきっかけに交際が始まり、昨年、二人は結ばれることになりました。私は以前、「偶然という名の運命」という自作の曲を書いたことがありますが、このようなケースをそう呼んでいます。
池富さんは現在、600坪の敷地を自分の手で造成中です。そこに観葉植物栽培用のビニールハウスを三棟建てる計画です。2010年の完成を当面の目標にしているそうです。現在の顧客は80軒。これを熊本県内全域で150~200軒まで伸ばしたいというのが池富さんの当面の目標。「ここまではなんとか一人でやっていける。そこから先に、南九州への展開が見えてくるんです」とあくまで自然体の池富さんは語ります。
池富さんにいただいた資料に、観葉植物の効用には、汚染物質浄化作用、カビ・バクテリア等の繁殖抑制作用、マイナスイオン作用、視覚作用、香り作用、エッジ効果、アートセラピー・アグリセラピー、フラシーボ効果があると書かれています。池富さんの夢は、オフィスや個人宅の室内空間を植物で潤う庭として提供すること。「きれいな植物で空間を演出し、空気清浄にも役立ち、香りも楽しんでもらえたらと思っています」と池富さんは語ります。

この資料にはそれぞれの効用について詳しいレポートがありますが、その中で、空気の清浄と汚染物質の除去が実は絶妙な関係にあることが書かれています。アメリカ航空宇宙局(NASA)が宇宙船の換気について研究した折、植物が光合成を行う際、同時に室内の汚染物質を吸収するということがわかったというのです。これ以上の情報開示は池富さんの著作権を侵害することになりますので、興味のある方は直接池富さんにお問合せくださいね。
そして、池富さんはこれから植物に電気を通して大きくする研究を行いたいそうです。雷の後に植物が大きく元気に育つことがあるそうで、これはイオンの影響によるものではないかというのが、池富さんの仮説です。とにかく、池富さんはこの植物、庭づくりに関してまっしぐらに進まれています。しかも、その姿は実に自然体です。

私は池富さんに、創業から16年で東証一部上場を果したワタミ㈱の渡邉美樹社長の姿を見ます。渡邊さんとは今から20年前に求人広告の担当営業マンとしてお付き合いさせていただきました。「夢に日付を入れる」で有名な渡邊さんのポリシーはその頃から生きていて、16年後の上場も日付が入れられていました。池富さんは当面10年計画で事業を展開されていますが、きっと10年後のIGLは南九州一円のオフィスや個人宅を観葉植物で彩ってくれているのではないかと思います。
池富さん、IGLへのアクセスは下記まで。

IGL(アイ・ジー・エル/Indoor Green Leading)/緑のトータルコンサルティング
代表 池富 猛
〒861-0154 熊本県鹿本郡植木町大字那知
TEL(096)215-3210
FAX(096)215-3218
取材が終わって別れ際に、池富さんから思わぬプレゼントをいただきました。「ピレア グラウカ」というイラクサ科の植物です。池富さん、ありがとうございました。ちゃんと育ててますよ。
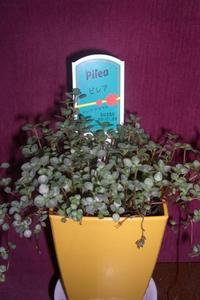
2008年04月20日
屈強の警部から保育所経営者への転進、友田秀一(21)
先日コミュニティ紙を眺めていたら、「働くお母さんを支援したい~24時間体制の保育施設~マザーハウス保育所」という紹介記事に目が留まりました。社長さんは行政書士・友田秀一と書かれていました。行政書士の方がなぜ、保育所経営に乗り出されたのかと、私は早速、4/2にこの保育所を直接訪ね、受付の方に友田社長への取材を申出ました。この日はあいにく友田さんが不在でしたので、資料だけ預けて保育所を後にしました。
一週間が経ったころ、取材を受けていただけるかどうか確認の連絡を入れたところ、取材は土曜日ならOKとの了解を得、4/12にお時間をいただきました。訪問前に改めてこのマザーハウス保育所のことをネットで検索してみて、私はちょっと腰が引けました。それは最初に見過ごしていた友田さんの経歴でした。人吉市出身、1955(昭和30)年4月生まれ。そして・・・

昭和49年4月3日付けで熊本県巡査を拝命し、平成19年3月に退職するまで、そのほとんどを熊本市内警察署、熊本県警察本部で暴力団捜査部門の刑事として従事。暴力団の対立抗争事件捜査や殺人事件をはじめ各種事件捜査に従事し、その後、暴力団の武器であるけん銃の捜査や資金源となる覚せい剤など麻薬捜査の経歴を持つ。警察在籍33年の内、捜査経歴28年の経験から裁判立証のための行動確認、尾行の技術は、他社に負けぬ自信を持つ。
在籍時、各種事件の功労として熊本県警察本部長賞詞6回、(うち、優秀警察官表彰を受賞、警察庁課長賞2回、九州管区警察公安部長賞2回、熊本県警察本部長賞誉18回、その他各部長賞、所属長賞数十回を受賞。退職時、警部に昇任し、熊本県警察本部長功績賞を受賞。平成19年5月、熊本県公安委員会第100186号、第200129号で警備員指導教育責任者資格を取得。同月行政書士資格取得し、友田行政書士事務所を開業。
車を運転しているときパトカーを発見しただけで萎縮してしまう小心者の私は、これまで「刑事」と名のつく方と接触したことがなく、しかも昨年までバリバリの暴力団捜査の警察官と聞けばおのずと緊張感が高まってしまいます。そんな訳で、恐れ多くも第21回目のゲストは、株式会社マザーハウス保育所・代表取締役で行政書士の友田秀一(53)さんです。
友田さんが警察官だったということは公務員だったということです。小心者の私ではありますが、友田さんが定年を前に退官されたことについて、その事情をどうしてもうかがいたくなるところです。経歴を見ればわかるように、友田さんの警察官としての実績には非の打ちどころがありません。恐る恐るうかがった友田さんの退職理由は、一言で言えば、組織の中で生きることの難しさでした。(スイマセン、お話の内容上、ここでは詳しく書けません)友田さんは退職される前年の10月には、上司の方に退職を申出られたそうです。しかし、それは随分も前に友田さんの中では決まっていたことでした。
退職後の友田さんの計画には行政書士としての仕事に加え、「安全アドバイザー」という新しい仕事の立ち上げが念頭にありました。これまでの刑事としての経験から、刑事事件に発展するようなケースで、被害者が事前に警察へ駆け込むまでにはかなりの時間を要していることがわかっていました。一方で家裁、弁護士などへの相談もなかなか敷居が高いと思われていたことも。友田さんはこの間を繋ぐことができれば、少しでも被害者を少なくする手伝いができる筈だと思われました。それが「安全アドバイザー」としての起業になります。
そして、満を持して昨年3月に惜しまれながら退職。ご家族はさぞや安心されたことだろうと思います。これまでの切った張ったの命がけの仕事から解放されたのは友田さんご本人だけでありません。ご家族こそ、これから初めての平穏な生活がその日から始まるのです。退職後の行政書士としての仕事は、これまでのお付き合いから企業の顧問契約の話もあり、順調なスタートでした。
友田さんが行政書士として独立して人脈を拡げておられたそんなある日、二人の方から友田さんに声がかけられました。株式会社阿蘇ナチュラル・Jファーム、代表取締役の森光臣さんと熊本県医師会・婦人の会・副会長で日本エジプト協会熊本会長の西郷澪子さんでした。お二人のお話は、既に設立されていた、シングルマザーを中心とした働く母親支援を目的とするテイクアウトキッチンの建て直しに一役かって欲しいというものでした。
聞けば、テイクアウトキッチン事業と保育事業を両立させたいということで始められたのですが、コスト問題などが大きく立ちふさがり、いったんテイクアウトキッチン事業を撤退し、保育事業に特化した形で再開することになったということでした。お二人からの要望は、友田さんにこの事業の経営責任者になってほしいというもの。友田さんはいきなり経営者になってくれと要請され、戸惑います。
ご家族に相談されたところ、大反対。よそ様の子供を預かるということの責任は、暴力団と対峙すること以上に重いものだということを切々と訴えられました。ご家族にとっては、やっと平穏な暮らしが始まると思っていた矢先だけに、ひと様の幼子を預かるという新たな緊張感は精神的に大きな負担です。友田さんにも家族の心配は理解できますし、むしろ自分自身が経営者としてやっていけるかどうかの不安の方が先立ちます。唯一の関係といえば、お姉さまが長年保育士であったということだけでした。
そこに第三の人物が現れます。九州柳河精機㈱会長で菊南運輸倉庫㈱会長の杉田貞治さんです。友田さんは杉田さんの話を聞きながら次第に就任への気持ちに傾いていきました。杉田さんから出る話は、退官後も友田さんが思い描いていた弱者への支援という理念に通じるものでした。そして、杉田さんからの次のことばが友田さんの心を打ちました。それは「見返りを求めない奉仕の心で取り組んでくれませんか」という一言でした。
「全国初となった慈恵病院の『こうのとりのゆりかご』がありますね。同じ熊本県民としてこの問題を重く受け止め、私たちにも何かできないかと考えたとき、働くお母さんの子育てを支援することを志して設立されたのがこの保育所です。私に声がかけられたのも何かの縁と、挑戦することを決めました」。
「子供は悪さをするために生まれてくるのではありませんね。私は、長年暴力団の連中と接してきましたが、彼らももとを糾せば赤ん坊だったわけで、幼児教育に遡ることができます。ということは、お母さんが子供に対して愛情を惜しみなく注げるような環境づくりのお手伝いをすること、つまり母親支援をすることが健全な子育てにとって最も有効なのだと思ったわけです」。
そして、今年の1月、友田さんは(株)マザーハウス保育所の代表取締役に就任されました。年中無休の24時間運営体制。急な用事で子供を預けなければならなくなったといった場合にも対応できといいます。体験入所も随時受け入れ可能。何しろ24時間体制です。その施設の最高責任者が友田さんです。それだけに就任当初の友田さんは寝付かれなかったそうです。

0歳児から小学生までの預かりと保育。料金は1日預かり(8時間)1600円から、昼夜の月決め2万円からで、年齢によって変わるシステム。これから同保育所では、手作り給食などを通じて食育にも重点を置いていく予定。これは、ドイツ国際食肉加工見本市( 2002)における国際コンクールで数々の金賞を受賞している株式会社阿蘇ナチュラル・Jファームが責任を持って提供していかれます。また、将来的には、英語、音楽を取り入れた情操教育も導入する計画とのこと。
マザーハウス保育所は、旧ブライダルマリエビル全フロア(1~6階)を活用しています。各フロアの床面積は約80㎡で、1回は受付及び0歳児用託児スペース、2・4階はプレールーム、3階は厨房と食堂、5階は保健室とプレールーム、6階は会議室及び職員事務室と、とにかく広いスペースです。現在は60名近くの契約ですが、このキャパシティからすればまだまだ余力があります。
さらに保育士の方々も募集中です。5:00~12:00、12:00~20:00のいずれかで働ける方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか?現在は7名の方が勤務されています。「保育園自体が今年1月からのスタートですから、職場としての環境や制度をこれから作っていくことにやりがいを感じられる人なら積極的に採用したい」と友田さんは話しておられました。
今回のインタヴューでは、友田さんの前職時代の武勇伝も数多くお聞きしましたが、残念ながらここでご紹介することはできません。長年暴力団と対峙されてきた警察官としての屈強さを感じ入りながら、(株)マザーハウス保育所の社長としての友田さんの印象は、実に穏やかで腰の低い方。しかし、シングルマザーをはじめ、弱者を守るという友田さんのミッションは今も変わらずに続いているのでした。
㈱マザーハウス保育所
〒860-0803
熊本市新市街13-19
TEL&FAX 096-351-6400
http://www.tomokk.com/24hhoiku.html
一週間が経ったころ、取材を受けていただけるかどうか確認の連絡を入れたところ、取材は土曜日ならOKとの了解を得、4/12にお時間をいただきました。訪問前に改めてこのマザーハウス保育所のことをネットで検索してみて、私はちょっと腰が引けました。それは最初に見過ごしていた友田さんの経歴でした。人吉市出身、1955(昭和30)年4月生まれ。そして・・・

昭和49年4月3日付けで熊本県巡査を拝命し、平成19年3月に退職するまで、そのほとんどを熊本市内警察署、熊本県警察本部で暴力団捜査部門の刑事として従事。暴力団の対立抗争事件捜査や殺人事件をはじめ各種事件捜査に従事し、その後、暴力団の武器であるけん銃の捜査や資金源となる覚せい剤など麻薬捜査の経歴を持つ。警察在籍33年の内、捜査経歴28年の経験から裁判立証のための行動確認、尾行の技術は、他社に負けぬ自信を持つ。
在籍時、各種事件の功労として熊本県警察本部長賞詞6回、(うち、優秀警察官表彰を受賞、警察庁課長賞2回、九州管区警察公安部長賞2回、熊本県警察本部長賞誉18回、その他各部長賞、所属長賞数十回を受賞。退職時、警部に昇任し、熊本県警察本部長功績賞を受賞。平成19年5月、熊本県公安委員会第100186号、第200129号で警備員指導教育責任者資格を取得。同月行政書士資格取得し、友田行政書士事務所を開業。
車を運転しているときパトカーを発見しただけで萎縮してしまう小心者の私は、これまで「刑事」と名のつく方と接触したことがなく、しかも昨年までバリバリの暴力団捜査の警察官と聞けばおのずと緊張感が高まってしまいます。そんな訳で、恐れ多くも第21回目のゲストは、株式会社マザーハウス保育所・代表取締役で行政書士の友田秀一(53)さんです。
友田さんが警察官だったということは公務員だったということです。小心者の私ではありますが、友田さんが定年を前に退官されたことについて、その事情をどうしてもうかがいたくなるところです。経歴を見ればわかるように、友田さんの警察官としての実績には非の打ちどころがありません。恐る恐るうかがった友田さんの退職理由は、一言で言えば、組織の中で生きることの難しさでした。(スイマセン、お話の内容上、ここでは詳しく書けません)友田さんは退職される前年の10月には、上司の方に退職を申出られたそうです。しかし、それは随分も前に友田さんの中では決まっていたことでした。
退職後の友田さんの計画には行政書士としての仕事に加え、「安全アドバイザー」という新しい仕事の立ち上げが念頭にありました。これまでの刑事としての経験から、刑事事件に発展するようなケースで、被害者が事前に警察へ駆け込むまでにはかなりの時間を要していることがわかっていました。一方で家裁、弁護士などへの相談もなかなか敷居が高いと思われていたことも。友田さんはこの間を繋ぐことができれば、少しでも被害者を少なくする手伝いができる筈だと思われました。それが「安全アドバイザー」としての起業になります。
そして、満を持して昨年3月に惜しまれながら退職。ご家族はさぞや安心されたことだろうと思います。これまでの切った張ったの命がけの仕事から解放されたのは友田さんご本人だけでありません。ご家族こそ、これから初めての平穏な生活がその日から始まるのです。退職後の行政書士としての仕事は、これまでのお付き合いから企業の顧問契約の話もあり、順調なスタートでした。
友田さんが行政書士として独立して人脈を拡げておられたそんなある日、二人の方から友田さんに声がかけられました。株式会社阿蘇ナチュラル・Jファーム、代表取締役の森光臣さんと熊本県医師会・婦人の会・副会長で日本エジプト協会熊本会長の西郷澪子さんでした。お二人のお話は、既に設立されていた、シングルマザーを中心とした働く母親支援を目的とするテイクアウトキッチンの建て直しに一役かって欲しいというものでした。
聞けば、テイクアウトキッチン事業と保育事業を両立させたいということで始められたのですが、コスト問題などが大きく立ちふさがり、いったんテイクアウトキッチン事業を撤退し、保育事業に特化した形で再開することになったということでした。お二人からの要望は、友田さんにこの事業の経営責任者になってほしいというもの。友田さんはいきなり経営者になってくれと要請され、戸惑います。
ご家族に相談されたところ、大反対。よそ様の子供を預かるということの責任は、暴力団と対峙すること以上に重いものだということを切々と訴えられました。ご家族にとっては、やっと平穏な暮らしが始まると思っていた矢先だけに、ひと様の幼子を預かるという新たな緊張感は精神的に大きな負担です。友田さんにも家族の心配は理解できますし、むしろ自分自身が経営者としてやっていけるかどうかの不安の方が先立ちます。唯一の関係といえば、お姉さまが長年保育士であったということだけでした。
そこに第三の人物が現れます。九州柳河精機㈱会長で菊南運輸倉庫㈱会長の杉田貞治さんです。友田さんは杉田さんの話を聞きながら次第に就任への気持ちに傾いていきました。杉田さんから出る話は、退官後も友田さんが思い描いていた弱者への支援という理念に通じるものでした。そして、杉田さんからの次のことばが友田さんの心を打ちました。それは「見返りを求めない奉仕の心で取り組んでくれませんか」という一言でした。
「全国初となった慈恵病院の『こうのとりのゆりかご』がありますね。同じ熊本県民としてこの問題を重く受け止め、私たちにも何かできないかと考えたとき、働くお母さんの子育てを支援することを志して設立されたのがこの保育所です。私に声がかけられたのも何かの縁と、挑戦することを決めました」。
「子供は悪さをするために生まれてくるのではありませんね。私は、長年暴力団の連中と接してきましたが、彼らももとを糾せば赤ん坊だったわけで、幼児教育に遡ることができます。ということは、お母さんが子供に対して愛情を惜しみなく注げるような環境づくりのお手伝いをすること、つまり母親支援をすることが健全な子育てにとって最も有効なのだと思ったわけです」。
そして、今年の1月、友田さんは(株)マザーハウス保育所の代表取締役に就任されました。年中無休の24時間運営体制。急な用事で子供を預けなければならなくなったといった場合にも対応できといいます。体験入所も随時受け入れ可能。何しろ24時間体制です。その施設の最高責任者が友田さんです。それだけに就任当初の友田さんは寝付かれなかったそうです。

0歳児から小学生までの預かりと保育。料金は1日預かり(8時間)1600円から、昼夜の月決め2万円からで、年齢によって変わるシステム。これから同保育所では、手作り給食などを通じて食育にも重点を置いていく予定。これは、ドイツ国際食肉加工見本市( 2002)における国際コンクールで数々の金賞を受賞している株式会社阿蘇ナチュラル・Jファームが責任を持って提供していかれます。また、将来的には、英語、音楽を取り入れた情操教育も導入する計画とのこと。
マザーハウス保育所は、旧ブライダルマリエビル全フロア(1~6階)を活用しています。各フロアの床面積は約80㎡で、1回は受付及び0歳児用託児スペース、2・4階はプレールーム、3階は厨房と食堂、5階は保健室とプレールーム、6階は会議室及び職員事務室と、とにかく広いスペースです。現在は60名近くの契約ですが、このキャパシティからすればまだまだ余力があります。
さらに保育士の方々も募集中です。5:00~12:00、12:00~20:00のいずれかで働ける方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか?現在は7名の方が勤務されています。「保育園自体が今年1月からのスタートですから、職場としての環境や制度をこれから作っていくことにやりがいを感じられる人なら積極的に採用したい」と友田さんは話しておられました。
今回のインタヴューでは、友田さんの前職時代の武勇伝も数多くお聞きしましたが、残念ながらここでご紹介することはできません。長年暴力団と対峙されてきた警察官としての屈強さを感じ入りながら、(株)マザーハウス保育所の社長としての友田さんの印象は、実に穏やかで腰の低い方。しかし、シングルマザーをはじめ、弱者を守るという友田さんのミッションは今も変わらずに続いているのでした。
㈱マザーハウス保育所
〒860-0803
熊本市新市街13-19
TEL&FAX 096-351-6400
http://www.tomokk.com/24hhoiku.html
2008年04月15日
からだから人生の看護へ、FP広瀬美貴子の挑戦(20)
第20回目のゲストは、㈱Fineプロデュース代表取締役・広瀬美貴子さん。広瀬さんのことはFMKに出演されていた番組を聞いて知りました。そのとき、子供たちに金銭教育、キャリア教育を施すことの重要性について、「世の中のすべてにおける分野で、自分で気づき・考えて・行動する教育。世の中のことを伝える教育が必要で、学校と家庭と地域との連携、家庭が社会へ巣立つための経験の場となるような親子のかかわりやコミュニケーションが大切」だという思いを語っておられたのが印象的でした。
いつかはお会いしたいなと思っていたころ、第17回目のゲスト・西田ミワさんにお話を伺った際、西田さんから尊敬する女性としてご紹介を受けたのがその広瀬さんでした。また、そのときにいただいた「夢を形に・起業家たちの人間力」という本に、前回の江浦誠さんと一緒に執筆陣の一人として登場されていたのが広瀬さんでした。不思議なご縁です。そして、お会いする前にHPや本などでご経歴を拝見してみて、その縦横無尽な活躍ぶりに目を見張ったのでした。

広瀬さんの現在の肩書きは、次のようになっています。「ファイナンシャル・プランナー」、「金融知力普及協会認定インストラクター」、「キャリアカウンセラー(JCDA認定)」、「産業カウンセラー」、「FP協会熊本県支部幹事」、「熊本県金融広報アドバイザー」。掲載記事を読むと、広瀬さんの職業人としてのスタートは看護師となっていました。一見すると全く畑違いのこれらの肩書きがいつ、どんな経緯で移り変わっていったのか、関心が高まったのでした。
広瀬さんの詳しいご経歴、事業の内容についてはリンクを張ったHPやパブリシティなどで後程確認していただくとして、私の興味は、看護師であった広瀬さんがファイナンシャル・プランナーに転進するまでの経緯と、これからどんな方向へ進まれようとしていらっしゃるのかということです。今回、学校での講演やワークショップで連日ご多忙の中の一時間をいただきお話をいただきました。
広瀬さんは高校卒業を前にご両親から県立大学への進学を薦められますが、心中秘かに「東京に行きたい」という思いを募らせていた広瀬さんは、心臓病で長く苦しんだお兄様へとの関わりと、東京にあって全寮制、奨学金支給という魅力もあいまって看護師を志すことに決めます。品川区五反田にある関東逓信病院(現・NTT東日本関東病院)附属高等看護学院への受験を願い出て、ご両親の承諾を得られました。そして、13倍の難関を突破し見事に入学を果されます。

25年前の当時、関東逓信(ていしん)病院は日本で最先端のシステムを導入していて、すでにコンピュータ化もかなり進んでいたそうです。また、授業では講師陣も優秀な先生方に学び、看護も医療チームの一員としての役割を実践で学ばれました。学院卒業後は、看護師として勤務早々ながらも9日間の休暇が与えられ、この休暇を使って海外旅行を経験されたりと、申し分のない社会人としてのスタートでした。折りしも二年後、小学校の同級生だった彼が大学生として上京して来て再会。ここで大人の恋も芽生えます。このときの大学生は、後のご主人です。
しかしながら、この世の春は、咲き誇る桜の花が瞬く間に散りゆくように、そう長くは続きませんでした。お父様が突然倒れられて、熊本へ帰ることを余儀なくされたのです。憧れの東京での暮らしはあえなく三年間で幕引きとなりました。同時に、彼との都合四年間の遠距離恋愛の始まりでもありました。後ろ髪を惹かれる思いで熊本に戻った広瀬さんは、熊本赤十字病院に就職されます。
熊本赤十字病院といえば県内でも屈指の病院ですが、当時でも県内では先端の病院であったはずです。しかしながら、広瀬さんが東京で勤めていたのは日本で最先端の病院でした。この二つの病院の医療体制の大きな隔たりを前に広瀬さんは愕然とします。東京では看護に専念できた日々でしたが、熊本では休みを取ることもままならい忙しさに加え、看護以外の事務作業が追い討ちをかけました。(あくまで当時の話です)広瀬さんの中で、カルチャーショックと看護師が医療チームとして認めらないことへのストレス、そして体力的な消耗が、看護師としての希望を次第に失わせていきました。
「自分にとって看護師という職業は一生続けていける仕事なのだろうかという疑問がわいたんですね」。この間、広瀬さんの中で、お父様が40歳で起業されていたこともあって、組織の中で仕事をするよりも、自分で起業したいという思いが芽生えだしました。「漠然とでしたが、私も40までに起業をしたいなと思うようになったんです」と。
そんな鬱屈とした日々の中で、意中の彼が熊本の銀行に就職を果し、戻って来ました。長かった遠距離恋愛が一気に燃え上がり、平成2年2月に結婚。広瀬さんは、ご主人の意向もあって結婚退職の道を選ばれます。その後三人の子宝に恵まれ、専業主婦の生活を過ごされますが、三度目の出産後にご自分の今後の人生に目を向けられるようになった広瀬さんは、簿記とコンピュータの勉強を始められます。
結婚から6年後、広瀬さんは、とある小さな株式会社に勤めることになります。そこで、総務・経理・労務を担当する中、社内の若者たちの多重債務状況とそのかかわりを通して、金銭教育の必要性を強く意識されるようになりました。元看護師としての職業的意識が、心の医療ともいうべきカウンセラーへと変質して芽生えたのがこの時期でした。
「『金銭教育』をするためにお金のプロになりたいと思ったときに知ったのがファイナンシャル・プランナーだったんです」。この資格を取るための勉強の時間を作るために仕事もパートに切り換え、車を使う営業の仕事をするようになられます。「遠距離を走る仕事でしたが、私にとっては車の中でテープを聴きながら勉強できたいい時間でした」と楽しい思い出を話すように語られましたが、夜は子育てが終わって11時頃まで、朝は4時起きという五ヶ月間に及ぶ勉強を続けておられました。
「夜11時頃に寝ることが質の良い睡眠になるというので、それなら4時起きでもいけるかなって思ってやってました」。この成果あって、念願のファイナンシャル・プランナーの資格を取得。次に、自分が伝えたいことをきちんと相手に伝える技術の必要性を感じた広瀬さんは、「NPO法人金融知力普及協会認定インストラクター」養成講座も受講をしました。「自らの活動の中で、セミナーを開催するときに必要となる、効果的に話す方法や、アイコンタクトのとりかた、質問の投げかけ方やシナリオの組み立て方などを学ぶことができました」。目標に向かって一気に邁進する広瀬さんの行動力に脱帽です。
しかし取得直後の活動は思うようには進みませんでした。「金銭教育の活動をしたくても無名だったため、活動の場がありませんでした」。そんな中、初めは、自分がやりたいと思っている方向性と同じ内容について開催しているセミナーやワークショップに手伝いとして参加したり、チラシ配布やDM発送などきっかけを掴むための地道な努力が続きます。
そんな中、九州の金銭教育では草分け的存在の方のセミナーに参加したことがきっかけでその方のサポートをするようになられます。その後、講師を任されるようになり一人で鹿児島や沖縄に飛び回る日々を過ごされます。そして、資格取得から1年半ほど過ぎたころ、初めて訪れたチャンスが、お子さんが通う学校のPTA主催の「金銭教育」のセミナーでした。
そして、2004年12月、念願の自主開催でのワークショップを企画・開催。以降ワークショップを続け、その都度プレスリリース(ニュースリリース)をいろいろなメディアに送ったところ、後にメディアからの取材につながり、新聞に取り上げてもらうなど、広瀬さんの名前と活動が少しずつ認知されるようになりました。9月に投げ込んだDMが半年後のレスポンスに繋がりました。
この雌伏の日々の活動が、厳しい寒さに耐えた桜の蕾が時期を得て力強い花を咲かせるように、広瀬さんのもとへ様々なオファーを舞い込ませました。「市の登録講師となり、県の金融広報委員会からの依頼で金融広報アドバイザーになり、市の総合女性センター、公民館などで講師をさせていただくなど、活動の場が拡がりました」と。

広瀬さんの活動実績を見ると、学校関係のセミナーでの講演が実に多いのですが、ここでの話は次ぎの信念に根ざした内容になっています。
「子供たちが手にするお小遣いはどこから来るのか?それはもちろん、ご両親の収入からです。言いかえればご両親の『稼ぎ』の中からです。この『稼ぐ』ことの意味を問いかけなければいけないと思っているんです。つまり、金銭教育とキャリア教育は車の両輪なんですね」。
現在、広瀬さんの視線は学生から社会人へと広がっています。「より良く働く人のための支援は、結果的に企業収益の向上につながるんです。ストレスを抱えて保健室で過ごしてきた子供たちが、将来社会人になったときにストレスを発散する場がない。そんな場を提供していきたいんですね。企業へのカウンセリングと人材教育のアウトソーシングを目指しています」。
広瀬さんから「EAP」という言葉を聞きました。「Employee Assistance Program」の略で、「従業員のメンタルヘルス対策支援。社員が抱える職場や家族、健康に関する悩みへの相談を受け付ける体制作りのこと。生産性の向上や優秀な人材の離職防止といった効果がある」手法です。
EAPの具体的な活動内容には、(1)社員の啓もう、(2)電話や電子メール、対面によるカウンセリング、(3)部下との接し方やストレス除去法の教育研修、(4)専門医への紹介などがあります。上司が問題意識のない社員を相談に行くように促したり、気軽に社員が相談できる体制作りまで実施する点が特徴。EAPを導入すれば、社員の欠勤や医療費の削減につながります。さらに、社員の悩みを無くし快適に働ける職場作りをすることで、生産性を向上したり、優秀な人材の流出を阻止するといった効果も期待できます。(日経情報ストラテジー2002/10/29)
実際、カウンセリングの資格を持ちながら、この資格を活かせない方々が少なくないといいます。広瀬さんの目標は、県内の企業経営者に、従業員の方々のストレスを解消することで結果的に収益につながるということを理解してもらい、こういったソフトへの投資を活発化させること。そうすることで潜在カウンセラーたちの活躍の場を提供することにもつながるという狙いです。
さらに、広瀬さんの視線には企業の資金調達の支援活動も入っています。「現在、公的機関による助成金をはじめ、経済産業省や中小企業基盤機構などの様々な機関、財団等から出されているもので、実は3,000種類位あるんですね。ただこうした制度について余りにも情報不足です。特に中小企業にとっては返さなくても良い資金である助成金の存在は貴重な財源です。もちろん所定の審査はありますが、内容によっては数千万~億単位の助成金を受けることも可能なんです。私たちはこの助成金獲得への書類作成などのサポートができます」。
三年後の広瀬さんはどうなっているのかをご本人に尋ねてみました。「仕事をとってくるのが経営者の本質だとしたら、私はそうした経営者にはなれないと思います。自分の手や言葉で直接関わって行きたいんです。そういった意味では、三年後も今と同じ。それに加えてコーディネーターをやっているかもしれません。カウンセリングのアウトソーシングを実現したいんです」。
私が広瀬さんを知ったFMKの番組で司会者が広瀬さんに「社会の看護師みたいですね」と言ったことが、「ちょっぴり嬉しかったですね」と話す広瀬さん。冒頭で私は、「看護師であった広瀬さんがファイナンシャル・プランナーに転進するまでの経緯」と書きましたが、広瀬さんにとってそれは「転進」ではなく、「階段を上る」ことだったんだなと思うようになりました。それは、「からだの健康」から「こころの健康」の看護への夢の途中なのだと思うようになりました。
最後に「県知事になれと言われたら何から手をつけたいですか?」と唐突な質問を投げかけてみました。「んー、やりたいことはたくさんありますが・・・。まずは、中学校教育の現場改革ですね。社会につながった教育改革。キャリア教育のできる先生を増やしたいですね。金銭教育、キャリア教育、法教育、食教育、環境教育などは産業界や法曹界、専門家などとの交流が大切です。これまでの教育界の垣根を取っ払って、社会に繋がった教育を実現したいです」と、そのお応えには全く迷いがありませんでした。

週末は阿久根、都城への講演活動に向かうという広瀬さん。今後の更なるご活躍に期待します。そして、蒲島新知事に、広瀬美貴子さんを政策ブレーンとして採用されることをお奨めして、終わります。
<株式会社Fineプロデュースの理念>
Fineな人生 働く人々に、イキイキとした自分らしい仕事人生をプロデュース
Fineな企業 がんばる企業に、人的資源・資金・信用力アップをプロデュース
Fineな社会 働く人と企業のFineで、より良い社会の実現を目指す!
株式会社Fineプロデュース 広瀬 美貴子
〒860-0085 熊本市高平2-25-45日進ビル302号
Tel 096-346-0611 Fax 096-346-0610
E-mail info@fine-produce.co.jp
All Aboutメールマガジン「フォーエル」連載記事「話題のおシゴトに就きたい」
http://forl.allabout.co.jp/L/popularjob/060503/lr04305/
いつかはお会いしたいなと思っていたころ、第17回目のゲスト・西田ミワさんにお話を伺った際、西田さんから尊敬する女性としてご紹介を受けたのがその広瀬さんでした。また、そのときにいただいた「夢を形に・起業家たちの人間力」という本に、前回の江浦誠さんと一緒に執筆陣の一人として登場されていたのが広瀬さんでした。不思議なご縁です。そして、お会いする前にHPや本などでご経歴を拝見してみて、その縦横無尽な活躍ぶりに目を見張ったのでした。

広瀬さんの現在の肩書きは、次のようになっています。「ファイナンシャル・プランナー」、「金融知力普及協会認定インストラクター」、「キャリアカウンセラー(JCDA認定)」、「産業カウンセラー」、「FP協会熊本県支部幹事」、「熊本県金融広報アドバイザー」。掲載記事を読むと、広瀬さんの職業人としてのスタートは看護師となっていました。一見すると全く畑違いのこれらの肩書きがいつ、どんな経緯で移り変わっていったのか、関心が高まったのでした。
広瀬さんの詳しいご経歴、事業の内容についてはリンクを張ったHPやパブリシティなどで後程確認していただくとして、私の興味は、看護師であった広瀬さんがファイナンシャル・プランナーに転進するまでの経緯と、これからどんな方向へ進まれようとしていらっしゃるのかということです。今回、学校での講演やワークショップで連日ご多忙の中の一時間をいただきお話をいただきました。
広瀬さんは高校卒業を前にご両親から県立大学への進学を薦められますが、心中秘かに「東京に行きたい」という思いを募らせていた広瀬さんは、心臓病で長く苦しんだお兄様へとの関わりと、東京にあって全寮制、奨学金支給という魅力もあいまって看護師を志すことに決めます。品川区五反田にある関東逓信病院(現・NTT東日本関東病院)附属高等看護学院への受験を願い出て、ご両親の承諾を得られました。そして、13倍の難関を突破し見事に入学を果されます。

25年前の当時、関東逓信(ていしん)病院は日本で最先端のシステムを導入していて、すでにコンピュータ化もかなり進んでいたそうです。また、授業では講師陣も優秀な先生方に学び、看護も医療チームの一員としての役割を実践で学ばれました。学院卒業後は、看護師として勤務早々ながらも9日間の休暇が与えられ、この休暇を使って海外旅行を経験されたりと、申し分のない社会人としてのスタートでした。折りしも二年後、小学校の同級生だった彼が大学生として上京して来て再会。ここで大人の恋も芽生えます。このときの大学生は、後のご主人です。
しかしながら、この世の春は、咲き誇る桜の花が瞬く間に散りゆくように、そう長くは続きませんでした。お父様が突然倒れられて、熊本へ帰ることを余儀なくされたのです。憧れの東京での暮らしはあえなく三年間で幕引きとなりました。同時に、彼との都合四年間の遠距離恋愛の始まりでもありました。後ろ髪を惹かれる思いで熊本に戻った広瀬さんは、熊本赤十字病院に就職されます。
熊本赤十字病院といえば県内でも屈指の病院ですが、当時でも県内では先端の病院であったはずです。しかしながら、広瀬さんが東京で勤めていたのは日本で最先端の病院でした。この二つの病院の医療体制の大きな隔たりを前に広瀬さんは愕然とします。東京では看護に専念できた日々でしたが、熊本では休みを取ることもままならい忙しさに加え、看護以外の事務作業が追い討ちをかけました。(あくまで当時の話です)広瀬さんの中で、カルチャーショックと看護師が医療チームとして認めらないことへのストレス、そして体力的な消耗が、看護師としての希望を次第に失わせていきました。
「自分にとって看護師という職業は一生続けていける仕事なのだろうかという疑問がわいたんですね」。この間、広瀬さんの中で、お父様が40歳で起業されていたこともあって、組織の中で仕事をするよりも、自分で起業したいという思いが芽生えだしました。「漠然とでしたが、私も40までに起業をしたいなと思うようになったんです」と。
そんな鬱屈とした日々の中で、意中の彼が熊本の銀行に就職を果し、戻って来ました。長かった遠距離恋愛が一気に燃え上がり、平成2年2月に結婚。広瀬さんは、ご主人の意向もあって結婚退職の道を選ばれます。その後三人の子宝に恵まれ、専業主婦の生活を過ごされますが、三度目の出産後にご自分の今後の人生に目を向けられるようになった広瀬さんは、簿記とコンピュータの勉強を始められます。
結婚から6年後、広瀬さんは、とある小さな株式会社に勤めることになります。そこで、総務・経理・労務を担当する中、社内の若者たちの多重債務状況とそのかかわりを通して、金銭教育の必要性を強く意識されるようになりました。元看護師としての職業的意識が、心の医療ともいうべきカウンセラーへと変質して芽生えたのがこの時期でした。
「『金銭教育』をするためにお金のプロになりたいと思ったときに知ったのがファイナンシャル・プランナーだったんです」。この資格を取るための勉強の時間を作るために仕事もパートに切り換え、車を使う営業の仕事をするようになられます。「遠距離を走る仕事でしたが、私にとっては車の中でテープを聴きながら勉強できたいい時間でした」と楽しい思い出を話すように語られましたが、夜は子育てが終わって11時頃まで、朝は4時起きという五ヶ月間に及ぶ勉強を続けておられました。
「夜11時頃に寝ることが質の良い睡眠になるというので、それなら4時起きでもいけるかなって思ってやってました」。この成果あって、念願のファイナンシャル・プランナーの資格を取得。次に、自分が伝えたいことをきちんと相手に伝える技術の必要性を感じた広瀬さんは、「NPO法人金融知力普及協会認定インストラクター」養成講座も受講をしました。「自らの活動の中で、セミナーを開催するときに必要となる、効果的に話す方法や、アイコンタクトのとりかた、質問の投げかけ方やシナリオの組み立て方などを学ぶことができました」。目標に向かって一気に邁進する広瀬さんの行動力に脱帽です。
しかし取得直後の活動は思うようには進みませんでした。「金銭教育の活動をしたくても無名だったため、活動の場がありませんでした」。そんな中、初めは、自分がやりたいと思っている方向性と同じ内容について開催しているセミナーやワークショップに手伝いとして参加したり、チラシ配布やDM発送などきっかけを掴むための地道な努力が続きます。
そんな中、九州の金銭教育では草分け的存在の方のセミナーに参加したことがきっかけでその方のサポートをするようになられます。その後、講師を任されるようになり一人で鹿児島や沖縄に飛び回る日々を過ごされます。そして、資格取得から1年半ほど過ぎたころ、初めて訪れたチャンスが、お子さんが通う学校のPTA主催の「金銭教育」のセミナーでした。
そして、2004年12月、念願の自主開催でのワークショップを企画・開催。以降ワークショップを続け、その都度プレスリリース(ニュースリリース)をいろいろなメディアに送ったところ、後にメディアからの取材につながり、新聞に取り上げてもらうなど、広瀬さんの名前と活動が少しずつ認知されるようになりました。9月に投げ込んだDMが半年後のレスポンスに繋がりました。
この雌伏の日々の活動が、厳しい寒さに耐えた桜の蕾が時期を得て力強い花を咲かせるように、広瀬さんのもとへ様々なオファーを舞い込ませました。「市の登録講師となり、県の金融広報委員会からの依頼で金融広報アドバイザーになり、市の総合女性センター、公民館などで講師をさせていただくなど、活動の場が拡がりました」と。

広瀬さんの活動実績を見ると、学校関係のセミナーでの講演が実に多いのですが、ここでの話は次ぎの信念に根ざした内容になっています。
「子供たちが手にするお小遣いはどこから来るのか?それはもちろん、ご両親の収入からです。言いかえればご両親の『稼ぎ』の中からです。この『稼ぐ』ことの意味を問いかけなければいけないと思っているんです。つまり、金銭教育とキャリア教育は車の両輪なんですね」。
現在、広瀬さんの視線は学生から社会人へと広がっています。「より良く働く人のための支援は、結果的に企業収益の向上につながるんです。ストレスを抱えて保健室で過ごしてきた子供たちが、将来社会人になったときにストレスを発散する場がない。そんな場を提供していきたいんですね。企業へのカウンセリングと人材教育のアウトソーシングを目指しています」。
広瀬さんから「EAP」という言葉を聞きました。「Employee Assistance Program」の略で、「従業員のメンタルヘルス対策支援。社員が抱える職場や家族、健康に関する悩みへの相談を受け付ける体制作りのこと。生産性の向上や優秀な人材の離職防止といった効果がある」手法です。
EAPの具体的な活動内容には、(1)社員の啓もう、(2)電話や電子メール、対面によるカウンセリング、(3)部下との接し方やストレス除去法の教育研修、(4)専門医への紹介などがあります。上司が問題意識のない社員を相談に行くように促したり、気軽に社員が相談できる体制作りまで実施する点が特徴。EAPを導入すれば、社員の欠勤や医療費の削減につながります。さらに、社員の悩みを無くし快適に働ける職場作りをすることで、生産性を向上したり、優秀な人材の流出を阻止するといった効果も期待できます。(日経情報ストラテジー2002/10/29)
実際、カウンセリングの資格を持ちながら、この資格を活かせない方々が少なくないといいます。広瀬さんの目標は、県内の企業経営者に、従業員の方々のストレスを解消することで結果的に収益につながるということを理解してもらい、こういったソフトへの投資を活発化させること。そうすることで潜在カウンセラーたちの活躍の場を提供することにもつながるという狙いです。
さらに、広瀬さんの視線には企業の資金調達の支援活動も入っています。「現在、公的機関による助成金をはじめ、経済産業省や中小企業基盤機構などの様々な機関、財団等から出されているもので、実は3,000種類位あるんですね。ただこうした制度について余りにも情報不足です。特に中小企業にとっては返さなくても良い資金である助成金の存在は貴重な財源です。もちろん所定の審査はありますが、内容によっては数千万~億単位の助成金を受けることも可能なんです。私たちはこの助成金獲得への書類作成などのサポートができます」。
三年後の広瀬さんはどうなっているのかをご本人に尋ねてみました。「仕事をとってくるのが経営者の本質だとしたら、私はそうした経営者にはなれないと思います。自分の手や言葉で直接関わって行きたいんです。そういった意味では、三年後も今と同じ。それに加えてコーディネーターをやっているかもしれません。カウンセリングのアウトソーシングを実現したいんです」。
私が広瀬さんを知ったFMKの番組で司会者が広瀬さんに「社会の看護師みたいですね」と言ったことが、「ちょっぴり嬉しかったですね」と話す広瀬さん。冒頭で私は、「看護師であった広瀬さんがファイナンシャル・プランナーに転進するまでの経緯」と書きましたが、広瀬さんにとってそれは「転進」ではなく、「階段を上る」ことだったんだなと思うようになりました。それは、「からだの健康」から「こころの健康」の看護への夢の途中なのだと思うようになりました。
最後に「県知事になれと言われたら何から手をつけたいですか?」と唐突な質問を投げかけてみました。「んー、やりたいことはたくさんありますが・・・。まずは、中学校教育の現場改革ですね。社会につながった教育改革。キャリア教育のできる先生を増やしたいですね。金銭教育、キャリア教育、法教育、食教育、環境教育などは産業界や法曹界、専門家などとの交流が大切です。これまでの教育界の垣根を取っ払って、社会に繋がった教育を実現したいです」と、そのお応えには全く迷いがありませんでした。

週末は阿久根、都城への講演活動に向かうという広瀬さん。今後の更なるご活躍に期待します。そして、蒲島新知事に、広瀬美貴子さんを政策ブレーンとして採用されることをお奨めして、終わります。
<株式会社Fineプロデュースの理念>
Fineな人生 働く人々に、イキイキとした自分らしい仕事人生をプロデュース
Fineな企業 がんばる企業に、人的資源・資金・信用力アップをプロデュース
Fineな社会 働く人と企業のFineで、より良い社会の実現を目指す!
株式会社Fineプロデュース 広瀬 美貴子
〒860-0085 熊本市高平2-25-45日進ビル302号
Tel 096-346-0611 Fax 096-346-0610
E-mail info@fine-produce.co.jp
All Aboutメールマガジン「フォーエル」連載記事「話題のおシゴトに就きたい」
http://forl.allabout.co.jp/L/popularjob/060503/lr04305/
2008年04月08日
天草に雇用創出を!FP・江浦誠(19)の挑戦
先日、第17回のゲストにお迎えした西田ミワさんからいただいた「夢を形に・起業家たちの人間力」という本を読んでいたら、この本の執筆者のお一人の文章に、「生まれ育ったふるさと天草に雇用創出をする!」という力強いタイトルを見つけました。その文章を読んでみると、サラリーマン時代から独立を夢見ながらも、起業するまでの悶々とした思いとその葛藤を淡々と綴りつつ、故郷・天草に対する思いが溢れていました。

これはもっと話を聞かずにはいられないと、自称「夢追いインタヴュワー」の私はさっそく江浦さんにコンタクトを取って、ご多忙中をぬって時間を割いていただきました。そんな訳で、第19回のゲストはFP江浦事務所のファイナンシャルプランナー・江浦誠さん(47)です。辛島町にあるオフィスでお話を伺いました。外は雨模様でしたが、爽やかに応対していただきました。

江浦さんは、天草町高浜の生まれ。天草西高卒業後、現・学園大に入学されます。学生時代にアルバイトをしていた求人誌発行会社にそのまま就職された後、広告代理店、不動産会社を経て、平成8年に友人が立ち上げた生保代理店に参画されました。この代理店は、保険業法改正を見据えて立ち上げた、全国でも画期的な、30数社取扱の乗合代理店だったそうです。創業から丸3年間、最後の一年は熊本の責任者として勤務された後、別法人で組織された代理店に勤められ、生保代理店業10年を迎えた平成18年7月21日に満を持して独立されました。
江浦さんには学生時代から抱いていた二つの思いがありました。「求人誌の営業ではお客様の経営者と商談することが多いのですが、情熱あるお話しを聞いているうちに自分も経営者になりたいと思ったんです」というおぼろ気ながらの「思い」。そして、「学生時代に帰省したとく、高校時代の後輩がとあるきっかけで縫製会社を起こして立派に地元で雇用貢献をしていたことを知ったんですね。自分もいずれは天草の雇用創出に何らかの貢献をしたいと思っていましたが、彼は既に地に足がついた形で実現していて、これも立派な貢献なんだなと気づいたんです」というなんらかの形での貢献をという「思い」。
とは言え、「いつかは起業したい」、そして、「いつかは天草への雇用創出に貢献したい」という漠然とした思いは、なかなか具体的な活動には至らなかった江浦さんでした。しかし、目の前の仕事をこなしながらもこの間に、テープが伸びるほど聞きまくったという自己啓発テープの一つがありました。それは、竹内日祥という住職の「社長・経営幹部のための特別講話乱世を生き抜くリーダーの条件」。
この収録時間、二時間というテープの中の一節が江浦さんの潜在意識に入り込んでいたのでした。その一節は、「まず、旗を揚げること。旗を揚げることによって、周りに知らしめることが肝要だ」という内容だったそうです。私は不勉強で、この竹内日祥上人なる方を存じ上げませんでしたので、ちっと調べてみました。
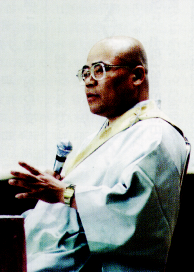
竹内日祥上人;1947年、神戸市に生まれる、立正大学仏教学部卒業後、日蓮宗妙見閣寺住職となる。上人の講演は、仏教思想を 現代に即応した表現で、独特な弁舌と明解な切れ味の良い論理に乗せて、さわやかな中にちょっぴり深刻な上人の生きざまをのぞかせて、感動を与えると定評があります。特に上人は経営トップの指導と企業幹部の人材育成に強烈な影響を与え、大変革時代の方向と、戦略の原点を的確に示し、混迷の乱世を勝ち抜く価値観の集団的転換(パラダイム・シフト)を徹底的に解明。年間講演回数は、200回に及び、すべての収益は国際永久平和祈念祭典の資金の一部に充てられています。
その後、生保代理店としての仕事は決して順調とは言えず、江浦さんの起業への思いはその一歩を踏み出すことを躊躇させていました。そんな折、ある先輩からの質問が江浦さんの悶々とする思いに火をつけました。それは、これからの人生においての「60歳からの引き算」です。江浦さんの中で15年もあると思っていたその「時間」は、実質的な稼働時間で言えば、その1/3しかなかったことに気づいたのです。「好きな時に好きなことを好きなだけやる」には今しかないと、このとき江浦さんの起業家としてのエンジンは回転し始めました。
そして運命が動き出しました。先述の「夢を形に・起業家たちの人間力」への執筆依頼の話が本書の編著者である中尾吉宏さんから舞い込んだのです。起業して、ある意味さっぱりした気持ちになっていた江浦さんは、この話を受けてから原稿を苦もなく書き始め、締め切りのかなり前に原稿を仕上げたそうです。一方、他の執筆者の方々が締め切りを過ぎてもなかなか仕上がらない中、中尾さんが来熊されるという機会がありました。そこで江浦さんは原稿では触れなかった天草への思いを語ったそうです。すると中尾さんは、「この前の原稿、没にします」と一言。江浦さんは焦りました。その後、中尾さんから継いで出た言葉は「その話を書きましょうよ」と。
書き直した原稿には「天草で仕事をしよう、天草に雇用を創出しよう、天草を盛り上げよう」という思いが綴られることになりました。そして、そこでこの思いを形にして公然とその旗を揚げることにしました。それが、「天草倶楽部」の設立になりました。記念すべき第一回は今年1月24日に行われました。この第一回には前述の西田ミワさんも途中から出席されていて、そのときの模様を次のように書いておられます。

講師の方も含め、8名でスタートした茶話会では天草の現状…雇用、過疎化、小児科・産婦人科の圧倒的不足高齢化(若者の流出)、シャッター街などの現状報告がありこれらをどう食い止めたらいいのか地域資源は何かなどが話題の中心になりました。(じかに聞くとニュースでは得られない切実さが伝わってきます)
ある参加者は、ママさんのネットワークを強化したとえば、病院・子育て情報をITを活用し共有する活動をすでにはじめておられ、ある参加者は、他の地域での成功事例を紹介され、ある参加者は、「とにかく、なにをどうお手伝いできるかわからないけど、天草の魅力を発信していきたい。」と熱く語っておられました。
西田からは、世の中の傾向や興味深い慣例など事例を紹介。参加者の中には、ユニークなキャラと活動に注目があつまり質問攻めになる一幕もあり、会場は大盛り上がり(笑)厳しい現状のなかでも、良い風が吹きそうな予感がします。これから3ヶ月に1回ほどのスパンで天草倶楽部交流会は実施されるそう。私は熊本市内在住ではありますが、同じ熊本県民ですし、彼等の活動のお手伝いしていきたいと思ってます。(http://tabineko.otemo-yan.net/e65557.html)
江浦さんは、この「天草倶楽部」を立ち上げてみて、わかったことがあるといいます。それは、天草を再生させたいと活動されている方々はたくさんいて、組織されたグループ、コミュニティも決して少なくないということでした。「私は、この倶楽部が先頭に立ってこれらの方々を引っ張りたいという気持ちはさらさらありません。この倶楽部がそれぞれの活動にどう繋がっていけるのか、これからそれを模索していきたいと思っています」と、謙虚に語られました。
また、「この倶楽部を立ち上げて、いろんなところで天草に対する思いを語っていくうちに、聞いて頂く方々の食指に触れるのでしょうか、相手の方も熱く語ってくださる方が多いんですね。先日もお客様との商談の後この話になって、お客様は地元への思いを二時間も語られました。お客様は天草の方ではありませんでしたが、今後もこの倶楽部を応援していただけるということでした」。
江浦さんの当面の雇用創出への活動は、自らが地元の企業を創出するということではなく、まず、この「天草倶楽部」を通じて参加者への知的啓発とビジネス・マッチングの模索にあります。「目下、手弁当での開催だけに、講師陣の方々にはボランティアでお願いせざるを得ません」とのこと。
天草へ熱い思いをお持ちのコンサルタントやご専門の方、あるいは、そんな方をご存知の方は江浦さんへのご紹介をお願いします。第二回目の「天草倶楽部」は今月17日(木)に開催されます。天草にお住まいの方、天草ご出身の方、あるいは天草の発展に力を貸したいという方は、ふるってご参加ください。
<第二回 天草倶楽部」>
場所;天草宝島国際交流会館ポルト
住所;天草市中央新町15-7 旧ニチイ跡
時間;受付開始/13:15、開会/13:30
勉強会/13:35~14:35、交流会/14:40~15:40
会費;ワンコイン500円(飲み物込み)

勉強会講師:田中美智子さん(久留米でご活躍の「営業プロデューサー」)
HP:http://of-tanaka.com/
ファーマーズスタジオ;http://far-s.com/
主催/天草倶楽部
連絡先/096-367-9276
090-4343-7707(江浦誠)
「天草倶楽部コミュ」
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2887514
上記の他の江浦さんへのアクセスは下記です。
E-mail;meuraster@gmail.com
URL;http://blog.goo.ne.jp/9sugo/、http://sugo.otemo-yan.net/

これはもっと話を聞かずにはいられないと、自称「夢追いインタヴュワー」の私はさっそく江浦さんにコンタクトを取って、ご多忙中をぬって時間を割いていただきました。そんな訳で、第19回のゲストはFP江浦事務所のファイナンシャルプランナー・江浦誠さん(47)です。辛島町にあるオフィスでお話を伺いました。外は雨模様でしたが、爽やかに応対していただきました。

江浦さんは、天草町高浜の生まれ。天草西高卒業後、現・学園大に入学されます。学生時代にアルバイトをしていた求人誌発行会社にそのまま就職された後、広告代理店、不動産会社を経て、平成8年に友人が立ち上げた生保代理店に参画されました。この代理店は、保険業法改正を見据えて立ち上げた、全国でも画期的な、30数社取扱の乗合代理店だったそうです。創業から丸3年間、最後の一年は熊本の責任者として勤務された後、別法人で組織された代理店に勤められ、生保代理店業10年を迎えた平成18年7月21日に満を持して独立されました。
江浦さんには学生時代から抱いていた二つの思いがありました。「求人誌の営業ではお客様の経営者と商談することが多いのですが、情熱あるお話しを聞いているうちに自分も経営者になりたいと思ったんです」というおぼろ気ながらの「思い」。そして、「学生時代に帰省したとく、高校時代の後輩がとあるきっかけで縫製会社を起こして立派に地元で雇用貢献をしていたことを知ったんですね。自分もいずれは天草の雇用創出に何らかの貢献をしたいと思っていましたが、彼は既に地に足がついた形で実現していて、これも立派な貢献なんだなと気づいたんです」というなんらかの形での貢献をという「思い」。
とは言え、「いつかは起業したい」、そして、「いつかは天草への雇用創出に貢献したい」という漠然とした思いは、なかなか具体的な活動には至らなかった江浦さんでした。しかし、目の前の仕事をこなしながらもこの間に、テープが伸びるほど聞きまくったという自己啓発テープの一つがありました。それは、竹内日祥という住職の「社長・経営幹部のための特別講話乱世を生き抜くリーダーの条件」。
この収録時間、二時間というテープの中の一節が江浦さんの潜在意識に入り込んでいたのでした。その一節は、「まず、旗を揚げること。旗を揚げることによって、周りに知らしめることが肝要だ」という内容だったそうです。私は不勉強で、この竹内日祥上人なる方を存じ上げませんでしたので、ちっと調べてみました。
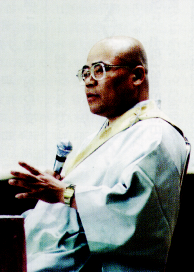
竹内日祥上人;1947年、神戸市に生まれる、立正大学仏教学部卒業後、日蓮宗妙見閣寺住職となる。上人の講演は、仏教思想を 現代に即応した表現で、独特な弁舌と明解な切れ味の良い論理に乗せて、さわやかな中にちょっぴり深刻な上人の生きざまをのぞかせて、感動を与えると定評があります。特に上人は経営トップの指導と企業幹部の人材育成に強烈な影響を与え、大変革時代の方向と、戦略の原点を的確に示し、混迷の乱世を勝ち抜く価値観の集団的転換(パラダイム・シフト)を徹底的に解明。年間講演回数は、200回に及び、すべての収益は国際永久平和祈念祭典の資金の一部に充てられています。
その後、生保代理店としての仕事は決して順調とは言えず、江浦さんの起業への思いはその一歩を踏み出すことを躊躇させていました。そんな折、ある先輩からの質問が江浦さんの悶々とする思いに火をつけました。それは、これからの人生においての「60歳からの引き算」です。江浦さんの中で15年もあると思っていたその「時間」は、実質的な稼働時間で言えば、その1/3しかなかったことに気づいたのです。「好きな時に好きなことを好きなだけやる」には今しかないと、このとき江浦さんの起業家としてのエンジンは回転し始めました。
そして運命が動き出しました。先述の「夢を形に・起業家たちの人間力」への執筆依頼の話が本書の編著者である中尾吉宏さんから舞い込んだのです。起業して、ある意味さっぱりした気持ちになっていた江浦さんは、この話を受けてから原稿を苦もなく書き始め、締め切りのかなり前に原稿を仕上げたそうです。一方、他の執筆者の方々が締め切りを過ぎてもなかなか仕上がらない中、中尾さんが来熊されるという機会がありました。そこで江浦さんは原稿では触れなかった天草への思いを語ったそうです。すると中尾さんは、「この前の原稿、没にします」と一言。江浦さんは焦りました。その後、中尾さんから継いで出た言葉は「その話を書きましょうよ」と。
書き直した原稿には「天草で仕事をしよう、天草に雇用を創出しよう、天草を盛り上げよう」という思いが綴られることになりました。そして、そこでこの思いを形にして公然とその旗を揚げることにしました。それが、「天草倶楽部」の設立になりました。記念すべき第一回は今年1月24日に行われました。この第一回には前述の西田ミワさんも途中から出席されていて、そのときの模様を次のように書いておられます。

講師の方も含め、8名でスタートした茶話会では天草の現状…雇用、過疎化、小児科・産婦人科の圧倒的不足高齢化(若者の流出)、シャッター街などの現状報告がありこれらをどう食い止めたらいいのか地域資源は何かなどが話題の中心になりました。(じかに聞くとニュースでは得られない切実さが伝わってきます)
ある参加者は、ママさんのネットワークを強化したとえば、病院・子育て情報をITを活用し共有する活動をすでにはじめておられ、ある参加者は、他の地域での成功事例を紹介され、ある参加者は、「とにかく、なにをどうお手伝いできるかわからないけど、天草の魅力を発信していきたい。」と熱く語っておられました。
西田からは、世の中の傾向や興味深い慣例など事例を紹介。参加者の中には、ユニークなキャラと活動に注目があつまり質問攻めになる一幕もあり、会場は大盛り上がり(笑)厳しい現状のなかでも、良い風が吹きそうな予感がします。これから3ヶ月に1回ほどのスパンで天草倶楽部交流会は実施されるそう。私は熊本市内在住ではありますが、同じ熊本県民ですし、彼等の活動のお手伝いしていきたいと思ってます。(http://tabineko.otemo-yan.net/e65557.html)
江浦さんは、この「天草倶楽部」を立ち上げてみて、わかったことがあるといいます。それは、天草を再生させたいと活動されている方々はたくさんいて、組織されたグループ、コミュニティも決して少なくないということでした。「私は、この倶楽部が先頭に立ってこれらの方々を引っ張りたいという気持ちはさらさらありません。この倶楽部がそれぞれの活動にどう繋がっていけるのか、これからそれを模索していきたいと思っています」と、謙虚に語られました。
また、「この倶楽部を立ち上げて、いろんなところで天草に対する思いを語っていくうちに、聞いて頂く方々の食指に触れるのでしょうか、相手の方も熱く語ってくださる方が多いんですね。先日もお客様との商談の後この話になって、お客様は地元への思いを二時間も語られました。お客様は天草の方ではありませんでしたが、今後もこの倶楽部を応援していただけるということでした」。
江浦さんの当面の雇用創出への活動は、自らが地元の企業を創出するということではなく、まず、この「天草倶楽部」を通じて参加者への知的啓発とビジネス・マッチングの模索にあります。「目下、手弁当での開催だけに、講師陣の方々にはボランティアでお願いせざるを得ません」とのこと。
天草へ熱い思いをお持ちのコンサルタントやご専門の方、あるいは、そんな方をご存知の方は江浦さんへのご紹介をお願いします。第二回目の「天草倶楽部」は今月17日(木)に開催されます。天草にお住まいの方、天草ご出身の方、あるいは天草の発展に力を貸したいという方は、ふるってご参加ください。
<第二回 天草倶楽部」>
場所;天草宝島国際交流会館ポルト
住所;天草市中央新町15-7 旧ニチイ跡
時間;受付開始/13:15、開会/13:30
勉強会/13:35~14:35、交流会/14:40~15:40
会費;ワンコイン500円(飲み物込み)

勉強会講師:田中美智子さん(久留米でご活躍の「営業プロデューサー」)
HP:http://of-tanaka.com/
ファーマーズスタジオ;http://far-s.com/
主催/天草倶楽部
連絡先/096-367-9276
090-4343-7707(江浦誠)
「天草倶楽部コミュ」
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2887514
上記の他の江浦さんへのアクセスは下記です。
E-mail;meuraster@gmail.com
URL;http://blog.goo.ne.jp/9sugo/、http://sugo.otemo-yan.net/
2008年04月05日
イタリアで認められた、皿に絵を描く料理人・古畑圭一朗
今回は、番外編をお送りします。先日、深夜にふと見たテレビ。鹿児島は大口市出身の古畑圭一朗さんという、イタリアで3年連続でミシュランから星を獲得するシェフのルポでした。その感想を別のブログで書いたところ、今朝、ご本人から次のようなコメントが帰ってきました。
■本人です(笑)
はじめまして、偶然ネットサーフィン中に発見してしまいました古畑です。びっくりしました(笑)ブログに取り上げていただいていて。沢山の方から反響がありましてうれしい限りです。鹿児島では再放送も決定いたしました。4月18日(金)25:05~26:05 KTS 鹿児島テレビです。これからもどうぞよろしく。CIAO!!

古畑さんのこうした気配りが彼の人間性を表していますね。この番組、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、見ていないという方に、そのときのブログの記事を転載します。ちなみに、トスカーナは、「イタリア半島の北部に位置し、シエナ、ピサ、フィレンツェなど魅力的な古都が数多く存在する。ユネスコ世界遺産の数も多い。農業が大変に盛んで、ワイン、オリーブ、小麦などを生産している。特にワインはキャンティやスーペル・トスカーナといった名品を生産する、世界屈指の名醸地」だそうです。

昨日(3/30)、九州ドキュメンタリーとして放映されている番組で昨年12月2日に放映された、KTS制作の「Buon Buon Buon」~皿に絵を描く料理人・古畑(こばた)圭一朗~の再放送を見ました。古畑任三郎ではありませんよ。イタリア・トスカーナにある「IL PATRIARCA」でシェフをまかされて、3年連続店の星を維持し続けている鹿児島出身の古畑圭一朗さんです。番組HPでは次のように紹介されています。

日本人の食生活にすっかり定着したイタリア料理。そのイタリア料理を学ぼうと、日本から毎年2000人以上の見習いコックがイタリアを訪れるという。しかし、そのほとんどは半年から2年ほどの短期で日本に帰ってしまう。「イタリアで修行」、その経歴は日本では大きな武器になるからだ。そんな中、あえてイタリアに残り勝負を挑み続ける日本人シェフがいる。その男の名は、古畑圭一朗(35)。鹿児島県大口市の出身。もともとはコンピューター業界のシステムエンジニア。ふとしたことがきっかけで料理の世界に飛び込んだユニークな経歴の持ち主だ。

古畑がつくる料理は、まさに芸術品。それが高く評価され、3年連続でミシュランから星を獲得。古畑がシェフをつとめるレストランは、イタリア・トスカーナ地方のとある田舎町にある。その地位は古畑が「技術・知識・人間性」すべてにおいてパーフェクトだと語るイタリア人シェフ、サルバトーレ氏から認められ、譲り受けたものだ。その時にサルバトーレ氏が残してくれた言葉が「皿に絵を描け」。そして、古畑の夢は、いつの日か恩師サルバトーレ氏を越えること…。
大口市といえば鹿児島でも熊本県人吉市などや宮崎県えびの市との県境で、鹿児島市内から車で2時間ほどの位置にあります。私は前職時代、多いときには月に一度は行っていたところですが、仕事で自治体に行く程度ですから観光はしたことがありません。そう言えば吉田拓郎さんはここで生まれたのではなかったでしょうか?
古畑さんの凄いところは、後述のプロフィールにあるように、料理の世界に入ったのが22才からで、渡伊後5年で一流シェフになったことでしょう。料理の世界、特に日本では一流と呼ばれるまでには数十年かかるものと思っていたので、このキャリアには驚きです。ちなみにこの写真は、「アンコウとファアグラの詰め物、サフランソース。アンコウを一晩マリネして臭みを抜き、鴨のフォアグラをスティック状に刺し、豚の網油で巻き焼き・蒸し揚げる。サフランソースと茹でた野菜を共に」(古畑さんHP)ですが、番組でも紹介されていました。

さらに、この一枚はスイカの彫刻。見事です。古畑さんは、イタリアでミケランジェロなどの彫刻に魅せられたといいます。料理は味に加え、目、香り、食感で楽しませる総合芸術と言ってもいいわけですから、師匠の「皿に絵を描け」という言葉をしっかり受け継いで、自分の表現手段としての料理に結実させているのですね。番組では大口市に帰省した古畑さんがイベントで氷の彫刻を彫っていたところも紹介されていました。

KEIICHIRO (プロフィール);1973年 鹿児島生まれ。鹿児島某専門学校卒業後、SEとして上京するが、ふとしたきっかけから大手町のイタリアレストランへ入店。3年後、渡伊。98年秋より、ローマのレストランで修行を始める。半年後トスカーナ州のレストランへ。のち、モリーゼ州、ウンブリア州などのレストランで働き、99年秋、現在の「IL PATRIARCA」へ入店。各担当をうけもち02年にセコンドシェフへ昇格。03年、「IL PATRIARCA」はミシェランから星を獲得。05年よりシェフを任されている。

http://happytown.orahoo.com/sasuraichef/
■本人です(笑)
はじめまして、偶然ネットサーフィン中に発見してしまいました古畑です。びっくりしました(笑)ブログに取り上げていただいていて。沢山の方から反響がありましてうれしい限りです。鹿児島では再放送も決定いたしました。4月18日(金)25:05~26:05 KTS 鹿児島テレビです。これからもどうぞよろしく。CIAO!!

古畑さんのこうした気配りが彼の人間性を表していますね。この番組、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、見ていないという方に、そのときのブログの記事を転載します。ちなみに、トスカーナは、「イタリア半島の北部に位置し、シエナ、ピサ、フィレンツェなど魅力的な古都が数多く存在する。ユネスコ世界遺産の数も多い。農業が大変に盛んで、ワイン、オリーブ、小麦などを生産している。特にワインはキャンティやスーペル・トスカーナといった名品を生産する、世界屈指の名醸地」だそうです。

昨日(3/30)、九州ドキュメンタリーとして放映されている番組で昨年12月2日に放映された、KTS制作の「Buon Buon Buon」~皿に絵を描く料理人・古畑(こばた)圭一朗~の再放送を見ました。古畑任三郎ではありませんよ。イタリア・トスカーナにある「IL PATRIARCA」でシェフをまかされて、3年連続店の星を維持し続けている鹿児島出身の古畑圭一朗さんです。番組HPでは次のように紹介されています。

日本人の食生活にすっかり定着したイタリア料理。そのイタリア料理を学ぼうと、日本から毎年2000人以上の見習いコックがイタリアを訪れるという。しかし、そのほとんどは半年から2年ほどの短期で日本に帰ってしまう。「イタリアで修行」、その経歴は日本では大きな武器になるからだ。そんな中、あえてイタリアに残り勝負を挑み続ける日本人シェフがいる。その男の名は、古畑圭一朗(35)。鹿児島県大口市の出身。もともとはコンピューター業界のシステムエンジニア。ふとしたことがきっかけで料理の世界に飛び込んだユニークな経歴の持ち主だ。

古畑がつくる料理は、まさに芸術品。それが高く評価され、3年連続でミシュランから星を獲得。古畑がシェフをつとめるレストランは、イタリア・トスカーナ地方のとある田舎町にある。その地位は古畑が「技術・知識・人間性」すべてにおいてパーフェクトだと語るイタリア人シェフ、サルバトーレ氏から認められ、譲り受けたものだ。その時にサルバトーレ氏が残してくれた言葉が「皿に絵を描け」。そして、古畑の夢は、いつの日か恩師サルバトーレ氏を越えること…。
大口市といえば鹿児島でも熊本県人吉市などや宮崎県えびの市との県境で、鹿児島市内から車で2時間ほどの位置にあります。私は前職時代、多いときには月に一度は行っていたところですが、仕事で自治体に行く程度ですから観光はしたことがありません。そう言えば吉田拓郎さんはここで生まれたのではなかったでしょうか?
古畑さんの凄いところは、後述のプロフィールにあるように、料理の世界に入ったのが22才からで、渡伊後5年で一流シェフになったことでしょう。料理の世界、特に日本では一流と呼ばれるまでには数十年かかるものと思っていたので、このキャリアには驚きです。ちなみにこの写真は、「アンコウとファアグラの詰め物、サフランソース。アンコウを一晩マリネして臭みを抜き、鴨のフォアグラをスティック状に刺し、豚の網油で巻き焼き・蒸し揚げる。サフランソースと茹でた野菜を共に」(古畑さんHP)ですが、番組でも紹介されていました。

さらに、この一枚はスイカの彫刻。見事です。古畑さんは、イタリアでミケランジェロなどの彫刻に魅せられたといいます。料理は味に加え、目、香り、食感で楽しませる総合芸術と言ってもいいわけですから、師匠の「皿に絵を描け」という言葉をしっかり受け継いで、自分の表現手段としての料理に結実させているのですね。番組では大口市に帰省した古畑さんがイベントで氷の彫刻を彫っていたところも紹介されていました。

KEIICHIRO (プロフィール);1973年 鹿児島生まれ。鹿児島某専門学校卒業後、SEとして上京するが、ふとしたきっかけから大手町のイタリアレストランへ入店。3年後、渡伊。98年秋より、ローマのレストランで修行を始める。半年後トスカーナ州のレストランへ。のち、モリーゼ州、ウンブリア州などのレストランで働き、99年秋、現在の「IL PATRIARCA」へ入店。各担当をうけもち02年にセコンドシェフへ昇格。03年、「IL PATRIARCA」はミシェランから星を獲得。05年よりシェフを任されている。

http://happytown.orahoo.com/sasuraichef/
2008年03月31日
世界を目指す熊本在住の若き画家・遠藤徳人(18)
第18回目のゲストにお迎えしたのは、第四回目のゲスト・黒田恵子さんがご自分のギャラリー「ADO」での個展開催などで支援する画家・遠藤徳人(とくひと)さん(24)です。遠藤さんと最初にお会いしたのは2月1日、黒田さんのギャラリーでした。1月22日に最初に「ADO」にお邪魔した際、二階にあるギャラリーで遠藤さんの絵をはじめて見ました。そこに飾られた墨絵調の昇り龍、原色をふんだんに使った龍、抽象的なPOPアートなどなど様々なタッチが印象的でした。
遠藤さんはこの3月、黒田さんのご紹介で取材させていただいた第七回目の渡辺真希子さん、第八回目に登場いただいた「人間建築探検處」の代表であり、建築家の長野聖二さんが代表を務められる「河原町文化開発研究所」のある河原町商店街の住人となりました。今回は、このブログとのカテゴリーとはちっとはずれますが、そんな訳で黒田さんのギャラリーでのインタヴューをお送りします。

遠藤さんに初めてお会いしたとき、彼の分厚いポートフォリオ(作品集)を見せてもらいました。そこにも実に多彩なタッチの絵が並んでいて、その一連の絵に興味を持ちつつ、そんな絵を描く彼自身についても興味がわいたのでした。その中で一際印象的だったのが「ミスターCLOUD」というキャラクターでした。
絵を描き始めた当初、彼の頭の中にこのキャラが突然現われたそうで、何枚もの絵が描かれていました。今回は残念ながらこの「ミスターCLOUD」を紹介できませんが、遠藤さんによると「このキャラは絵に対するモヤモヤした気持ちの表れだったような気がするんです。ですから最近はほとんどこのキャラ自体を描くことはありません」ということでした。しかし、最近は別の角度で自分を見つめ直すことが多いと語る遠藤さん。絵に集中し、自分の世界を描き出す「自分」と社会人としての「自分」の存在。その自分の中のバランスをどう取っていくか?それが今の彼の課題だと。

絵画という方法で自分を表現しようとするアーティストにあれこれ言葉で語ってもらうということに果たしてどれだけ意味があるのか?今回はここに自分なりに疑問を持ちながらインタヴューに臨みました。そんな思いでいた私は、黒田さんにまず、これから遠藤さんに何を望みますかと尋ねてみました。「絵で人の心を動かせないうちは、人として当たり前のコミュニケーションが取れることが大事なことだと思います。遠藤君がそうだということでありませんが、自分の作品を人にきちんと語れる画家になってほしいと思います」と、私の疑問を知ったかのようなコメントをされました。そう言えば岡本太郎さんや日比野克彦さんでさえ実に饒舌に語っているではありませんか。少し気が楽になった私のインタヴューが始まりました。

遠藤さんは開新高校出身。幼い頃から漫画家に憧れて絵を描いてきた彼は、熊本デザイン専門学校に通ううちに画家の道を進むことを選んだといいます。私の年代になると開新高校と言われてもピンときませんが、前身は熊本第一工業高等学校。更に遡ると、熊本鉄道高等学校、明治37年の東亜鉄道学院に行き着くんですね。平成16年に男女共学になっていますから、創立から丸100年間男子校としての歴史を歩んできています。話が逸れました。
絵描きの道を選ぶと言っても、プロとしての画家は当然ながら棘の道。遠藤さんは一時期、就職することも考えたそうですが、就職を決めた途端に大病に遭ったり、再び絵描きを諦めかけたときに知人から個展を開かないかという誘いがあったりと、彼が絵を諦めようとする度に運命が遠藤さんに画業を捨てさせなかった経緯がありました。
絵を描きつつ遠藤さんはずっと「自分らしくある」ことについて思い悩んでいたといいます。人と同じ考え、行動をとることに対する閉塞感がありました。この問題に自分なりの決着をつけられたのが、昨年訪れたアメリカで、そこに暮す人々の日常を知ってからだったそうです。シカゴ、コロンバスを友人とホームステイをしながらの二週間の旅で、現地の人々が自由に自己を主張しながら生きる姿を目の当たりにして「あぁ、こうやって自分らしく生きていいんだ」と自信を持ったそうです。

そんな遠藤さんが絵を描くときに常に考えていることは、ある二つの価値観をどうやったら一つに融合できるかということだそうです。たとえばそれは母親の価値観と父親の価値観。双方共にその価値観を理解できる。そこでこの二つの価値観を掘り下げていく事によってその源泉的な価値観、1+1が別の新たな「1」になるという価値観を導くために思索すること。別の言い方をすれば、卵子と精子が一つになって新しい生命となるというプロセスと結果をどう表現するか。そこに彼のアーティスティックな営みがあります。
遠藤さんは最近この河原町にアトリエを持ちました。「これからは気が狂うほど描きたい」と熱く語ります。このアトリエで6月1日から二週間にわたって開かれるギャラリーADOでの個展に向けて、作品を作り上げていく予定です。魂を込められた作品だけをここで展示したいと語ってくれました。その個展ではライブ・ペイントも披露する予定です。
先日もクラブでライブ・ペイントを行ったそうです。クラブの音楽のテーマが「男が女を口説く」というものだったので、彼の得意とする陰影技法でこのテーマを受けて抽象的な人物を描いたそうですが、「今年一番の自信作っすよ」とご機嫌でした。この絵はまだ会場に残してあって、この日は見ることができませんでしたが、6月の個展には登場するはずです。
遠藤さんに目下のライバルは誰ですか?と尋ねてみました。「art horymen、ado(渡辺真希子)さん、eichiさんには少なくとも負けたくありません。でも、熊本の画家たちの中でも、この河原町に集るアーティストたちのレベルは高いっすよ。マジッ、ヤバイッス」。訳してもらうと、ここに集まるアーティストたちは、趣味や癒しで絵を描いているのではなく、哲学をもって絵を描いている人が多い、ということでした。
最後に黒田さんに遠藤さんの絵について語ってもらいました。「タッチがどうとか、色彩がどうかということではなく、彼の絵に、とにかく『勢い』を感じたんです。彼にはまず絵を通して、たった一人でもいいからその人の心を動かすことができる絵描きになってほしいですね。自分の中で悶々としたものがあれば、その息吹を一枚の絵に入れ込んでほしい。自分のフィルターを通して蒸留水のように浄化した思いを描いてほしいと思っています」と、熱い叱咤激励でした。

遠藤徳人さんへのアクセス;
TEL;080-5214-0740
Emai;art-style.89wrangler@ezweb.ne.jp、cluodtoku@yahoo.co.jp
<遠藤徳人個展>
日時;2008年6月1日~14日
場所;「GALLERY ADO」;熊本市河原町2
TEL;096-352-1930(OPEN;11:00~20:00)
http://www.just.st/303750
遠藤さんはこの3月、黒田さんのご紹介で取材させていただいた第七回目の渡辺真希子さん、第八回目に登場いただいた「人間建築探検處」の代表であり、建築家の長野聖二さんが代表を務められる「河原町文化開発研究所」のある河原町商店街の住人となりました。今回は、このブログとのカテゴリーとはちっとはずれますが、そんな訳で黒田さんのギャラリーでのインタヴューをお送りします。

遠藤さんに初めてお会いしたとき、彼の分厚いポートフォリオ(作品集)を見せてもらいました。そこにも実に多彩なタッチの絵が並んでいて、その一連の絵に興味を持ちつつ、そんな絵を描く彼自身についても興味がわいたのでした。その中で一際印象的だったのが「ミスターCLOUD」というキャラクターでした。
絵を描き始めた当初、彼の頭の中にこのキャラが突然現われたそうで、何枚もの絵が描かれていました。今回は残念ながらこの「ミスターCLOUD」を紹介できませんが、遠藤さんによると「このキャラは絵に対するモヤモヤした気持ちの表れだったような気がするんです。ですから最近はほとんどこのキャラ自体を描くことはありません」ということでした。しかし、最近は別の角度で自分を見つめ直すことが多いと語る遠藤さん。絵に集中し、自分の世界を描き出す「自分」と社会人としての「自分」の存在。その自分の中のバランスをどう取っていくか?それが今の彼の課題だと。

絵画という方法で自分を表現しようとするアーティストにあれこれ言葉で語ってもらうということに果たしてどれだけ意味があるのか?今回はここに自分なりに疑問を持ちながらインタヴューに臨みました。そんな思いでいた私は、黒田さんにまず、これから遠藤さんに何を望みますかと尋ねてみました。「絵で人の心を動かせないうちは、人として当たり前のコミュニケーションが取れることが大事なことだと思います。遠藤君がそうだということでありませんが、自分の作品を人にきちんと語れる画家になってほしいと思います」と、私の疑問を知ったかのようなコメントをされました。そう言えば岡本太郎さんや日比野克彦さんでさえ実に饒舌に語っているではありませんか。少し気が楽になった私のインタヴューが始まりました。

遠藤さんは開新高校出身。幼い頃から漫画家に憧れて絵を描いてきた彼は、熊本デザイン専門学校に通ううちに画家の道を進むことを選んだといいます。私の年代になると開新高校と言われてもピンときませんが、前身は熊本第一工業高等学校。更に遡ると、熊本鉄道高等学校、明治37年の東亜鉄道学院に行き着くんですね。平成16年に男女共学になっていますから、創立から丸100年間男子校としての歴史を歩んできています。話が逸れました。
絵描きの道を選ぶと言っても、プロとしての画家は当然ながら棘の道。遠藤さんは一時期、就職することも考えたそうですが、就職を決めた途端に大病に遭ったり、再び絵描きを諦めかけたときに知人から個展を開かないかという誘いがあったりと、彼が絵を諦めようとする度に運命が遠藤さんに画業を捨てさせなかった経緯がありました。
絵を描きつつ遠藤さんはずっと「自分らしくある」ことについて思い悩んでいたといいます。人と同じ考え、行動をとることに対する閉塞感がありました。この問題に自分なりの決着をつけられたのが、昨年訪れたアメリカで、そこに暮す人々の日常を知ってからだったそうです。シカゴ、コロンバスを友人とホームステイをしながらの二週間の旅で、現地の人々が自由に自己を主張しながら生きる姿を目の当たりにして「あぁ、こうやって自分らしく生きていいんだ」と自信を持ったそうです。

そんな遠藤さんが絵を描くときに常に考えていることは、ある二つの価値観をどうやったら一つに融合できるかということだそうです。たとえばそれは母親の価値観と父親の価値観。双方共にその価値観を理解できる。そこでこの二つの価値観を掘り下げていく事によってその源泉的な価値観、1+1が別の新たな「1」になるという価値観を導くために思索すること。別の言い方をすれば、卵子と精子が一つになって新しい生命となるというプロセスと結果をどう表現するか。そこに彼のアーティスティックな営みがあります。
遠藤さんは最近この河原町にアトリエを持ちました。「これからは気が狂うほど描きたい」と熱く語ります。このアトリエで6月1日から二週間にわたって開かれるギャラリーADOでの個展に向けて、作品を作り上げていく予定です。魂を込められた作品だけをここで展示したいと語ってくれました。その個展ではライブ・ペイントも披露する予定です。
先日もクラブでライブ・ペイントを行ったそうです。クラブの音楽のテーマが「男が女を口説く」というものだったので、彼の得意とする陰影技法でこのテーマを受けて抽象的な人物を描いたそうですが、「今年一番の自信作っすよ」とご機嫌でした。この絵はまだ会場に残してあって、この日は見ることができませんでしたが、6月の個展には登場するはずです。
遠藤さんに目下のライバルは誰ですか?と尋ねてみました。「art horymen、ado(渡辺真希子)さん、eichiさんには少なくとも負けたくありません。でも、熊本の画家たちの中でも、この河原町に集るアーティストたちのレベルは高いっすよ。マジッ、ヤバイッス」。訳してもらうと、ここに集まるアーティストたちは、趣味や癒しで絵を描いているのではなく、哲学をもって絵を描いている人が多い、ということでした。
最後に黒田さんに遠藤さんの絵について語ってもらいました。「タッチがどうとか、色彩がどうかということではなく、彼の絵に、とにかく『勢い』を感じたんです。彼にはまず絵を通して、たった一人でもいいからその人の心を動かすことができる絵描きになってほしいですね。自分の中で悶々としたものがあれば、その息吹を一枚の絵に入れ込んでほしい。自分のフィルターを通して蒸留水のように浄化した思いを描いてほしいと思っています」と、熱い叱咤激励でした。

遠藤徳人さんへのアクセス;
TEL;080-5214-0740
Emai;art-style.89wrangler@ezweb.ne.jp、cluodtoku@yahoo.co.jp
<遠藤徳人個展>
日時;2008年6月1日~14日
場所;「GALLERY ADO」;熊本市河原町2
TEL;096-352-1930(OPEN;11:00~20:00)
http://www.just.st/303750
2008年03月18日
実と虚の空間を回遊するドルフィンワークス・西田ミワ(17)
全国商工会議所女性会連合会が、平成14年に創設した「女性起業家大賞」という顕彰があります。同賞は、「創業・経営革新に果敢に取り組んでいる女性起業家を顕彰し応援することにより、産業界の男女共同参画社会の実現を推進し、わが国経済の発展に資することを目的とするもの」だそうです。この顕彰は、各地の商工会から推薦された応募企業から選出されるようです。この熊本商工会議所女性会が推薦する賞として「輝女(テルージョ)」があります。
昨年、その「輝女(テルージョ)」に輝いたお一人にドルフィンワークス代表の西田ミワさんがいらっしゃいました。他に三人の女性経営者がいらっしゃいますが、事業面から個人的に関心があった西田さんにインタヴュー依頼をさせていただき、今回お話をうかがいました。という訳で第17回目のゲストは、「コンテンツディレクター/プランナー」、「財団法人生涯学習開発財団認定コーチ」として活躍されている西田ミワさんです。

実は今回のインタヴューを終えて、ちょっと困りました。西田さんにはいろんなメディアからの取材が多く、私があえてここで書くことはないんじゃないかと思うほどだったからです。しかも、取材後、この記事を書くにあたって西田さんからいただいた資料を読みながら何気なくHPをチェックするといきなり、「エントワークリンケージ 後藤愼一様よりネット取材いただくことになりました。どんな視点で取り上げてくださるのか楽しみです^^のちほどご報告いたします」と書かれているではありませんか。暗黙のプレッシャーです。
とは言え、お忙しい中でせっかく頂いた時間ですので、西田さんご自身、今後の事業についてうかがったことを私なりの解釈で皆さんにお伝えしたいと思います。第一稿を西田さんにメールで送ったところ、前述の「暗黙のプレッシャー」について、西田さんから「脳化学的に申しますと、この『ピュアプレッシャー』は”さらなる向上と幸福感を誘発するドーパミンを大量放出”するそうで…」という励ましをいただきました。それでは本題に入ります。

2001年7月の創業以来、なぜ西田さんがこれほど注目を浴びておられるのか?私の西田さんに対する興味はこの点にありました。取材を終えてその答えが理解できたように思います。実は、西田さんに数多くのメディアから取材依頼が寄せられるようになったのは、起業から半年間、売上ゼロという苦境に喘いだ西田さんが、そこから脱するために暗中模索の中でたどり着いて実行した「顔を売る」という行動の賜物だったことがわかりました。
「私と同じように起業した人、起業を目指している人、様々な異業種、同業種の交流会に顔を出し、団体のリーダーやお世話係も積極的に引き受けました」(商工ひのくに)と西田さんは語っています。もちろん西田さんが手がけられようとした事業そのものにメディアが関心を示さなければ、いくら顔を売っても連鎖はしませんね。しかし、事業そのものがどんなにインパクトのあるものでも、それが確実に歩を進めていなければメディアはフォローしてくれません。
西田さんの何がメディアの関心を呼んだのかをもう少し掘り下げてみようと、まず、西田さんがどのようにして起業するに至ったか、そして、西田ミワという女性がどういう方なのかを知るために、起業前のことについて振り返っていただきました。
高校を卒業した西田さんは、ご実家でアパート経営されていることもあって、建築に興味を抱きながら、とあるゼネコンに入社されます。そして、不動産販売に携わる中で宅建主任の資格を取得され、建築業界、不動産業界でのキャリアを積んでいかれました。この辺までの西田さんは業界では一般に見受けられるOLの一人でした。
仕事にも慣れた頃から、西田さんの中で「私自身、果たして世の中でどのくらい通用するのだろう?」という単純明快な疑問がわいてきました。さらにそれが「そもそも、自分とはいったい何者なのか?」という命題に突き当たっていきます。西田さんは23歳のとき、突然思い立って「自分探しの旅」のためにアメリカに旅立ちました。宿だけを確保しながらの、2週間にわたるアメリカの旅です。しかし結局、アメリカでは何も見つけることはできませんでした。
その後熊本に戻った西田さんは、ハウスメーカーで建売住宅の営業職をはじめに様々な仕事を経験されます。数えるとそれは20種類以上にも及ぶといいます。ときには二足・三足のわらじを履いたこともあるそうです。とにかく自分にあった仕事に出会うために「OL時代は原因を外に見つけるのが得意で、気に入らなければ即転職」という「ジョブ・サーフィン」とも言える状況でした。西田さんの「自分探し」はまだ続いていました。
そこへ運命は、西田さんが求める「ほんとの自分」ではなく、「一生のパートナー」を巡り会わせることにしました。この運命の波に乗って28歳で結婚され、翌年ご長女を出産されます。一見順調な新婚生活でした。ところが、家庭に納まった西田さんは社会的な接点を失ったような気持ちから、一時、育児ノイローゼ状態に陥ってしまいます。
この閉塞感の捌け口として西田さんは、当時立ち上がったばかりのメールマガジンに思いのたけをぶつけ始めました。今から10年位前のことですから、今ほどインターネットは盛んではありませんでしたが、このメルマガがなんと1,400名の読者の共感を呼んだのでした。今の西田さんの仕事の出発点はここから生まれたのでした。
以来、西田さんは家庭に加えて「自分の仮の居場所」を見つけて、まずはネット社会を泳ぎまわることになります。ネットサーフィンをしながら、現在の環境の中で再就職の道が固く閉ざされていることもひしひしと感じていました。一方で、メルマガの読者にはいろんな人がいて、彼らから情報提供を受けたり、相談に応えたりする中で、今目の前にあるパソコンとインターネットでなんらかのサービス提供ができるのではないかと考え、西田さんはWEBデザーナーとして独り立ちすることを決意します。

そして、起業。しかし前述のように半年間は全く仕事が入ってきません。西田さんはそんな起業後の苦しみの中からもうひとつ「居場所」について思い至ります。「一人でやってみて初めて、自分にはこれまで会社という後ろ盾があったことが自覚できたんです。そして、そのありがたさに気づいたんです」と。実社会の海は西田さんにとって、ネット社会ほど自由な回遊空間ではありませんでしたが、冒頭の積極的な人脈づくりが少しずつ実っていきました。
「Webデザイナーとして開業はしましたが、何しろ独学ですから、当初はお客様にご協力いただきながら必死で制作していました。そして、やればやるほどその都度、自分に欠けているものがわかってくるんですね。その発見が喜びだったんです。確かに苦労はしましたが、お客様が喜ぶ顔が見たいという気持ちの方が勝っていたと思います」と、西田さんはその当時の思いを語ります。
これまでずっと探していた「自分」が直接的にではなく、結婚、出産、育児というプロセスを経てようやく西田さんの目の前に現われたのです。前述の「やればやるほどその都度、自分に欠けているものがわかってくるんですね。その発見が喜びだったんです」と語る西田さんの言葉とあわせてみると、結局、探している「自分」は、もともと西田さんの中にあったことがわかります。そして「仮の自分の居場所」が「ほんとの自分の居場所」へと変わっていくのです。
西田さんのこんな「自分探し」の話を聞きながら、私は、あるブログの読者同士である武闘派銀行マン「のんた」さんのブログ「潰してたまるか!お前の会社」の次のような記事のことを思い出していました。(http://ameblo.jp/k-hotline/entry-10080027975.html)
自分の取り得や才能を、最も簡単に見つけられる方法があります。それは、起業することです。逆に言えば、起業しない限り、あなたの本当の才能を見つけ出すことは出来ません。すでに起業して苦労した人は分かると思いますが、人というものは、一人ぼっちになって初めて、自分自身の力量が分かります。「自分に何が出来るのか」ということを客観視できます。
会社にいる限りは、基本的に温室育ちであることに大差ありません。そんな環境で、いくら自分に何が出来るかを考えてみたところで、客観視することなど不可能です。資格を持っているから大丈夫だろう、営業が得意だから大丈夫だろうという甘い考えは、起業したとたんに吹き飛んでしまいます。そして、最終的には、「自分は何のために生まれてきたのか」ということが分かります。そこから先は、また自分で決めるのです。
私自身がそうであったように、起業して自分が得意だと思っていたことに力を注いだ結果、「こんなはずじゃなかった」と感じることなど日常茶飯事です。好きだと思って始めたのに、実は好きではなかったということがあってもいいのです。そうやって、少しずつ自分を分かっていくことが、起業する喜びでもあるのです。あなたが現在いるところは、世界で一番いいところでもなければ、悪いところでもありません。今がベストだと思っても、外に出るともっといいところがあったという発見をし、世間の広さを知って喜びを知るのです。
自分の取り得を知ってから起業するのではありません。起業することで、自分の取り得を見つけることができるのです。
今の西田さんの本業は、「DOLPHIN WORKS」における、インターネットコンテンツの企画・制作、ブログ・メルマガの執筆代行、そして昨年立ち上げた「STAND UP」における次世代リーダーのための起業家育成活動、ワークショップ等企画運営、加えて共同出版にまでと多岐に及んでいます。更に4月1日からは「STAND UP」の弟分的団体、社会起業家とフリーランスのための情報発信局「SOHOフォレスト」を稼働されるそうです。これは、熊本県を拠点に活動するフリーランサー、社会起業家、個人事業主のシンクタンクとしての位置づけで、交流の場、ビジネスマッチングの場としての受け皿になるようです。
「高度なコミュニケーション能力と、地域やネットワークの媒介としての役目を担う会社でありたい」という願いをこめたという「DOLPHIN WORKS(ドルフィンワークス)」。この屋号は更に、「ボスを目ざすサメとリーダーを目ざすイルカ―上司・同僚・部下から評価されるイルカ型ビジネスのすすめ」(単行本))という本に書かれた次ぎの内容にインスパイアされたものでもあるそうです。

社会で働く人は、男女問わず、サメ(海の殺し屋)、グッピー(自己中心主義者)、イルカ(高い知性を持って、和を大切にする人)に分けられる。それぞれどのようにつきあえばよいか、アメリカのビジネスで成功している女性200人のインタビューを基に構成されたハウツーブック。//内容(「BOOK」データベースより)
そして、女性鉱山労働者になったシングルマザーが、男性社会の中で耐え難いセクシャル・ハラスメントを受け、立ち上がるまでを実話に基づいて描いたシャーリーズ・セロン主演の「スタンド・アップ」からインスピレーションを得たという「STAND UP」。西田さんは「この受け皿を『スター誕生』」に場にしたいんです」と語ってくれました。

最後に今後の活動についておうかがいしました。「私って、思ったことと今やっていることの間にギャップがあったりします。それはいろんなニーズや状況によって、そのときの最もよい形がケース・バイ・ケースで違ってくるからで、私の中ではごく自然な流れで方向転換しています」と笑いながら語る西田さんには何か一筋ピンとしたものが通っていることを感じさせる目の輝きがあります。
第一稿のメールへの西田さんの返信に次のようなメッセージがありました。
もう一つ、私が目指す、社会的なミッションがあります。現代社会においては、従来の社会が「リアル地球」と称するならば、インターネット上では「バーチャル地球」が存在しており、2つの地球が互いに干渉したり、シンクロしあって、現在のような社会が形成されています。(googleなどの影響で加速していますね)
「情報格差」という言葉がありますが、私の解釈では、格差とは、その2つの地球を上手に住み分けできるかできないかの違いによって起こるもの。インフラ面では、日本においては、ほぼ平等に権利を手に入れているのですが、必ず加速していく社会の波に乗れない人も出てくる。私は、その受け皿が絶対的に必要だと思っています。
ドルフィンワークスは、その、リアルとバーチャルをつなぐ潤滑油のような役目と、希薄になりつつある”心”と心の闇に焦点をあて、人と人、ネットワークをつなぐ潤滑油になりたいと思っています。SOHOフォレストも、スタンドアップも、その通過点での試みです。
西田さんのこれまでの話を聞いていると、一人の女性が「顔のない」ネット社会の海に飛び出し、そこでコミュニケーションの必要性を学び、そのことによって「自分」という存在意義がはっきりと実像化され、その実像をまとって「顔のある」実社会に繋がっている姿が見て取れます。そして今度は「顔のある」存在として、再びネット社会の海を自由の泳ぎまわっている姿。
創業以来、なぜ西田さんがこれほど注目を浴びておられるのか?それはネット社会と実社会という二つの社会を泳ぎ回る西田さんの行動範囲が一般人よりも遥かに広いわけですから、当然の帰結な訳です。時には戦略的に網にかかることもあるでしょうし、無作為に泳いでいるところを発見されたりもするでしょう。結果的に露出頻度が高くなり、正のスパイラルを起こすことになるという訳です。
「自分が味わった苦悩や失敗を伝えたり、コーチングすることで、これらから起業する方々が少しでもリスクを回避してもらえるようにサポートしていきたいと思っています。また、意図に反して苦境に立ってしまった方にもフォローできるような体制も組んでいきたいと思います。そして、仕事でも家庭でもストレスなくやっていけるような環境づくりをいろんな方法で目指してきたいですね」と語ってくれました。
西田ミワさんへのアクセスは下記。
ドルフィンワークス
代表 西田ミワ
OFFICE:(〒862-0902)熊本市東本町16-39-1001
TEL&FAX:096-368-8176 / MOBILE:090-3415-5630
URL:http://dolphin-w.com / MAIL:info@dolphin-w.com
SKYPE:dw-nishida / mixiネーム:旅ねこ
------------------------------------------------------------------------
▼スタンドアップblog更新中!
★http://tabineko.otemo-yan.net/
◆「SOHOフォレスト」準備中!
(追記)~西田さんからのメッセージ~
この本になぞりながら、次世代リーダーのあり方について私のメンターである増田紀彦氏がこのような記事を書いておられます。
▼【独立事典デスク:週刊「増田紀彦」通信】
第44回「それぞれの持ち味」 2003.06.27配信
http://www.keyplanet.com/keypla/masuda/masu04.html
求めている仕事のありかたを模索している時、偶然に、増田氏のこの記事を読み、リーダーのあり方について深く感銘を受けました。※増田紀彦氏は、アントレ編集デスクでもあり、起業家でもあり、現在は、NICeのチーフプロデューサーでもあります。
▼NICe(起業家SNS) 経済産業省プロジェクト
http://www.nice-vec.jp/
昨年、その「輝女(テルージョ)」に輝いたお一人にドルフィンワークス代表の西田ミワさんがいらっしゃいました。他に三人の女性経営者がいらっしゃいますが、事業面から個人的に関心があった西田さんにインタヴュー依頼をさせていただき、今回お話をうかがいました。という訳で第17回目のゲストは、「コンテンツディレクター/プランナー」、「財団法人生涯学習開発財団認定コーチ」として活躍されている西田ミワさんです。

実は今回のインタヴューを終えて、ちょっと困りました。西田さんにはいろんなメディアからの取材が多く、私があえてここで書くことはないんじゃないかと思うほどだったからです。しかも、取材後、この記事を書くにあたって西田さんからいただいた資料を読みながら何気なくHPをチェックするといきなり、「エントワークリンケージ 後藤愼一様よりネット取材いただくことになりました。どんな視点で取り上げてくださるのか楽しみです^^のちほどご報告いたします」と書かれているではありませんか。暗黙のプレッシャーです。
とは言え、お忙しい中でせっかく頂いた時間ですので、西田さんご自身、今後の事業についてうかがったことを私なりの解釈で皆さんにお伝えしたいと思います。第一稿を西田さんにメールで送ったところ、前述の「暗黙のプレッシャー」について、西田さんから「脳化学的に申しますと、この『ピュアプレッシャー』は”さらなる向上と幸福感を誘発するドーパミンを大量放出”するそうで…」という励ましをいただきました。それでは本題に入ります。

2001年7月の創業以来、なぜ西田さんがこれほど注目を浴びておられるのか?私の西田さんに対する興味はこの点にありました。取材を終えてその答えが理解できたように思います。実は、西田さんに数多くのメディアから取材依頼が寄せられるようになったのは、起業から半年間、売上ゼロという苦境に喘いだ西田さんが、そこから脱するために暗中模索の中でたどり着いて実行した「顔を売る」という行動の賜物だったことがわかりました。
「私と同じように起業した人、起業を目指している人、様々な異業種、同業種の交流会に顔を出し、団体のリーダーやお世話係も積極的に引き受けました」(商工ひのくに)と西田さんは語っています。もちろん西田さんが手がけられようとした事業そのものにメディアが関心を示さなければ、いくら顔を売っても連鎖はしませんね。しかし、事業そのものがどんなにインパクトのあるものでも、それが確実に歩を進めていなければメディアはフォローしてくれません。
西田さんの何がメディアの関心を呼んだのかをもう少し掘り下げてみようと、まず、西田さんがどのようにして起業するに至ったか、そして、西田ミワという女性がどういう方なのかを知るために、起業前のことについて振り返っていただきました。
高校を卒業した西田さんは、ご実家でアパート経営されていることもあって、建築に興味を抱きながら、とあるゼネコンに入社されます。そして、不動産販売に携わる中で宅建主任の資格を取得され、建築業界、不動産業界でのキャリアを積んでいかれました。この辺までの西田さんは業界では一般に見受けられるOLの一人でした。
仕事にも慣れた頃から、西田さんの中で「私自身、果たして世の中でどのくらい通用するのだろう?」という単純明快な疑問がわいてきました。さらにそれが「そもそも、自分とはいったい何者なのか?」という命題に突き当たっていきます。西田さんは23歳のとき、突然思い立って「自分探しの旅」のためにアメリカに旅立ちました。宿だけを確保しながらの、2週間にわたるアメリカの旅です。しかし結局、アメリカでは何も見つけることはできませんでした。
その後熊本に戻った西田さんは、ハウスメーカーで建売住宅の営業職をはじめに様々な仕事を経験されます。数えるとそれは20種類以上にも及ぶといいます。ときには二足・三足のわらじを履いたこともあるそうです。とにかく自分にあった仕事に出会うために「OL時代は原因を外に見つけるのが得意で、気に入らなければ即転職」という「ジョブ・サーフィン」とも言える状況でした。西田さんの「自分探し」はまだ続いていました。
そこへ運命は、西田さんが求める「ほんとの自分」ではなく、「一生のパートナー」を巡り会わせることにしました。この運命の波に乗って28歳で結婚され、翌年ご長女を出産されます。一見順調な新婚生活でした。ところが、家庭に納まった西田さんは社会的な接点を失ったような気持ちから、一時、育児ノイローゼ状態に陥ってしまいます。
この閉塞感の捌け口として西田さんは、当時立ち上がったばかりのメールマガジンに思いのたけをぶつけ始めました。今から10年位前のことですから、今ほどインターネットは盛んではありませんでしたが、このメルマガがなんと1,400名の読者の共感を呼んだのでした。今の西田さんの仕事の出発点はここから生まれたのでした。
以来、西田さんは家庭に加えて「自分の仮の居場所」を見つけて、まずはネット社会を泳ぎまわることになります。ネットサーフィンをしながら、現在の環境の中で再就職の道が固く閉ざされていることもひしひしと感じていました。一方で、メルマガの読者にはいろんな人がいて、彼らから情報提供を受けたり、相談に応えたりする中で、今目の前にあるパソコンとインターネットでなんらかのサービス提供ができるのではないかと考え、西田さんはWEBデザーナーとして独り立ちすることを決意します。

そして、起業。しかし前述のように半年間は全く仕事が入ってきません。西田さんはそんな起業後の苦しみの中からもうひとつ「居場所」について思い至ります。「一人でやってみて初めて、自分にはこれまで会社という後ろ盾があったことが自覚できたんです。そして、そのありがたさに気づいたんです」と。実社会の海は西田さんにとって、ネット社会ほど自由な回遊空間ではありませんでしたが、冒頭の積極的な人脈づくりが少しずつ実っていきました。
「Webデザイナーとして開業はしましたが、何しろ独学ですから、当初はお客様にご協力いただきながら必死で制作していました。そして、やればやるほどその都度、自分に欠けているものがわかってくるんですね。その発見が喜びだったんです。確かに苦労はしましたが、お客様が喜ぶ顔が見たいという気持ちの方が勝っていたと思います」と、西田さんはその当時の思いを語ります。
これまでずっと探していた「自分」が直接的にではなく、結婚、出産、育児というプロセスを経てようやく西田さんの目の前に現われたのです。前述の「やればやるほどその都度、自分に欠けているものがわかってくるんですね。その発見が喜びだったんです」と語る西田さんの言葉とあわせてみると、結局、探している「自分」は、もともと西田さんの中にあったことがわかります。そして「仮の自分の居場所」が「ほんとの自分の居場所」へと変わっていくのです。
西田さんのこんな「自分探し」の話を聞きながら、私は、あるブログの読者同士である武闘派銀行マン「のんた」さんのブログ「潰してたまるか!お前の会社」の次のような記事のことを思い出していました。(http://ameblo.jp/k-hotline/entry-10080027975.html)
自分の取り得や才能を、最も簡単に見つけられる方法があります。それは、起業することです。逆に言えば、起業しない限り、あなたの本当の才能を見つけ出すことは出来ません。すでに起業して苦労した人は分かると思いますが、人というものは、一人ぼっちになって初めて、自分自身の力量が分かります。「自分に何が出来るのか」ということを客観視できます。
会社にいる限りは、基本的に温室育ちであることに大差ありません。そんな環境で、いくら自分に何が出来るかを考えてみたところで、客観視することなど不可能です。資格を持っているから大丈夫だろう、営業が得意だから大丈夫だろうという甘い考えは、起業したとたんに吹き飛んでしまいます。そして、最終的には、「自分は何のために生まれてきたのか」ということが分かります。そこから先は、また自分で決めるのです。
私自身がそうであったように、起業して自分が得意だと思っていたことに力を注いだ結果、「こんなはずじゃなかった」と感じることなど日常茶飯事です。好きだと思って始めたのに、実は好きではなかったということがあってもいいのです。そうやって、少しずつ自分を分かっていくことが、起業する喜びでもあるのです。あなたが現在いるところは、世界で一番いいところでもなければ、悪いところでもありません。今がベストだと思っても、外に出るともっといいところがあったという発見をし、世間の広さを知って喜びを知るのです。
自分の取り得を知ってから起業するのではありません。起業することで、自分の取り得を見つけることができるのです。
今の西田さんの本業は、「DOLPHIN WORKS」における、インターネットコンテンツの企画・制作、ブログ・メルマガの執筆代行、そして昨年立ち上げた「STAND UP」における次世代リーダーのための起業家育成活動、ワークショップ等企画運営、加えて共同出版にまでと多岐に及んでいます。更に4月1日からは「STAND UP」の弟分的団体、社会起業家とフリーランスのための情報発信局「SOHOフォレスト」を稼働されるそうです。これは、熊本県を拠点に活動するフリーランサー、社会起業家、個人事業主のシンクタンクとしての位置づけで、交流の場、ビジネスマッチングの場としての受け皿になるようです。
「高度なコミュニケーション能力と、地域やネットワークの媒介としての役目を担う会社でありたい」という願いをこめたという「DOLPHIN WORKS(ドルフィンワークス)」。この屋号は更に、「ボスを目ざすサメとリーダーを目ざすイルカ―上司・同僚・部下から評価されるイルカ型ビジネスのすすめ」(単行本))という本に書かれた次ぎの内容にインスパイアされたものでもあるそうです。

社会で働く人は、男女問わず、サメ(海の殺し屋)、グッピー(自己中心主義者)、イルカ(高い知性を持って、和を大切にする人)に分けられる。それぞれどのようにつきあえばよいか、アメリカのビジネスで成功している女性200人のインタビューを基に構成されたハウツーブック。//内容(「BOOK」データベースより)
そして、女性鉱山労働者になったシングルマザーが、男性社会の中で耐え難いセクシャル・ハラスメントを受け、立ち上がるまでを実話に基づいて描いたシャーリーズ・セロン主演の「スタンド・アップ」からインスピレーションを得たという「STAND UP」。西田さんは「この受け皿を『スター誕生』」に場にしたいんです」と語ってくれました。

最後に今後の活動についておうかがいしました。「私って、思ったことと今やっていることの間にギャップがあったりします。それはいろんなニーズや状況によって、そのときの最もよい形がケース・バイ・ケースで違ってくるからで、私の中ではごく自然な流れで方向転換しています」と笑いながら語る西田さんには何か一筋ピンとしたものが通っていることを感じさせる目の輝きがあります。
第一稿のメールへの西田さんの返信に次のようなメッセージがありました。
もう一つ、私が目指す、社会的なミッションがあります。現代社会においては、従来の社会が「リアル地球」と称するならば、インターネット上では「バーチャル地球」が存在しており、2つの地球が互いに干渉したり、シンクロしあって、現在のような社会が形成されています。(googleなどの影響で加速していますね)
「情報格差」という言葉がありますが、私の解釈では、格差とは、その2つの地球を上手に住み分けできるかできないかの違いによって起こるもの。インフラ面では、日本においては、ほぼ平等に権利を手に入れているのですが、必ず加速していく社会の波に乗れない人も出てくる。私は、その受け皿が絶対的に必要だと思っています。
ドルフィンワークスは、その、リアルとバーチャルをつなぐ潤滑油のような役目と、希薄になりつつある”心”と心の闇に焦点をあて、人と人、ネットワークをつなぐ潤滑油になりたいと思っています。SOHOフォレストも、スタンドアップも、その通過点での試みです。
西田さんのこれまでの話を聞いていると、一人の女性が「顔のない」ネット社会の海に飛び出し、そこでコミュニケーションの必要性を学び、そのことによって「自分」という存在意義がはっきりと実像化され、その実像をまとって「顔のある」実社会に繋がっている姿が見て取れます。そして今度は「顔のある」存在として、再びネット社会の海を自由の泳ぎまわっている姿。
創業以来、なぜ西田さんがこれほど注目を浴びておられるのか?それはネット社会と実社会という二つの社会を泳ぎ回る西田さんの行動範囲が一般人よりも遥かに広いわけですから、当然の帰結な訳です。時には戦略的に網にかかることもあるでしょうし、無作為に泳いでいるところを発見されたりもするでしょう。結果的に露出頻度が高くなり、正のスパイラルを起こすことになるという訳です。
「自分が味わった苦悩や失敗を伝えたり、コーチングすることで、これらから起業する方々が少しでもリスクを回避してもらえるようにサポートしていきたいと思っています。また、意図に反して苦境に立ってしまった方にもフォローできるような体制も組んでいきたいと思います。そして、仕事でも家庭でもストレスなくやっていけるような環境づくりをいろんな方法で目指してきたいですね」と語ってくれました。
西田ミワさんへのアクセスは下記。
ドルフィンワークス
代表 西田ミワ
OFFICE:(〒862-0902)熊本市東本町16-39-1001
TEL&FAX:096-368-8176 / MOBILE:090-3415-5630
URL:http://dolphin-w.com / MAIL:info@dolphin-w.com
SKYPE:dw-nishida / mixiネーム:旅ねこ
------------------------------------------------------------------------
▼スタンドアップblog更新中!
★http://tabineko.otemo-yan.net/
◆「SOHOフォレスト」準備中!
(追記)~西田さんからのメッセージ~
この本になぞりながら、次世代リーダーのあり方について私のメンターである増田紀彦氏がこのような記事を書いておられます。
▼【独立事典デスク:週刊「増田紀彦」通信】
第44回「それぞれの持ち味」 2003.06.27配信
http://www.keyplanet.com/keypla/masuda/masu04.html
求めている仕事のありかたを模索している時、偶然に、増田氏のこの記事を読み、リーダーのあり方について深く感銘を受けました。※増田紀彦氏は、アントレ編集デスクでもあり、起業家でもあり、現在は、NICeのチーフプロデューサーでもあります。
▼NICe(起業家SNS) 経済産業省プロジェクト
http://www.nice-vec.jp/
2008年03月16日
音楽で農業支援、ツゥートクエンジニアリング・永脇泰夫(16)
ミュージックバナナというバナナをご存知でしょうか?宮崎県の都城でモーツアルトを聞いて育ったバナナのことです。バナナ自体は青い状態で輸入して、日本で追熟してから販売する商品。ミュージックバナナは、フィリピンの海抜300メートル以上の高地で栽培されたバナージュという優良品種をコンテナ積みのまま都城へ輸送し、熟成倉庫に搬入し、モーツァルトを聞かせて熟成しているといいます。

モーツアルトの曲には8000ヘルツ以上の高周波音とゆらぎの音がたくさん含まれていて、あるゆるものの分子を活性化する作用があると言われ、「モーツアルト効果」という言葉まで生まれています。波動がキーワードだそうです。私はまだ食べたことはありませんが、消費者調査では90%近くの人が一般のバナナよりもおいしいと回答しているという結果も出ているそうです。
このミュージックバナナを認定しているのが「日本音楽熟成協会」です。この協会は、「音楽熟成の研究と開発により、その成果を会員および一般に啓発・普及し、もって社会の健全な発展に寄与する事を目的」とし、会長は七田チャイルドアカデミー、右脳開発で有名な七田眞さんです。「都城大同青果」がこの協会に技術的なアドバイスを受けて音楽熟成されたこのバナナは傷みも少ないということです。
また前置きが長くなりましたが、16回目のゲストは、こうした話とは関係なく熊本県の農業を音楽の力で再生させたいと昨年1月下旬に起業した㈱ツゥートクエンジニアリング・代表取締役の永脇泰夫さん(50)です。永脇さんとのご縁は、第6回目のゲスト田上菜穂美さんのオフィスがある「夢挑戦プラザ21」にお邪魔した際に、入居会社一覧を見て同社のことを知り、田上さんに紹介していただきました。

永脇さんは御船町のご出身。小学校から高校まで御船で過され、前職の建設会社で25年間、音響設備の仕事に携わっておられました。公共ホールや学校の音響、放送設備、映像、通信システム設備の設計・施工という仕事です。折からの公共事業費の削減で事業が縮小化に向かう中、これまでの技術を、同じく苦境にあえぐ県内農業の再生に活かしたいということで独立、起業されました。
会社名の「ツゥートク」は前職の会社名から。「社長に頼んで暖簾分け的にいただきました」と、前職の仕事と会社に愛着を持つ技術者としての永脇さんのお人柄が現われています。この会社から二人の後輩を引き連れての起業でした。ちなみに「ツゥートク」は、「通信、特殊機器」の頭文字を取ったネーミングです。
ミュージックバナナの話とは関係なく、と書きましたが、この話は永脇さんからお聞きしたものです。永脇さんも音楽を使って農作物を栽培したり、牛や豚、鶏などにモーツァルトなどの音楽を聞かせる農家があるということは勿論ご存知で、それだからこそこの事業に足を踏み入れられた訳です。起業後にいろいろ情報収集してみたところ、その試みが全国的に行われていたことがわかった、ということで、このミュージックバナナの話もその一つです。
そして永脇さんの情報収集の中から紹介してもらったのが「タンパク質の音楽」(ちくまプリマーブックス)という本です。この本の紹介文には次のようなコメントがありました。

「タンパク質と音楽。まったく関係がないように見えるこの2つの事柄が、実はとても深く結びついているのです。地球上のあらゆる生命活動が、タンパク質の奏でる音楽に左右されていると言っても過言ではありません。“タンパク質の音楽”の用途はさまざま。正しく利用することによって、近い将来、農業や医療の世界に革命がもたらされることになるでしょう」
タンパク質の分子構造を音符に置き換えるとなんと、クラシック調のメロディーが紡ぎだされるというのです。「たんぱく質の音楽」には次にように書かれています。
「ウシにモーツァルトを聞かせると乳がよく出る」。音楽の効果を示すのによく取り上げられる話である。ところがその理由となると、「ウシも音楽でいい気持ちになり、乳の出もよくなったのだろう」くらいにしか考えられていない。だがステルンナイメール博士の提案した《タンパク質の音楽》理論によれば、この現象も十分に説明ができるのだ。
乳腺の発達や乳汁の分泌を促すタンパク質として、プロラクチンが知られている。その機能から、乳腺刺激ホルモンとも呼ばれる。そこでステルンナイメール博士は、このタンパク質をメロディに置き換えることを思いついた。果たして予想に違わず、モーツァルト的としか言いようのない部分が含まれていたのだ。
この本が永脇さんのインスピレーションを裏付けました。「『安全でおいしい食の追及』をテーマに、第一次産業(農業・畜産・酪農・養鶏等)を音楽と音響設備で支援しよう。ビニールハウス・牛舎・豚舎に高品の音楽を流し、農作物・家畜に癒しの空間を作り出し、生産性の向上を目指そう」と。現状では各農家が独自に取り組んでいる音楽熟成を、永脇さんは一つのシステムとして構築し、安価に提供したいと考えておられます。
例えば、朝5時からモーツァルトが流れ7時に自動的に止まるシステム。日によって、時間によって流す曲を自動的に変えるシステムなどなど。また、動物の条件反射も性質を利用して、餌を与える時間を音楽で知らせたり、乳牛には相当なストレスになるという搾乳時に音楽でストレスを緩和したりといろいろな応用が可能だそうです。

「耳のある動物なら音楽を聞かせても効果がありそうなことはわかってもらえますが、耳のない植物に効果があるのかとよく聞かれます。でも実際は植物こそ、この音楽が効果的なんですね。音楽、音響は空気振動です。植物はこの空気振動を敏感に受容してくれるのです。よい空気振動は、光合成を促進したり、水分の吸収力を高めるという研究結果もあります。ですから、動物よりも植物は感受性が高いと言えますよ」と永脇さん。確かに観葉植物に声をかけるとよく育つという話はよく聞きますよね。
目下の課題は二つ。音響設備による研究データが少ないこと。また、このデータを取るには研究機関と農業施設が必要になって、資金も時間もかかる。ですから、永脇さんは今のところこのシステムを積極的に販売しようとは思っていません。ご自分の収穫する農作物に付加価値をつけたいと積極的に考えている農家の方々と一緒に取り組んでいきたいというのが永脇さんの意向です。
もう一つは、この25年間ずっと建設業に携わっただけに、農業関係者の人脈が少ないことです。現在は前職時代の音響設備の仕事で経営を支えながら、農業関係者の人脈を少しずつ広げて早めにこの事業へ本格的に転換することを目指されています。また将来的には水産業への応用も視野に入っています。
研究データは少なくとも「音楽を聞かせて育った野菜は、甘味が強くておいしい」という話は少なくありません。この辺は当面、実証主義ではなく経験主義でいくしかないと私もそう思います。「今、日本の食の安全が問われていますね。30%台の低い自給率、飼料の高騰による生産コスト増を打開するためには日本の地産地消を高めることです。一日も早く農業の再生を実現しければならない。そのために役に立ちたい。私たちは挑戦します」と永脇さんは熱く語られました。
この記事をご覧頂いた農家の方、知り合いに農家の方がいらっしゃる方で興味のある方は下記までアクセスして下さいね。
㈱ツゥートクエンジニアリング
上益城郡益城町田原2081-10 夢挑戦プラザ21 オフィス1号室
TEL;096-214-5233
FAX;096-289-3177
E-mai;tsutoku-engl@bz03.plala.or.jp

モーツアルトの曲には8000ヘルツ以上の高周波音とゆらぎの音がたくさん含まれていて、あるゆるものの分子を活性化する作用があると言われ、「モーツアルト効果」という言葉まで生まれています。波動がキーワードだそうです。私はまだ食べたことはありませんが、消費者調査では90%近くの人が一般のバナナよりもおいしいと回答しているという結果も出ているそうです。
このミュージックバナナを認定しているのが「日本音楽熟成協会」です。この協会は、「音楽熟成の研究と開発により、その成果を会員および一般に啓発・普及し、もって社会の健全な発展に寄与する事を目的」とし、会長は七田チャイルドアカデミー、右脳開発で有名な七田眞さんです。「都城大同青果」がこの協会に技術的なアドバイスを受けて音楽熟成されたこのバナナは傷みも少ないということです。
また前置きが長くなりましたが、16回目のゲストは、こうした話とは関係なく熊本県の農業を音楽の力で再生させたいと昨年1月下旬に起業した㈱ツゥートクエンジニアリング・代表取締役の永脇泰夫さん(50)です。永脇さんとのご縁は、第6回目のゲスト田上菜穂美さんのオフィスがある「夢挑戦プラザ21」にお邪魔した際に、入居会社一覧を見て同社のことを知り、田上さんに紹介していただきました。

永脇さんは御船町のご出身。小学校から高校まで御船で過され、前職の建設会社で25年間、音響設備の仕事に携わっておられました。公共ホールや学校の音響、放送設備、映像、通信システム設備の設計・施工という仕事です。折からの公共事業費の削減で事業が縮小化に向かう中、これまでの技術を、同じく苦境にあえぐ県内農業の再生に活かしたいということで独立、起業されました。
会社名の「ツゥートク」は前職の会社名から。「社長に頼んで暖簾分け的にいただきました」と、前職の仕事と会社に愛着を持つ技術者としての永脇さんのお人柄が現われています。この会社から二人の後輩を引き連れての起業でした。ちなみに「ツゥートク」は、「通信、特殊機器」の頭文字を取ったネーミングです。
ミュージックバナナの話とは関係なく、と書きましたが、この話は永脇さんからお聞きしたものです。永脇さんも音楽を使って農作物を栽培したり、牛や豚、鶏などにモーツァルトなどの音楽を聞かせる農家があるということは勿論ご存知で、それだからこそこの事業に足を踏み入れられた訳です。起業後にいろいろ情報収集してみたところ、その試みが全国的に行われていたことがわかった、ということで、このミュージックバナナの話もその一つです。
そして永脇さんの情報収集の中から紹介してもらったのが「タンパク質の音楽」(ちくまプリマーブックス)という本です。この本の紹介文には次のようなコメントがありました。

「タンパク質と音楽。まったく関係がないように見えるこの2つの事柄が、実はとても深く結びついているのです。地球上のあらゆる生命活動が、タンパク質の奏でる音楽に左右されていると言っても過言ではありません。“タンパク質の音楽”の用途はさまざま。正しく利用することによって、近い将来、農業や医療の世界に革命がもたらされることになるでしょう」
タンパク質の分子構造を音符に置き換えるとなんと、クラシック調のメロディーが紡ぎだされるというのです。「たんぱく質の音楽」には次にように書かれています。
「ウシにモーツァルトを聞かせると乳がよく出る」。音楽の効果を示すのによく取り上げられる話である。ところがその理由となると、「ウシも音楽でいい気持ちになり、乳の出もよくなったのだろう」くらいにしか考えられていない。だがステルンナイメール博士の提案した《タンパク質の音楽》理論によれば、この現象も十分に説明ができるのだ。
乳腺の発達や乳汁の分泌を促すタンパク質として、プロラクチンが知られている。その機能から、乳腺刺激ホルモンとも呼ばれる。そこでステルンナイメール博士は、このタンパク質をメロディに置き換えることを思いついた。果たして予想に違わず、モーツァルト的としか言いようのない部分が含まれていたのだ。
この本が永脇さんのインスピレーションを裏付けました。「『安全でおいしい食の追及』をテーマに、第一次産業(農業・畜産・酪農・養鶏等)を音楽と音響設備で支援しよう。ビニールハウス・牛舎・豚舎に高品の音楽を流し、農作物・家畜に癒しの空間を作り出し、生産性の向上を目指そう」と。現状では各農家が独自に取り組んでいる音楽熟成を、永脇さんは一つのシステムとして構築し、安価に提供したいと考えておられます。
例えば、朝5時からモーツァルトが流れ7時に自動的に止まるシステム。日によって、時間によって流す曲を自動的に変えるシステムなどなど。また、動物の条件反射も性質を利用して、餌を与える時間を音楽で知らせたり、乳牛には相当なストレスになるという搾乳時に音楽でストレスを緩和したりといろいろな応用が可能だそうです。

「耳のある動物なら音楽を聞かせても効果がありそうなことはわかってもらえますが、耳のない植物に効果があるのかとよく聞かれます。でも実際は植物こそ、この音楽が効果的なんですね。音楽、音響は空気振動です。植物はこの空気振動を敏感に受容してくれるのです。よい空気振動は、光合成を促進したり、水分の吸収力を高めるという研究結果もあります。ですから、動物よりも植物は感受性が高いと言えますよ」と永脇さん。確かに観葉植物に声をかけるとよく育つという話はよく聞きますよね。
目下の課題は二つ。音響設備による研究データが少ないこと。また、このデータを取るには研究機関と農業施設が必要になって、資金も時間もかかる。ですから、永脇さんは今のところこのシステムを積極的に販売しようとは思っていません。ご自分の収穫する農作物に付加価値をつけたいと積極的に考えている農家の方々と一緒に取り組んでいきたいというのが永脇さんの意向です。
もう一つは、この25年間ずっと建設業に携わっただけに、農業関係者の人脈が少ないことです。現在は前職時代の音響設備の仕事で経営を支えながら、農業関係者の人脈を少しずつ広げて早めにこの事業へ本格的に転換することを目指されています。また将来的には水産業への応用も視野に入っています。
研究データは少なくとも「音楽を聞かせて育った野菜は、甘味が強くておいしい」という話は少なくありません。この辺は当面、実証主義ではなく経験主義でいくしかないと私もそう思います。「今、日本の食の安全が問われていますね。30%台の低い自給率、飼料の高騰による生産コスト増を打開するためには日本の地産地消を高めることです。一日も早く農業の再生を実現しければならない。そのために役に立ちたい。私たちは挑戦します」と永脇さんは熱く語られました。
この記事をご覧頂いた農家の方、知り合いに農家の方がいらっしゃる方で興味のある方は下記までアクセスして下さいね。
㈱ツゥートクエンジニアリング
上益城郡益城町田原2081-10 夢挑戦プラザ21 オフィス1号室
TEL;096-214-5233
FAX;096-289-3177
E-mai;tsutoku-engl@bz03.plala.or.jp
2008年03月13日
香りの伝道師、「香水の16区」田中貴子(15)(下)
オープンから翌年、田中さんに香水業界のツアーへの参加の話が舞い込みます。香水の本場、フランス、パリ、そして冒頭で触れたグラースへの旅です。田中さんの店は順調に推移し、交通センター内テナントでの坪当たりの売上がトップになる程。旅費を捻出することにはなんら問題がない状態でした。田中さんは絶好のチャンスと、このツアーに申し込みます。
初めて訪れるフランスでしたが、田中さんが注目したのはパリではなく、グラースでした。街中が香っているのです。グラースの数ある精油工場の煙突からはもくもくと煙が出ていますが、それは黒煙ではなく、バラなどから精油を抽出するための蒸留過程で出る水蒸気でした。この水蒸気によってグラースは「世界で唯一結核患者のない街」と言われ、「アロマテラピーの原点の地」だとされるそうです。田中さんは研究室への見学にも刺激され、そこの先生方と記念撮影など撮って楽しい時間を過ごしました。
日本に帰った田中さんは、また子育てと仕事に追われる日々の中に戻っていました。そんな年の夏、交通センターに向かう途中で夕立に合います。一瞬の雨で温まった地面が蒸されたかのような蒸気を立てます。それと同時に、花壇の土からスミレの精油を抽出しているような香りが漂ってきたのです。田中さんの脳裏は一瞬にしてあのグラースの光景とシンクロしていました。「いても立ってもいられなくなく」病が再発しました。

最初の訪問からまだ半年。田中さんは再びグラースの地にいました。たった一人で。田中さんは前回のルートを思い出しながら、前回訪れた研究所を目指します。田中さんが話せるフランス語は「ボンジュールとグラース」だけ。「片言でも気持ちは通じるものよ」と。到着した研究所の進入制止バーを軽く潜り抜け、制止しようとする警備員のフランス語に「ボンジュール」と応えながら、一気にエントランスまで。
エントランスには三人の女性が待ち構えていたそうです。おそらく「あなたは誰ですか?」とか「何をしに来たのか」と問われたはずです。田中さんは「私は半年前にこの研究所にきた日本人です。研究室の先生に会うためにはるばる日本から来たのです」と日本語で伝えたようです。しかし、田中さんの目にもその女性たちが、明らかに「帰れ」と言っているのはわかっていました。
しかしここまで来て引き下がることができないのが、田中さんです。田中さんはあろうことか、その三人の女性の間を潜り抜け、走り出したのです。目的の研究室へのルートはまだ記憶に新しい。その研究室まで一気に駆け抜ける作戦、いや衝動でした。走る田中さん、追う三人のフランス人。階段を駆け上り、お目当ての研究室の扉をノックし、突入。扉の向こうには、きょとんとした先生の姿。
田中さんはバッグから去年一緒に先生と撮影した写真を素早く取り出し、「覚えていますか?私です。先生に会いに日本からまた来たのです」と、多分何語ともとれない言葉で訴えたのでした。そのとき、「追っ手」の三人が部屋に駆け込んできました。先生は、「大丈夫だよ。下がっていいよ」(多分)と彼女たちを返しました。
先生のデスクの前に座った田中さんの鼻先にすーっと試験紙が差し出されます。田中さんは「ローズ?」と答える。「ウィ」と先生。「次は?」とこういうやり取りが暫く続いたそうですが、良く考えると奇妙な光景ですよ。先生はフランス語で語りかけ、田中さんは笑って「ウィ」と応え続けます。そして、弾む(?)会話を通じて、言葉での会話はできないままでも心は満たされていました。
先生との再会を果した田中さんは、グラースの町を大手を振って歩き回ったそうです。話に聞き入っていた私は、「それで、その先生に会いに行かれた今回の目的はなんだったんですか?」と尋ねました。すると「先生に会いたかっただけよ」と。恐るべし、肥後の女。

帰国後も田中さんはお店でパフューマーに会った話をしながら、心は次にグラースを訪ねることしかなかったそうです。そして次ぎの年、また次ぎの年とグラースとその先生を訪ねる中で、田中さんにはこの先生から「そんなに香りが好きなら、ここで勉強しませんか?」と言われたように聞こえたそうです。
田中さんは、一回目のフランスツアーでコーディネーターをやっていた日本人パフューマーにこの間、何通か手紙を書いていたそうですが、これまで返事が返ってこなかったそうです。ところが、数回目の訪問のとき、偶然にも彼からコンタクトがあったのです。パリに戻った田中さんはそのパフューマーに先ほどの先生とのやり取りを話しました。以来、そのパフューマーとは家族ぐるみのお付き合いだそうです。
熊本に帰った田中さんのもとへ、暫くして彼から連絡が入りました。「来年の2月にこちらに来られますか?入学が許可されることになりましたよ。私が推薦人になっておきましたから」と。そのスクールとは世界的にも有名なグラース市の由緒ある香料会社のラボ(研究室)でした。通常であれば大手化粧品メーカーなどの取引先から、しかも数人しか入学できないラボです。田中さんが断る理由はありませんでした。
それから10年後、田中さんは(有)パフューマークラブを設立。お店もさすがに手狭になり、さらに5年後、新市街に店舗「香りの16区」を移転します。時は1990年。開業から15年目のことでした。ちなみに「16区」とは、「パリの16区」からのインスピレーション。1960-70年代まで、ブルジョワエレガンスがここパリ16区に住む人々の特徴でした。20世紀初頭の建築という視点から言っても一番美しい場所、美しい言葉が残る場所の一つに数えられるといいます。

田中さんは満を持したように、翌年、厚生省から化粧品製造許可を取得し、NHK福岡文化センターでフレグランススクールを開校。更に1993年にはNKK熊本文化センターに同校熊本校を開校、熊本市政策審議懇談会委員、熊本市香りの森建設委員会委員の役職を務められます。
そして、2001年、熊本県から「県の香りマイスター」に任命されます。更に、翌年、厚生省より化粧品輸入許可を取得。続いて臭気判定士協会の理事に就任。そして、同年、フランスパフューマ―(調香師)協会の正会員になられます。今では、東京とグラースにもオフィスを構えておられます。田中さんのグラースへの訪問回数は既に50回以上にも及んでいるそうです。
すっかりグラース通となった田中さんは、かねてからグラース市長にパフューマー養成スクールの開設を打診していました。そして2003年についに、それが「Grasse Institute Perfumery(GIP)」という形で実現することになりました。今では各国からこのスクールへの入校依頼が殺到し、日本人枠が狭められるほどの人気になってしまっているそうです。
田中さんが福岡と熊本で開校したフレグランススクール(パフューマー・香りのスペシャリスト養成スクール)は既に33期生にまで達しています。卒業生の中には世界的に有名な香料会社の香料研究所に入社し活躍している方もいらっしゃいます。
この田中さんが今取り組まれているものには、「香りによる空間演出」、「高齢化社会とアロマコロジーを考える会」、「国際香りと文化の会」などがありますが、詳しくはHPを参照いただくとして、私が最も注目したいのは「九州香りアイランド構想」というプロジェクトです。

九州の恵まれた自然環境では、今でも森林浴、海水浴、太陽浴、温泉浴、花香浴をいたるところで楽しむことができます。これに新たに「芳香浴」をテーマにしたアグリ・レジャーランドを築こうというものです。香りのある植物を植え、それを抽出することによって新しい農業の新しい分野が広がることに貢献したいというものです。
減反政策や後継者の問題で人手の加わらなくなった田畑で季節の花々や香りのある植物を栽培する。「それは、売る花々や植物であってもいいし、グラースのように蒸留施設を作って精油精製をしてもいい。蒸留施設が出来る事によってその地域は豊かな香りの水蒸気で覆われ、アロマテラピー効果を発揮してそこに住む人々を心身ともに癒すことができる。その香りに誘われ、観光客も呼べるかもしれない」と田中さん。
グラースでは土地柄、主食になるような作物をつくることはできません。それだからこそ、かんきつ類などは実、皮、葉、更には種に至るまで抽出する技術を確立しているそうです。そんなグラースを見ているからこそ、田中さんには九州のこの素晴しい環境が野放しになっていることに残念な思いがあります。
例えば、ご当地の香り、四季の香りを香水にすること。田中さんは熊本市からの依頼を受け、
●森の都「森のかたらい」・・・リフレッシュ用
●水の都「川のささやき」・・・リラックス用
●肥後六花「花らんらん」・・・高揚(明るい成分)
という3部作の「くまもとの香り」を創作しています。
また、八代の名産・晩白柚の香りを抽出した香水もあります。これは、(社)熊本県物産振興協会
からH19年度の優良商品金賞を受賞されています。更に、これに晩白柚を使った焼酎、ジャム、石鹸などをセットにすることによって、晩白柚自体の付加価値を高める。そして、八代のあの駅前の臭いのイメージを晩白柚の香りで一掃することができないか?これは私が後付で勝手に妄想したものですが・・・。

2006年11月、今の「香水の16区」にお店を移転し、今では熊本市桜町に香水抽出用のラボも作りました。最後になりますが、田中さんと「香水の16区」に関する一番ホットなニュースは、なんと「東大」「NASA」、そして「紙飛行機」がキーワード。「香り」の無重力、あるいはマッハの世界での影響を研究するプロジェクトにも参加しておられるのです。詳しくは、
(http://www.yamaguchi.net/archives/005142.html)で。
とにかく「動き回るのが好きな」一人の主婦が、自分の居場所、やりがいを求めて駆け抜けた33年間。留まることが嫌いな田中さんの駆け足は、とうとう宇宙科学研究の領域にまで達していました。他にも老人介護、目の不自由な方へのサポート役としての「香り」の可能性の研究などなど田中さんの頭の中にはやりたいことが一杯です。熊本から世界へ、香りの伝道師は今日も駆けずり回ります。
香水専門店「香水の16区」;
〒860-0845 熊本市上通町5-6-1F
TEL:096(325)0418 FAX:096(326)8709
ホームページ;http://www.pluto.dti.ne.jp/~kaori16/
E-mail;kaori16@pluto.dti.ne.jp
営業時間:11:00~20:00休み:無休
初めて訪れるフランスでしたが、田中さんが注目したのはパリではなく、グラースでした。街中が香っているのです。グラースの数ある精油工場の煙突からはもくもくと煙が出ていますが、それは黒煙ではなく、バラなどから精油を抽出するための蒸留過程で出る水蒸気でした。この水蒸気によってグラースは「世界で唯一結核患者のない街」と言われ、「アロマテラピーの原点の地」だとされるそうです。田中さんは研究室への見学にも刺激され、そこの先生方と記念撮影など撮って楽しい時間を過ごしました。
日本に帰った田中さんは、また子育てと仕事に追われる日々の中に戻っていました。そんな年の夏、交通センターに向かう途中で夕立に合います。一瞬の雨で温まった地面が蒸されたかのような蒸気を立てます。それと同時に、花壇の土からスミレの精油を抽出しているような香りが漂ってきたのです。田中さんの脳裏は一瞬にしてあのグラースの光景とシンクロしていました。「いても立ってもいられなくなく」病が再発しました。

最初の訪問からまだ半年。田中さんは再びグラースの地にいました。たった一人で。田中さんは前回のルートを思い出しながら、前回訪れた研究所を目指します。田中さんが話せるフランス語は「ボンジュールとグラース」だけ。「片言でも気持ちは通じるものよ」と。到着した研究所の進入制止バーを軽く潜り抜け、制止しようとする警備員のフランス語に「ボンジュール」と応えながら、一気にエントランスまで。
エントランスには三人の女性が待ち構えていたそうです。おそらく「あなたは誰ですか?」とか「何をしに来たのか」と問われたはずです。田中さんは「私は半年前にこの研究所にきた日本人です。研究室の先生に会うためにはるばる日本から来たのです」と日本語で伝えたようです。しかし、田中さんの目にもその女性たちが、明らかに「帰れ」と言っているのはわかっていました。
しかしここまで来て引き下がることができないのが、田中さんです。田中さんはあろうことか、その三人の女性の間を潜り抜け、走り出したのです。目的の研究室へのルートはまだ記憶に新しい。その研究室まで一気に駆け抜ける作戦、いや衝動でした。走る田中さん、追う三人のフランス人。階段を駆け上り、お目当ての研究室の扉をノックし、突入。扉の向こうには、きょとんとした先生の姿。
田中さんはバッグから去年一緒に先生と撮影した写真を素早く取り出し、「覚えていますか?私です。先生に会いに日本からまた来たのです」と、多分何語ともとれない言葉で訴えたのでした。そのとき、「追っ手」の三人が部屋に駆け込んできました。先生は、「大丈夫だよ。下がっていいよ」(多分)と彼女たちを返しました。
先生のデスクの前に座った田中さんの鼻先にすーっと試験紙が差し出されます。田中さんは「ローズ?」と答える。「ウィ」と先生。「次は?」とこういうやり取りが暫く続いたそうですが、良く考えると奇妙な光景ですよ。先生はフランス語で語りかけ、田中さんは笑って「ウィ」と応え続けます。そして、弾む(?)会話を通じて、言葉での会話はできないままでも心は満たされていました。
先生との再会を果した田中さんは、グラースの町を大手を振って歩き回ったそうです。話に聞き入っていた私は、「それで、その先生に会いに行かれた今回の目的はなんだったんですか?」と尋ねました。すると「先生に会いたかっただけよ」と。恐るべし、肥後の女。

帰国後も田中さんはお店でパフューマーに会った話をしながら、心は次にグラースを訪ねることしかなかったそうです。そして次ぎの年、また次ぎの年とグラースとその先生を訪ねる中で、田中さんにはこの先生から「そんなに香りが好きなら、ここで勉強しませんか?」と言われたように聞こえたそうです。
田中さんは、一回目のフランスツアーでコーディネーターをやっていた日本人パフューマーにこの間、何通か手紙を書いていたそうですが、これまで返事が返ってこなかったそうです。ところが、数回目の訪問のとき、偶然にも彼からコンタクトがあったのです。パリに戻った田中さんはそのパフューマーに先ほどの先生とのやり取りを話しました。以来、そのパフューマーとは家族ぐるみのお付き合いだそうです。
熊本に帰った田中さんのもとへ、暫くして彼から連絡が入りました。「来年の2月にこちらに来られますか?入学が許可されることになりましたよ。私が推薦人になっておきましたから」と。そのスクールとは世界的にも有名なグラース市の由緒ある香料会社のラボ(研究室)でした。通常であれば大手化粧品メーカーなどの取引先から、しかも数人しか入学できないラボです。田中さんが断る理由はありませんでした。
それから10年後、田中さんは(有)パフューマークラブを設立。お店もさすがに手狭になり、さらに5年後、新市街に店舗「香りの16区」を移転します。時は1990年。開業から15年目のことでした。ちなみに「16区」とは、「パリの16区」からのインスピレーション。1960-70年代まで、ブルジョワエレガンスがここパリ16区に住む人々の特徴でした。20世紀初頭の建築という視点から言っても一番美しい場所、美しい言葉が残る場所の一つに数えられるといいます。

田中さんは満を持したように、翌年、厚生省から化粧品製造許可を取得し、NHK福岡文化センターでフレグランススクールを開校。更に1993年にはNKK熊本文化センターに同校熊本校を開校、熊本市政策審議懇談会委員、熊本市香りの森建設委員会委員の役職を務められます。
そして、2001年、熊本県から「県の香りマイスター」に任命されます。更に、翌年、厚生省より化粧品輸入許可を取得。続いて臭気判定士協会の理事に就任。そして、同年、フランスパフューマ―(調香師)協会の正会員になられます。今では、東京とグラースにもオフィスを構えておられます。田中さんのグラースへの訪問回数は既に50回以上にも及んでいるそうです。
すっかりグラース通となった田中さんは、かねてからグラース市長にパフューマー養成スクールの開設を打診していました。そして2003年についに、それが「Grasse Institute Perfumery(GIP)」という形で実現することになりました。今では各国からこのスクールへの入校依頼が殺到し、日本人枠が狭められるほどの人気になってしまっているそうです。
田中さんが福岡と熊本で開校したフレグランススクール(パフューマー・香りのスペシャリスト養成スクール)は既に33期生にまで達しています。卒業生の中には世界的に有名な香料会社の香料研究所に入社し活躍している方もいらっしゃいます。
この田中さんが今取り組まれているものには、「香りによる空間演出」、「高齢化社会とアロマコロジーを考える会」、「国際香りと文化の会」などがありますが、詳しくはHPを参照いただくとして、私が最も注目したいのは「九州香りアイランド構想」というプロジェクトです。

九州の恵まれた自然環境では、今でも森林浴、海水浴、太陽浴、温泉浴、花香浴をいたるところで楽しむことができます。これに新たに「芳香浴」をテーマにしたアグリ・レジャーランドを築こうというものです。香りのある植物を植え、それを抽出することによって新しい農業の新しい分野が広がることに貢献したいというものです。
減反政策や後継者の問題で人手の加わらなくなった田畑で季節の花々や香りのある植物を栽培する。「それは、売る花々や植物であってもいいし、グラースのように蒸留施設を作って精油精製をしてもいい。蒸留施設が出来る事によってその地域は豊かな香りの水蒸気で覆われ、アロマテラピー効果を発揮してそこに住む人々を心身ともに癒すことができる。その香りに誘われ、観光客も呼べるかもしれない」と田中さん。
グラースでは土地柄、主食になるような作物をつくることはできません。それだからこそ、かんきつ類などは実、皮、葉、更には種に至るまで抽出する技術を確立しているそうです。そんなグラースを見ているからこそ、田中さんには九州のこの素晴しい環境が野放しになっていることに残念な思いがあります。
例えば、ご当地の香り、四季の香りを香水にすること。田中さんは熊本市からの依頼を受け、
●森の都「森のかたらい」・・・リフレッシュ用
●水の都「川のささやき」・・・リラックス用
●肥後六花「花らんらん」・・・高揚(明るい成分)
という3部作の「くまもとの香り」を創作しています。
また、八代の名産・晩白柚の香りを抽出した香水もあります。これは、(社)熊本県物産振興協会
からH19年度の優良商品金賞を受賞されています。更に、これに晩白柚を使った焼酎、ジャム、石鹸などをセットにすることによって、晩白柚自体の付加価値を高める。そして、八代のあの駅前の臭いのイメージを晩白柚の香りで一掃することができないか?これは私が後付で勝手に妄想したものですが・・・。

2006年11月、今の「香水の16区」にお店を移転し、今では熊本市桜町に香水抽出用のラボも作りました。最後になりますが、田中さんと「香水の16区」に関する一番ホットなニュースは、なんと「東大」「NASA」、そして「紙飛行機」がキーワード。「香り」の無重力、あるいはマッハの世界での影響を研究するプロジェクトにも参加しておられるのです。詳しくは、
(http://www.yamaguchi.net/archives/005142.html)で。
とにかく「動き回るのが好きな」一人の主婦が、自分の居場所、やりがいを求めて駆け抜けた33年間。留まることが嫌いな田中さんの駆け足は、とうとう宇宙科学研究の領域にまで達していました。他にも老人介護、目の不自由な方へのサポート役としての「香り」の可能性の研究などなど田中さんの頭の中にはやりたいことが一杯です。熊本から世界へ、香りの伝道師は今日も駆けずり回ります。
香水専門店「香水の16区」;
〒860-0845 熊本市上通町5-6-1F
TEL:096(325)0418 FAX:096(326)8709
ホームページ;http://www.pluto.dti.ne.jp/~kaori16/
E-mail;kaori16@pluto.dti.ne.jp
営業時間:11:00~20:00休み:無休
2008年03月12日
香りの伝道師、「香水の16区」田中貴子(15)(上)
先日、「パフューム~ある人殺しの物語~」(独、仏、スペイン/2006年)という映画を見ました。「18世紀のパリ、悪臭のたちこめる魚市場で産み落とされたジャン=バティスト・グルヌイユ(ベン・ウィショー)。驚異的な嗅覚を持つがゆえに、奇怪な青年として周囲に疎まれている彼は、ある晩、芳しい香りの少女に夢中になり、誤って殺してしまう。その後、彼は少女の香りを求めて調香師になり、香水作りに没頭するが……」(シネマトゥデイ)というストーリーです。

1万個のバラの花から抽出されるエキス(精油)は、1オンス。1オンスは16分の1ポンドで、約28.35グラム。実にわずかな量です。そして、このエキスの取り出し方に「蒸留法」と「冷浸法」があることを知りました。本作では主人公が、永久に香りを保存する方法としてこの冷浸法を学ぶ事によって起こるサスペンスが伏線となっています。
「香水は、三つの和音からなる」とジャンの師ジュゼッペ・バルディーニ(ダスティン・ホフマン)が語ります。一つは「頭(ヘッド)」で香水の第一印象、次に「心(ハート)」でその香水の主題、最後に「土台(ベース)」で仄かに漂う残り香。この三つにそれぞれ四つの香料の音符がハーモニーを奏でる。こんな話を聞くと、普段香りに無粋な私でさえ首元に一滴忍ばせたくなる、そんな誘惑に駆られます。
この映画の主人公ジャンが、冷浸法の技術習得を求めてパリを旅立ったのがグラース(Grasse)という地でした。グラースは、フランスの南東部に位置する都市で、アルプ=マリティーム県にある人口43,874人の都市。カンヌ(Cannes)から電車で25分。ニース(Nice)から電車で1時間という立地。このグラースになんと、熊本から33年前に旅立った一人の主婦がいました。

前置きが長くなりましたが、15回目のゲストはその「一人の主婦」ご本人で、現在「香水の16区」の代表である田中貴子さんです。田中さんのことはFMKで出演されていた番組を聞き、「すごい人だなぁ」と思っていた矢先に、今度はテレビに出演されているのを見て俄然興味がわきました。公職でのお勤めもあわせて今では知る人ぞ知るという存在の田中さんですが、私はこれまでは存じ上げませんでした。
先月初旬にいきなり上通りにあるお店に飛び込み、ブログの主旨を説明してインタヴューの了解を得、ようやくこの日、お忙しい中時間を割いていただきました。閉店間際の19:30から始めさせてもらいましたが、情熱的な田中さんのお話につい聞き入ってしまい、インタヴューを終えたのは、22:00を回ろうとする時間でした。今回2時間半にわたりお話をいただきましたので、このインタヴューは二回に分けてご紹介していきます。

田中さんは、砥用町(ともち;現在、美里町)のご出身。高校卒業後、18歳で電撃結婚をされ、それから長女、長男と二人の子宝に恵まれ、母親と主婦に徹した毎日を過ごされていました。それが、次男の出産を控えた産婦人科の部屋でベッドから見上げる白い天井を眺めながらふと、「この子が20歳になっている頃、私はいくつなんだろう?私は子供を産むためにだけに生まれきたんだろうか?もし主人が逝ってしまったら、私はこの三人の子供たちを育てて行けるのだろうか?」と考えられたそうです。
「このままじゃいけない気がする」と思い立った田中さんは、いても立ってもいられず出産後5日間で退院します。「何かを始めなければいけない」。しかし、当時、乳飲み子を抱え、社会経験のない田中さんを採用してくれそうな会社は見当たらない。そこで、家庭で受講できる通信教育で資格を取ろうと建築図面のトレースの講座に取り組みますが全くちんぷんかんぷん。次に医療事務の講座にもチャレンジしますが、どうもしっくりこずに挫折。
行き詰った田中さんは、「自分に何ができるんだろう?」と悩み続けます。そこで思いついたのは、「昔から動き回ることが好きだったな」ということ。そして、アルバムをめくりながらこれまでの自分を振り返っていると、小学生のときよく男子に「こん、シャレ(洒落)がー」と言われていたことを思い出しました。「そうだ、お洒落のことなら仕事にできるかも・・・」と思い立ちますが、「洋服屋さん?ダメだ、お金がない。理容師?ダメだ、腕がない」と再び行き詰まり。
思い悩む毎日の中で、田中さんは「まず、外に出よう」と決めます。まずは、書店に。そこで、「10万円でできる商売」という本を見つけます。その本には10万円でアクセサリー販売をするノウハウが書かれていました。「これならできるかも」と考えた田中さんの頭にまず浮かんでいたのは、ビジネスの内容ではなく、「新世界」の地下と6年前に開業していた交通センターという店舗候補地の方でした。
店舗の候補は決めたものの、肝心の開業資金がない田中さんは、まだ暗中模索の中でした。そんなある日、7、8年前に読んだ講談社の「若い女性」という月刊誌に掲載されていた一つの記事のことを思い出しました。その記事には、東京・渋谷で変わった形態の香水のお店をやっていた女性のことが書かれていました。田中さんは講談社にこの記事が掲載された雑誌を購入したいと手紙に書きました。しかし、講談社からの返事は待てど暮らせどありませんでした。

(「若い女性」1970年7月号表紙)
何しろ7、8年前のことでもあり、仕方ないかと思う気持ちもありましたが、ダメもとで今度はハガキを書いて送ったところ、数日後にその記事を書いた講談社の担当者から電話があったのです。「その方は、今でもその仕事をされています。私から連絡をしておきますので、一度尋ねてみられてはどうですか?」と。この朗報に喜んだ田中さんは数日後、日帰りの予定で乳飲み子を親戚に預け、東京に飛んでいました。「次男の出産が5月だったから、あれは7月か8月頃だったかな」と。大胆です。
修学旅行以来、二度目の東京。渋谷にあるその会社を10時に尋ねた田中さんに、その女性経営者からかけられた言葉は、「これから仕事で出かけるので夜8時まで待てる?」と。日帰り予定の田中さんは一瞬戸惑いましたが、ここまで来て引き下がるわけにはいきませんでした。約束の時間に再訪した田中さんにその女性経営者から次にかけられたのは、「実は、あなたがいらっしゃることは聞いていました。そこで、どうやってお断りしようかと考えていました」という言葉でした。
その理由を尋ねると、雑誌掲載以来、既に100名以上の人が彼女のもとを訪れたそうですが、成功した人は一人もいないのだということでした。それでも田中さんには彼女に頼るしか道が開けないことがわかっていました。香水の販売をするにあたって事前に県の薬務課やJETROに問い合わせたところ、個人では香水を輸入することができなかったのでした。(彼女から仕入れるしかない)
「資金は?」と問われた田中さんは、思わず「50万円あります」と言ってしまいました。しかし女性経営者から返ってきたのは、「その3倍はかかりますよ」。更に、「50cm四方の固定したスペース」の確保が条件であると伝えられます。田中さんの手持ち資金は、結婚前にご両親からもらった10万円きり。しかもここまでの話は、ご主人には内緒で進めていること。相談などできませんでした。
今でさえ難しい話だと思いますし、当時の田中さんの立場であれば、普通ならここで断念するケースだと思います。しかし、「20年後の仮説」を前に動き始めた田中さんの脳裏には、「やるしかない」という気持ちしかありませんでした。帰熊後、独力で一年をかけてこの開業資金を作りました。後は、実際の店舗をどう手に入れるかの段階に入ることになりました。しかし、未だご主人には内緒の隠密行動でした。
当時交通センターは、伊勢丹の進出で二階をリニューアルすることになっていました。ここが田中さんの狙いです。田中さんはテナント入居交渉に背水の陣で臨みますが、田中さんが要求する「一坪」に担当者は目を丸くしたといいます。呆れて、です。しかし、田中さんの熱意に押された担当者は、最終的に田中さんにエスカレーター下の三角形の空きスペースを提供することになります。リニューアルオープンは11月でした。
そんなある日、家庭で良き妻、良き母を通していた田中さんは、義母様が経営されていたアパートの掃除も律儀にこなしていました。しかし、草むしりやその掃除が原因で、皮膚が荒れ、顔には黄疸が出てくるほどの状態にまで悪化してしまったのです。国立病院に行くと、病名は急性肝炎、即入院の診断を受けます。しかし、翌日にはオープンに向けての契約が待っていました。
「あー、運に見放されたな」と思った田中さんは、悲愴になった心と外見を思いっきりの化粧で隠し、交通センターとの契約に臨みます。すると、運は田中さんを見捨ててはいませんでした。担当者から聞かされたのは、「11月のリニューアルオープン予定が、3月に延びました」という言葉でした。
運を再度掴んだ田中さんにとって、開業準備に入ろうとしている今ここで入院するわけにはいきませんでした。なんと自宅を急場で子供たちと隔離できるように改築して、これで当面を凌ぐことにします。凄い発想です。じっと我慢の一週間。すると、検査後の数値が快復に向かっていることを示していました。「苔の一念 岩をも通す」ということでしょうか?
それでも田中さんは、仮設「隔離施設」で丸まる二ヶ月間の寝たきりの生活を余儀なくされます。当然、開店の準備は進みません。そしてまた、契約日が迫ってきました。そこへ再び神風が。「3月の予定が6月に延びました」。(今なら、田中さんは「ドンダケーッ」と言っているに違いありません)普通の開業準備中のテナントなら一日も早いオープンを望み、むしろこの七ヶ月の延期が死活問題になることもあるでしょうに、田中さんにとっては終始フォローウィンドーでした。
急性肝炎を取り合えずも乗り切った田中さんは、ついに4月、念願の交通センターとのテナント契約を交わすことになりますが、その前に田中さんが超えねばならない最大の難関が待っていました。それは、契約書の保証人になってもらう筈のご主人へ、「2ヵ月後」に交通センターで香水のお店を開店すること伝え、了解を得ることです。「寝耳に水」とは、まさにこのときのご主人の状態を指す言葉でした。
この説得ですべてが上手くいった訳ではありませんでしたが、一人の主婦は開業へのGOサインを手にしました。オープンから突発的に発生する細かな問題を解決しながら、ビジネスは概ね順調に進んでいきました。熊本の一人の主婦が「香りの伝道師」に生まれ変わろうとしていました。(続く)

1万個のバラの花から抽出されるエキス(精油)は、1オンス。1オンスは16分の1ポンドで、約28.35グラム。実にわずかな量です。そして、このエキスの取り出し方に「蒸留法」と「冷浸法」があることを知りました。本作では主人公が、永久に香りを保存する方法としてこの冷浸法を学ぶ事によって起こるサスペンスが伏線となっています。
「香水は、三つの和音からなる」とジャンの師ジュゼッペ・バルディーニ(ダスティン・ホフマン)が語ります。一つは「頭(ヘッド)」で香水の第一印象、次に「心(ハート)」でその香水の主題、最後に「土台(ベース)」で仄かに漂う残り香。この三つにそれぞれ四つの香料の音符がハーモニーを奏でる。こんな話を聞くと、普段香りに無粋な私でさえ首元に一滴忍ばせたくなる、そんな誘惑に駆られます。
この映画の主人公ジャンが、冷浸法の技術習得を求めてパリを旅立ったのがグラース(Grasse)という地でした。グラースは、フランスの南東部に位置する都市で、アルプ=マリティーム県にある人口43,874人の都市。カンヌ(Cannes)から電車で25分。ニース(Nice)から電車で1時間という立地。このグラースになんと、熊本から33年前に旅立った一人の主婦がいました。

前置きが長くなりましたが、15回目のゲストはその「一人の主婦」ご本人で、現在「香水の16区」の代表である田中貴子さんです。田中さんのことはFMKで出演されていた番組を聞き、「すごい人だなぁ」と思っていた矢先に、今度はテレビに出演されているのを見て俄然興味がわきました。公職でのお勤めもあわせて今では知る人ぞ知るという存在の田中さんですが、私はこれまでは存じ上げませんでした。
先月初旬にいきなり上通りにあるお店に飛び込み、ブログの主旨を説明してインタヴューの了解を得、ようやくこの日、お忙しい中時間を割いていただきました。閉店間際の19:30から始めさせてもらいましたが、情熱的な田中さんのお話につい聞き入ってしまい、インタヴューを終えたのは、22:00を回ろうとする時間でした。今回2時間半にわたりお話をいただきましたので、このインタヴューは二回に分けてご紹介していきます。

田中さんは、砥用町(ともち;現在、美里町)のご出身。高校卒業後、18歳で電撃結婚をされ、それから長女、長男と二人の子宝に恵まれ、母親と主婦に徹した毎日を過ごされていました。それが、次男の出産を控えた産婦人科の部屋でベッドから見上げる白い天井を眺めながらふと、「この子が20歳になっている頃、私はいくつなんだろう?私は子供を産むためにだけに生まれきたんだろうか?もし主人が逝ってしまったら、私はこの三人の子供たちを育てて行けるのだろうか?」と考えられたそうです。
「このままじゃいけない気がする」と思い立った田中さんは、いても立ってもいられず出産後5日間で退院します。「何かを始めなければいけない」。しかし、当時、乳飲み子を抱え、社会経験のない田中さんを採用してくれそうな会社は見当たらない。そこで、家庭で受講できる通信教育で資格を取ろうと建築図面のトレースの講座に取り組みますが全くちんぷんかんぷん。次に医療事務の講座にもチャレンジしますが、どうもしっくりこずに挫折。
行き詰った田中さんは、「自分に何ができるんだろう?」と悩み続けます。そこで思いついたのは、「昔から動き回ることが好きだったな」ということ。そして、アルバムをめくりながらこれまでの自分を振り返っていると、小学生のときよく男子に「こん、シャレ(洒落)がー」と言われていたことを思い出しました。「そうだ、お洒落のことなら仕事にできるかも・・・」と思い立ちますが、「洋服屋さん?ダメだ、お金がない。理容師?ダメだ、腕がない」と再び行き詰まり。
思い悩む毎日の中で、田中さんは「まず、外に出よう」と決めます。まずは、書店に。そこで、「10万円でできる商売」という本を見つけます。その本には10万円でアクセサリー販売をするノウハウが書かれていました。「これならできるかも」と考えた田中さんの頭にまず浮かんでいたのは、ビジネスの内容ではなく、「新世界」の地下と6年前に開業していた交通センターという店舗候補地の方でした。
店舗の候補は決めたものの、肝心の開業資金がない田中さんは、まだ暗中模索の中でした。そんなある日、7、8年前に読んだ講談社の「若い女性」という月刊誌に掲載されていた一つの記事のことを思い出しました。その記事には、東京・渋谷で変わった形態の香水のお店をやっていた女性のことが書かれていました。田中さんは講談社にこの記事が掲載された雑誌を購入したいと手紙に書きました。しかし、講談社からの返事は待てど暮らせどありませんでした。

(「若い女性」1970年7月号表紙)
何しろ7、8年前のことでもあり、仕方ないかと思う気持ちもありましたが、ダメもとで今度はハガキを書いて送ったところ、数日後にその記事を書いた講談社の担当者から電話があったのです。「その方は、今でもその仕事をされています。私から連絡をしておきますので、一度尋ねてみられてはどうですか?」と。この朗報に喜んだ田中さんは数日後、日帰りの予定で乳飲み子を親戚に預け、東京に飛んでいました。「次男の出産が5月だったから、あれは7月か8月頃だったかな」と。大胆です。
修学旅行以来、二度目の東京。渋谷にあるその会社を10時に尋ねた田中さんに、その女性経営者からかけられた言葉は、「これから仕事で出かけるので夜8時まで待てる?」と。日帰り予定の田中さんは一瞬戸惑いましたが、ここまで来て引き下がるわけにはいきませんでした。約束の時間に再訪した田中さんにその女性経営者から次にかけられたのは、「実は、あなたがいらっしゃることは聞いていました。そこで、どうやってお断りしようかと考えていました」という言葉でした。
その理由を尋ねると、雑誌掲載以来、既に100名以上の人が彼女のもとを訪れたそうですが、成功した人は一人もいないのだということでした。それでも田中さんには彼女に頼るしか道が開けないことがわかっていました。香水の販売をするにあたって事前に県の薬務課やJETROに問い合わせたところ、個人では香水を輸入することができなかったのでした。(彼女から仕入れるしかない)
「資金は?」と問われた田中さんは、思わず「50万円あります」と言ってしまいました。しかし女性経営者から返ってきたのは、「その3倍はかかりますよ」。更に、「50cm四方の固定したスペース」の確保が条件であると伝えられます。田中さんの手持ち資金は、結婚前にご両親からもらった10万円きり。しかもここまでの話は、ご主人には内緒で進めていること。相談などできませんでした。
今でさえ難しい話だと思いますし、当時の田中さんの立場であれば、普通ならここで断念するケースだと思います。しかし、「20年後の仮説」を前に動き始めた田中さんの脳裏には、「やるしかない」という気持ちしかありませんでした。帰熊後、独力で一年をかけてこの開業資金を作りました。後は、実際の店舗をどう手に入れるかの段階に入ることになりました。しかし、未だご主人には内緒の隠密行動でした。
当時交通センターは、伊勢丹の進出で二階をリニューアルすることになっていました。ここが田中さんの狙いです。田中さんはテナント入居交渉に背水の陣で臨みますが、田中さんが要求する「一坪」に担当者は目を丸くしたといいます。呆れて、です。しかし、田中さんの熱意に押された担当者は、最終的に田中さんにエスカレーター下の三角形の空きスペースを提供することになります。リニューアルオープンは11月でした。
そんなある日、家庭で良き妻、良き母を通していた田中さんは、義母様が経営されていたアパートの掃除も律儀にこなしていました。しかし、草むしりやその掃除が原因で、皮膚が荒れ、顔には黄疸が出てくるほどの状態にまで悪化してしまったのです。国立病院に行くと、病名は急性肝炎、即入院の診断を受けます。しかし、翌日にはオープンに向けての契約が待っていました。
「あー、運に見放されたな」と思った田中さんは、悲愴になった心と外見を思いっきりの化粧で隠し、交通センターとの契約に臨みます。すると、運は田中さんを見捨ててはいませんでした。担当者から聞かされたのは、「11月のリニューアルオープン予定が、3月に延びました」という言葉でした。
運を再度掴んだ田中さんにとって、開業準備に入ろうとしている今ここで入院するわけにはいきませんでした。なんと自宅を急場で子供たちと隔離できるように改築して、これで当面を凌ぐことにします。凄い発想です。じっと我慢の一週間。すると、検査後の数値が快復に向かっていることを示していました。「苔の一念 岩をも通す」ということでしょうか?
それでも田中さんは、仮設「隔離施設」で丸まる二ヶ月間の寝たきりの生活を余儀なくされます。当然、開店の準備は進みません。そしてまた、契約日が迫ってきました。そこへ再び神風が。「3月の予定が6月に延びました」。(今なら、田中さんは「ドンダケーッ」と言っているに違いありません)普通の開業準備中のテナントなら一日も早いオープンを望み、むしろこの七ヶ月の延期が死活問題になることもあるでしょうに、田中さんにとっては終始フォローウィンドーでした。
急性肝炎を取り合えずも乗り切った田中さんは、ついに4月、念願の交通センターとのテナント契約を交わすことになりますが、その前に田中さんが超えねばならない最大の難関が待っていました。それは、契約書の保証人になってもらう筈のご主人へ、「2ヵ月後」に交通センターで香水のお店を開店すること伝え、了解を得ることです。「寝耳に水」とは、まさにこのときのご主人の状態を指す言葉でした。
この説得ですべてが上手くいった訳ではありませんでしたが、一人の主婦は開業へのGOサインを手にしました。オープンから突発的に発生する細かな問題を解決しながら、ビジネスは概ね順調に進んでいきました。熊本の一人の主婦が「香りの伝道師」に生まれ変わろうとしていました。(続く)
2008年03月07日
生産から販売への転進、熊本産直センター・広瀬生夫(14)
14回目のゲストは、(有)熊本産直センター、代表取締役・広瀬生夫さん(59)。広瀬さんとのご縁は、先月20日に行われた某セミナー後の交流懇談会でご挨拶させていただいたことからでした。熊本県の特産品であるスイカ、メロン他季節の果物やお米、馬刺しに至るまでの店舗販売とインターネットを利用したオンラインショップで開店されて以来、右肩上がりの成長を遂げられています。
セミナー終了後の講師への質問タイムに、広瀬さんは「付加価値のつけ方」について質問なさっていました。講師の方のお答えが、「ちょっと的を射ていないなと」思った私は、僭越ながら個人的な意見を後日メールで送信させていただいても構わないかと打診してみました。広瀬さんからはなんの躊躇もなく「どんどんお聞きしたい」というお応え。ここで私は、広瀬さんの「器」に関心を持ちました。

広瀬さんのお店は植木町役場に近い国道3号線沿いにあります。熊本市内からも10Km程の距離。お昼前の1時間をいただき、半ば強引にインタヴューさせていただきました。事務所にお邪魔すると、ボア襟付きの革ジャンにジーンズという、そのままハーレーかなんかに乗って出かけてもおかしくないいでたちで、お客様と商談のお電話中でした。
広瀬さんは山鹿市鹿央町のご出身。今年還暦をお迎えになるそうですが、とてもそんな風には見えません。実家は何代も続く大きな農家の長男としてお生まれになっています。熊本農業高校を卒業とともに農業一筋に27年間、スイカ、メロン、米を作り続けてこられました。そして24年目のあるとき、自分が作った作物が産地ではなく、そのまま県外に流れて行くこと、消費者の顔が見えないことに疑問を抱くようになります。
「自分でつくったものを自分で消費者に直接届けたくなったんです」と思い立った広瀬さんは、トラックに100個のスイカを積み込み、路面販売を試みたのでした。今では見かけることの多い販売形式ですが、当時は誰もそんなことはやっていません。加えて、事前に周辺地域にオリコミ広告を1000部入れ、販売時には手書きの看板(POP)を準備してのチャレンジ。結果は予想以上の反応でした。
ここで消費者との直接のコンタクトに手ごたえを得た広瀬さんは、翌年奇抜な発想でスイカの販売にチャレンジします。それは「冬のスイカ」。クリスマスに向けて夏の風物詩を売るという逆転の発想でした。狙いは見事に的中し、大きな成功を得ました。ここにも広瀬さんのしかけがありました。熊日新聞にこの「冬のスイカ」の有料パブリシティ広告を打っていたのです。これによって、広告の力を実感されたそうです。
生産者としての商品に対するゆるぎない自信と、これをどうにかして消費者に届けたいという熱意、販売者の論理ではなく、あくまでも生産者の論理を貫き通す思いが受け入れられない筈はありませんね。そして、翌年。広瀬さんは新たなチャレンジに挑むのです。それは店舗販売へのチャレンジ。適当な場所を捜し歩いて見つけたのが、現在の3号線沿いに立つこの店舗がその場所でした。ここに「広瀬スイカ園」と名づけました。
 この場所は元々自動車整備工場だったそうですが、それが空き家になっていたのです。広瀬さんは地主さんから三ヶ月の期限付きで借り受けることにしました。当時は近隣に同業が12店舗もあったにも関わらず、です。しかし、この競争厳しい商圏の中にあっても広瀬さんのお得意のマーケティング戦略が功を奏します。それはDMでした。これまでで掴んだ消費者とのコンタクトをしっかりここで花開かせたのです。この三ヶ月間での売上は、これまでの農業収入を上回るものでした。
この場所は元々自動車整備工場だったそうですが、それが空き家になっていたのです。広瀬さんは地主さんから三ヶ月の期限付きで借り受けることにしました。当時は近隣に同業が12店舗もあったにも関わらず、です。しかし、この競争厳しい商圏の中にあっても広瀬さんのお得意のマーケティング戦略が功を奏します。それはDMでした。これまでで掴んだ消費者とのコンタクトをしっかりここで花開かせたのです。この三ヶ月間での売上は、これまでの農業収入を上回るものでした。
この三年間の地道なリサーチを経て、広瀬さんは27年間続けてきた生産者から販売者への転進を決意します。広瀬さん、46歳の起業です。長男であった広瀬さんの決意に、ご両親は全く反対されなかったそうです。
三ヶ月間の期限だった店舗販売が今年で14年目に入りました。驚くのは、果物の販売事業で9年目に1億円の売上に達したことに加え、この14年間右肩上がりの成長が続いていることです。バブル崩壊後の出店とは言え、ずっと右肩上がりで成長するには何か秘策がなければなかなかできることではありません。その秘訣を広瀬さんにうかがいました。
「別に特別なことはしていません。これまでやって良かったことを、次やるときに更に良くしてきたことです。そしてお客様の要望をよくお聞きし、その要望に応えることです」と、さらっと答えられました。ナルホド。「お客様に間違いのないものを提供しています。競合店のことは意識したことがありません。ただお客様に喜ばれるにはどうしたらいいのか、それだけです」。
今ではオンラインショップも好調で、同社のお客様は全国で5万9千名に。昨年は12月にメロンの注文が殺到したそうです。4名の社員の方に企画を任せたところ、それぞれの企画が見事に当たったのです。
 ここまでお話を聞いてきて広瀬さんのお話には、経営につきものの苦境がありません。あえて聞いてみると、「人間、本気になったらなんでもできるんです。私は物事を一切否定しませんし、プラス志向に徹しているだけです」と。「広瀬さんには幸運の女神がついているようですね」と私が言うと、「幸運の女神は誰にでもついていますよ。ただ、この女神が見えない人が少なくないでしょうね。私にはしっかり見えていますよ」と笑って答えられました。
ここまでお話を聞いてきて広瀬さんのお話には、経営につきものの苦境がありません。あえて聞いてみると、「人間、本気になったらなんでもできるんです。私は物事を一切否定しませんし、プラス志向に徹しているだけです」と。「広瀬さんには幸運の女神がついているようですね」と私が言うと、「幸運の女神は誰にでもついていますよ。ただ、この女神が見えない人が少なくないでしょうね。私にはしっかり見えていますよ」と笑って答えられました。
最後に若い起業家へのメッセージをお願いしました。「熱意は誰もが持っているんですね。大切なのは取り組む姿勢です。それにどんな経験でも積んでおくこと。そのときは何の足しにもならないと思う経験でも、それはそれで自分の中の引き出しに納まって行くんです。そしてある日、その引き出しが必要になるときが必ずやってきますよ」。
先日、広瀬さんは出身校の熊本農業高校で「出前授業」を行ったそうです。今年で3年目になるとか。その授業で使われたペーパーの中に(有)熊本産直センターの企業理念が書かれていました。
★(有)熊本産直センター(以下、KSC)は、お客様への品質の良いおいしい新鮮なものを、早く提供することで、満足と喜びを感じて頂くように、日々新た、まごころから最善を尽くして努力精進します。
★KSCは、常に視野を広げ、耳を澄まし時代の進化を柔軟かつ敏感にキャッチして時流に乗って進みます。
★KSCは、消費者の皆様だけでなく、生産者、流通業者、社員他KSCの業務に関わって頂くすべての人々に感謝の念を抱き、皆が善くなるようにという思いで行動します。
★KSCは、常にスピードを意識して、サービスと商品のブランド化に邁進します。
どれも、広瀬さんのお人柄をそのまま映したような理念だと思います。中でも三つ目の理念が、私が冒頭で感じた「器」なんだと感じました。そして、二枚目のペーパーに書かれていたのが、エマーソン語録でした。広瀬さんがこのアメリカの思想家に出会ったのは高校生の頃だったそうです。詳しくはお聞きしませんでしたが、農家の長男として家業を継ぐ決心をした高校時代の広瀬さんの思いを垣間見たような気がしました。
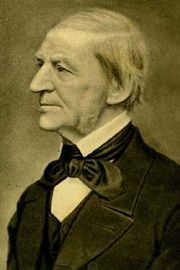
ラルフ・ワルド・エマーソン(Ralph Waldo Emerson、1803年5月25日-1882年4月27日)は、アメリカ合衆国の思想家、哲学者、作家、詩人、エッセイスト。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンに生まれる。18歳でハーバード大学を卒業し21歳までボストンで教鞭をとる。その後ハーバード神学校に入学し、伝道資格を取得し、牧師になる。
(有)熊本産直センター
〒861-0132
鹿本郡植木町植木115-1
TEL;096-273-4888(代)、FAX;096-273-4830
E-mail;hirose@crocus.ocn.ne.jp
ホームページ;http://www.kudamono39.net/
セミナー終了後の講師への質問タイムに、広瀬さんは「付加価値のつけ方」について質問なさっていました。講師の方のお答えが、「ちょっと的を射ていないなと」思った私は、僭越ながら個人的な意見を後日メールで送信させていただいても構わないかと打診してみました。広瀬さんからはなんの躊躇もなく「どんどんお聞きしたい」というお応え。ここで私は、広瀬さんの「器」に関心を持ちました。

広瀬さんのお店は植木町役場に近い国道3号線沿いにあります。熊本市内からも10Km程の距離。お昼前の1時間をいただき、半ば強引にインタヴューさせていただきました。事務所にお邪魔すると、ボア襟付きの革ジャンにジーンズという、そのままハーレーかなんかに乗って出かけてもおかしくないいでたちで、お客様と商談のお電話中でした。
広瀬さんは山鹿市鹿央町のご出身。今年還暦をお迎えになるそうですが、とてもそんな風には見えません。実家は何代も続く大きな農家の長男としてお生まれになっています。熊本農業高校を卒業とともに農業一筋に27年間、スイカ、メロン、米を作り続けてこられました。そして24年目のあるとき、自分が作った作物が産地ではなく、そのまま県外に流れて行くこと、消費者の顔が見えないことに疑問を抱くようになります。
「自分でつくったものを自分で消費者に直接届けたくなったんです」と思い立った広瀬さんは、トラックに100個のスイカを積み込み、路面販売を試みたのでした。今では見かけることの多い販売形式ですが、当時は誰もそんなことはやっていません。加えて、事前に周辺地域にオリコミ広告を1000部入れ、販売時には手書きの看板(POP)を準備してのチャレンジ。結果は予想以上の反応でした。
ここで消費者との直接のコンタクトに手ごたえを得た広瀬さんは、翌年奇抜な発想でスイカの販売にチャレンジします。それは「冬のスイカ」。クリスマスに向けて夏の風物詩を売るという逆転の発想でした。狙いは見事に的中し、大きな成功を得ました。ここにも広瀬さんのしかけがありました。熊日新聞にこの「冬のスイカ」の有料パブリシティ広告を打っていたのです。これによって、広告の力を実感されたそうです。
生産者としての商品に対するゆるぎない自信と、これをどうにかして消費者に届けたいという熱意、販売者の論理ではなく、あくまでも生産者の論理を貫き通す思いが受け入れられない筈はありませんね。そして、翌年。広瀬さんは新たなチャレンジに挑むのです。それは店舗販売へのチャレンジ。適当な場所を捜し歩いて見つけたのが、現在の3号線沿いに立つこの店舗がその場所でした。ここに「広瀬スイカ園」と名づけました。
 この場所は元々自動車整備工場だったそうですが、それが空き家になっていたのです。広瀬さんは地主さんから三ヶ月の期限付きで借り受けることにしました。当時は近隣に同業が12店舗もあったにも関わらず、です。しかし、この競争厳しい商圏の中にあっても広瀬さんのお得意のマーケティング戦略が功を奏します。それはDMでした。これまでで掴んだ消費者とのコンタクトをしっかりここで花開かせたのです。この三ヶ月間での売上は、これまでの農業収入を上回るものでした。
この場所は元々自動車整備工場だったそうですが、それが空き家になっていたのです。広瀬さんは地主さんから三ヶ月の期限付きで借り受けることにしました。当時は近隣に同業が12店舗もあったにも関わらず、です。しかし、この競争厳しい商圏の中にあっても広瀬さんのお得意のマーケティング戦略が功を奏します。それはDMでした。これまでで掴んだ消費者とのコンタクトをしっかりここで花開かせたのです。この三ヶ月間での売上は、これまでの農業収入を上回るものでした。この三年間の地道なリサーチを経て、広瀬さんは27年間続けてきた生産者から販売者への転進を決意します。広瀬さん、46歳の起業です。長男であった広瀬さんの決意に、ご両親は全く反対されなかったそうです。
三ヶ月間の期限だった店舗販売が今年で14年目に入りました。驚くのは、果物の販売事業で9年目に1億円の売上に達したことに加え、この14年間右肩上がりの成長が続いていることです。バブル崩壊後の出店とは言え、ずっと右肩上がりで成長するには何か秘策がなければなかなかできることではありません。その秘訣を広瀬さんにうかがいました。
「別に特別なことはしていません。これまでやって良かったことを、次やるときに更に良くしてきたことです。そしてお客様の要望をよくお聞きし、その要望に応えることです」と、さらっと答えられました。ナルホド。「お客様に間違いのないものを提供しています。競合店のことは意識したことがありません。ただお客様に喜ばれるにはどうしたらいいのか、それだけです」。
今ではオンラインショップも好調で、同社のお客様は全国で5万9千名に。昨年は12月にメロンの注文が殺到したそうです。4名の社員の方に企画を任せたところ、それぞれの企画が見事に当たったのです。
 ここまでお話を聞いてきて広瀬さんのお話には、経営につきものの苦境がありません。あえて聞いてみると、「人間、本気になったらなんでもできるんです。私は物事を一切否定しませんし、プラス志向に徹しているだけです」と。「広瀬さんには幸運の女神がついているようですね」と私が言うと、「幸運の女神は誰にでもついていますよ。ただ、この女神が見えない人が少なくないでしょうね。私にはしっかり見えていますよ」と笑って答えられました。
ここまでお話を聞いてきて広瀬さんのお話には、経営につきものの苦境がありません。あえて聞いてみると、「人間、本気になったらなんでもできるんです。私は物事を一切否定しませんし、プラス志向に徹しているだけです」と。「広瀬さんには幸運の女神がついているようですね」と私が言うと、「幸運の女神は誰にでもついていますよ。ただ、この女神が見えない人が少なくないでしょうね。私にはしっかり見えていますよ」と笑って答えられました。最後に若い起業家へのメッセージをお願いしました。「熱意は誰もが持っているんですね。大切なのは取り組む姿勢です。それにどんな経験でも積んでおくこと。そのときは何の足しにもならないと思う経験でも、それはそれで自分の中の引き出しに納まって行くんです。そしてある日、その引き出しが必要になるときが必ずやってきますよ」。
先日、広瀬さんは出身校の熊本農業高校で「出前授業」を行ったそうです。今年で3年目になるとか。その授業で使われたペーパーの中に(有)熊本産直センターの企業理念が書かれていました。
★(有)熊本産直センター(以下、KSC)は、お客様への品質の良いおいしい新鮮なものを、早く提供することで、満足と喜びを感じて頂くように、日々新た、まごころから最善を尽くして努力精進します。
★KSCは、常に視野を広げ、耳を澄まし時代の進化を柔軟かつ敏感にキャッチして時流に乗って進みます。
★KSCは、消費者の皆様だけでなく、生産者、流通業者、社員他KSCの業務に関わって頂くすべての人々に感謝の念を抱き、皆が善くなるようにという思いで行動します。
★KSCは、常にスピードを意識して、サービスと商品のブランド化に邁進します。
どれも、広瀬さんのお人柄をそのまま映したような理念だと思います。中でも三つ目の理念が、私が冒頭で感じた「器」なんだと感じました。そして、二枚目のペーパーに書かれていたのが、エマーソン語録でした。広瀬さんがこのアメリカの思想家に出会ったのは高校生の頃だったそうです。詳しくはお聞きしませんでしたが、農家の長男として家業を継ぐ決心をした高校時代の広瀬さんの思いを垣間見たような気がしました。
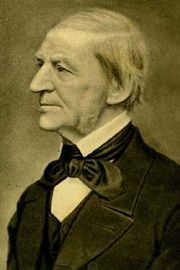
ラルフ・ワルド・エマーソン(Ralph Waldo Emerson、1803年5月25日-1882年4月27日)は、アメリカ合衆国の思想家、哲学者、作家、詩人、エッセイスト。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンに生まれる。18歳でハーバード大学を卒業し21歳までボストンで教鞭をとる。その後ハーバード神学校に入学し、伝道資格を取得し、牧師になる。
(有)熊本産直センター
〒861-0132
鹿本郡植木町植木115-1
TEL;096-273-4888(代)、FAX;096-273-4830
E-mail;hirose@crocus.ocn.ne.jp
ホームページ;http://www.kudamono39.net/
2008年03月02日
お客様のドレス必ず探します、「KINA」代表土本宏子(13)
13回目のゲストは、「アメブロ」で互いに読者であるドレスショップ「KINA」のオーナー・土本宏子さん(24)。彼女は21歳でドレスの訪問販売を始めて、二年目の昨年6月にオンラインSHOPをオープン、続いて翌月の7月にはリアル店舗「KINA」を下通りの光琳寺通り沿いに出店しました。今月の20日に24歳になったばかりの土本さんに対する私の興味は、彼女がビジネスを訪問販売、出張販売から始めたという点にありました。15:00開店前の1時間をいただき、このうら若きドレスショップ・オーナーに話をうかがいました。

いきなり余談ですが、私が約束の10分前にショップの前を通りかかったときに、なんと一軒手前の隣のビルの隙間から黒煙が立ち始めているではありませんか。そこに置かれた建築材のボードから出火していたのです。気づいたときには、近隣のお店から慌てて出てこられた女性から消火器を受け取り、消火活動をしていました。出火の原因は定かではありません。
短い消火活動を終えた私は、約束の時間に「KINA」に到着。ワインレッドの絨毯とブラックの内装の店内にはドレスやスーツが所狭しと並んでいます。そこに土本さんと店長の池田晴美さんがいらっしゃいました。挨拶もそこそこに、まず、「KINA」というネーミングについてうかがうと、彼女の愛犬(オスのパグ)の名前をつけたそうです。毛が黄色だったことから「キナ」。この「キナ」は彼女のブログでも度々登場していました。
彼女がこの「KINA」を始めたきっかけは、三年前にとあるテレビ番組でキャバクラ女性の24時間を追ったルポルタージュを見たことでした。その中で登場したある男性が、新宿で女性たちにドレスを訪問販売している模様があって、彼女にインスピレーションをもたらしました。「これなら、私でもできるかも」→「これ、私ならできるな」→「これをやろう」と瞬時に決断したそうです。(外では消防車のサイレンの音が聞こえていました・・・)
土本さんは中高時代に、自分が団体行動で生活することに違和感を持っていました。思い悩んだ末、彼女はご両親に相談して高校中退の道を選び、社会に出ることを決めます。居酒屋のアルバイトから始め、18歳になったときにキャバクラ、そしてクラブの世界へ。そのときには三つの仕事を掛け持ちでこなしていたといいます。土本さんにとっては忙しい仕事も、「世の中にはこんなにいろんな仕事があるんだ」という好奇心が先立ちました。しかもこの三年間で仕事をしながら、彼女は通信教育で高校卒業の資格も取得しています。
自分が夜の仕事で着用していたことからドレスの訪販を決意したものの、アパレル業界の知識、販売経験のない彼女は、これまでのつてを頼ったり、ネットで熊本や全国に仕入先を求めますが、既存のドレスショップとのバッティングなどで仕入れさせてくれるメーカーがなかなか見つかりませんでした。そんな中、土本さんに「韓国なら安く仕入れられる」という情報が飛び込んできました。暗中模索中の彼女はあれこれ考えるよりも先に、まず友人と韓国に飛んでいました。なぜか、釜山(プサン)へ。
「韓国のこと、何も知らなかったんです。韓国なら釜山だと思って行きました」と。結構大胆です。「当然韓国語も喋れないので、釜山で日本語を話せる人を探して友達になって、ドレスの仕入先を教えてもらったんです。そうしたら、それならソウルに行きなさいって言われたんですね」。土本さんは、その「友達」から韓国で有名なメーカーの情報を得て、いったん帰国後、今度は一人でソウルに向かいます。
釜山のときと同じように、初めてのソウルでも日本語の喋れる韓国人を探して、そのお目当ての仕入先に行き着いた彼女が仕入れたドレスは50着。このドレスをもとに、いよいよ移動販売「KINA」の第一歩がスタートします。実際販売してみると、サイズの違いなどがあっていくつか問題点があることがわかってきました。仕入先との何度かのやり取りを通じて、いつしか先方にカット、縫製を指示できるようにまでなっていました。
訪問販売先は紹介先から紹介先へと広がり、県内で契約店は30店舗に達しました。九州各地の訪問先へもその流れで鹿児島、宮崎、大分と広がっていきました。私が不意に「他県へ出張されるときにはどんなホテルに泊まるんですか?」とお聞きしたところ、「いえいえ、そんな勿体ないことはできません。すべて日帰りです。一度に100着ほど持って行くんですが、はじめはすべて一人でやりました。お客様の仕事柄、朝の4時から販売開始なんてこともあります。今は出張先に搬入などお手伝いしてくれるスタッフがいるので、多少は楽になりました」と。かなりパワフルです。
熊本を中心に九州各地で実績を積んでいく土本さんの姿がいつしか業界関係者の間で噂になり、日本のメーカーからも声がかかるようになります。今ではメーカーサイドから営業に来るほどになっているそうです。街を歩いていると今でもキャバクラからスカウトされたりするそうですが、土本さんは逆に営業をかけることもしばしばあるそうです。まだ電話でしか話したことのない仕入先の社長さんからもブログを見て、「全国的に見ても一番若いオーナーだ。頑張れ」と言われましたという程の活躍ぶりです。

そして、昨年のオンラインSHOPとリアル店舗「KINA」のオープン。「最初は、外販一本でやっていくつもりでした。お店を出すなんて全く考えていませんでした」と語る土本さん。「外販を続けているうちに、どうしても外販に行けないお客様がいらしたり、周りから店を出したらいいじゃないかとか、君ならできるよなんて言ってくれる方々がいて、じゃ、やってみようと思うようになったんです」。
出店資金は、昨年の5月に国民金融公庫からの融資を取り付けました。「自分で事業計画も作りました。最終的には税理士さんの助言を受けながらですけど・・・」と、立派な事業家です。オープンのときは、数多くのスタンド花が寄せられ、ショップのある3階から1階までの階段で納まりきれずに、光琳寺通りにまで並ぶほどだったそうです。取り扱い商品は、今では国内メーカーのものになっているそうです。なかでも、㈱HOT CLOTHING社の「R」、「WPC(WAY PAST COOL)」などは、仕入元と「KINA」の完全独占販売。
土本さんのモットーは、「お客様にあったドレスは必ず探し出します」ということ。「今の若い女性は細い人が多いんですよ。私よりもふたまわり位細いんです。そんなお客様にもピッタリのドレスや、逆に私よりふたまわり位大きいサイズのドレスなど、他所ではなかなか見つけられないものでも、私たちは必ず準備する自信があります」と、この点だけはやけに力が入っていました。さすがにオーナーです。
ちなみに土本さんは170cmの長身。しかもヒールを履いているので180cmには達していて、私には充分スリムに見えますし、サイズはM(9号)だそうです。彼女の言う、ふたまわり細いサイズとはSS。実物を見せてもらいましたが、実にか細いスーツでした。外販のみのころは、ドレス一本でしたが、店を構えるようになって、ダンス衣装、スーツ、パーティ用ドレスなどを求める顧客が増えたそうです。

土本さんにこれからの目標を聞きました。「売上の目標は特にありません。お金はどうでもいいんです。まずは、お客様に喜んでもらえるドレスやスーツを一着でも多く提供することです。そのためにオンラインやリアルのショップを充実させることです」。彼女の仕事上の立ち位置は、「無理はしないこと。自分で出来ることは自分でやる。できないことは、できる方にお願いすること」と、実に自然体です。
「学生のころは、心のどこかで自分の居場所がないと思っていました。バイトを掛け持ちしていたころは、一日が終わって、家に帰って寝るだけの毎日でした。楽しかったけれど、明日に希望なんて持っていませんでした。でも、今は忙しいんですが、今日そして、明日に希望が持てるようになりました。そして、ここに自分の居場所があることが何より幸せです」。
「今、引きこもりが話題になっていますけど、私には彼らの気持ちがわかるんです。でも、社会に出ることは私にもできたんだから、皆にも必ずできると思っています。特に自営業は、私がそうだったように、引きこもっている人に向いていると思うんです。一つの価値観ではなく、いろんな価値観があって、それをどう活かすかの自由があるからです。是非とも外の世界に一歩踏み込む勇気を持ってほしい」。
土本さんにこれまでの23年間を振り返ってもらうと、こんな言葉が返ってきました。忙しくなった、そんな彼女にとって今残念なことは、外販に行く機会が少なくならざるを得ないことでした。他県への外販では観光などする時間がない彼女ですが、他県の風景や人々に触れることが今でも新鮮で好きなのだそうです。
「人生の最期に、土本宏子ってどんな女性だったと言われたいですか?」とお聞きしました。「自由な人だった、と言われたいです」という返事でした。団体行動が嫌だったいう彼女が、自らの行動によって多くの顧客を得、それが今、全国に広がっていることに率直に驚きを感じます。しかし、束縛されない自らの行動が、今の土本宏子さんを活き活きと輝かせている。それがすべてを語っているのだと思いました。
土本さんが外販で培った人脈は更に広がり続け、オンラインSHOPで全国の顧客を掴み、リアルSHOPで地元の新たな顧客層を確実に掴みつつあります。土本さんは意識することもなく結果的にビジネスの基本を一歩一歩歩んでいます。インタヴューを終え、「KINA」を後にしながら表に出ると警察が火元の現場を検証中でした。自分の足元を見ると、靴が消火剤で真っ白でした。

ドレスSHOP「KINA」
〒860-0807
熊本市下通り1-12-3 高津ビル3F
TEL&FAX:096-355-2225
http://www.kina-kina.jp/
E-mail:shopmaster@kina-kina.jp
土本宏子さんのブログ
■熊本DRESS・SHOP『KINA』土本の思いつき日記
http://ameblo.jp/kina20050601/entry-10076292580.html
池田晴美さんのブログ
★熊本DRESS・SHOP『KINA』店長のブログ★
http://ameblo.jp/kinamoco/

いきなり余談ですが、私が約束の10分前にショップの前を通りかかったときに、なんと一軒手前の隣のビルの隙間から黒煙が立ち始めているではありませんか。そこに置かれた建築材のボードから出火していたのです。気づいたときには、近隣のお店から慌てて出てこられた女性から消火器を受け取り、消火活動をしていました。出火の原因は定かではありません。
短い消火活動を終えた私は、約束の時間に「KINA」に到着。ワインレッドの絨毯とブラックの内装の店内にはドレスやスーツが所狭しと並んでいます。そこに土本さんと店長の池田晴美さんがいらっしゃいました。挨拶もそこそこに、まず、「KINA」というネーミングについてうかがうと、彼女の愛犬(オスのパグ)の名前をつけたそうです。毛が黄色だったことから「キナ」。この「キナ」は彼女のブログでも度々登場していました。
彼女がこの「KINA」を始めたきっかけは、三年前にとあるテレビ番組でキャバクラ女性の24時間を追ったルポルタージュを見たことでした。その中で登場したある男性が、新宿で女性たちにドレスを訪問販売している模様があって、彼女にインスピレーションをもたらしました。「これなら、私でもできるかも」→「これ、私ならできるな」→「これをやろう」と瞬時に決断したそうです。(外では消防車のサイレンの音が聞こえていました・・・)
土本さんは中高時代に、自分が団体行動で生活することに違和感を持っていました。思い悩んだ末、彼女はご両親に相談して高校中退の道を選び、社会に出ることを決めます。居酒屋のアルバイトから始め、18歳になったときにキャバクラ、そしてクラブの世界へ。そのときには三つの仕事を掛け持ちでこなしていたといいます。土本さんにとっては忙しい仕事も、「世の中にはこんなにいろんな仕事があるんだ」という好奇心が先立ちました。しかもこの三年間で仕事をしながら、彼女は通信教育で高校卒業の資格も取得しています。
自分が夜の仕事で着用していたことからドレスの訪販を決意したものの、アパレル業界の知識、販売経験のない彼女は、これまでのつてを頼ったり、ネットで熊本や全国に仕入先を求めますが、既存のドレスショップとのバッティングなどで仕入れさせてくれるメーカーがなかなか見つかりませんでした。そんな中、土本さんに「韓国なら安く仕入れられる」という情報が飛び込んできました。暗中模索中の彼女はあれこれ考えるよりも先に、まず友人と韓国に飛んでいました。なぜか、釜山(プサン)へ。
「韓国のこと、何も知らなかったんです。韓国なら釜山だと思って行きました」と。結構大胆です。「当然韓国語も喋れないので、釜山で日本語を話せる人を探して友達になって、ドレスの仕入先を教えてもらったんです。そうしたら、それならソウルに行きなさいって言われたんですね」。土本さんは、その「友達」から韓国で有名なメーカーの情報を得て、いったん帰国後、今度は一人でソウルに向かいます。
釜山のときと同じように、初めてのソウルでも日本語の喋れる韓国人を探して、そのお目当ての仕入先に行き着いた彼女が仕入れたドレスは50着。このドレスをもとに、いよいよ移動販売「KINA」の第一歩がスタートします。実際販売してみると、サイズの違いなどがあっていくつか問題点があることがわかってきました。仕入先との何度かのやり取りを通じて、いつしか先方にカット、縫製を指示できるようにまでなっていました。
訪問販売先は紹介先から紹介先へと広がり、県内で契約店は30店舗に達しました。九州各地の訪問先へもその流れで鹿児島、宮崎、大分と広がっていきました。私が不意に「他県へ出張されるときにはどんなホテルに泊まるんですか?」とお聞きしたところ、「いえいえ、そんな勿体ないことはできません。すべて日帰りです。一度に100着ほど持って行くんですが、はじめはすべて一人でやりました。お客様の仕事柄、朝の4時から販売開始なんてこともあります。今は出張先に搬入などお手伝いしてくれるスタッフがいるので、多少は楽になりました」と。かなりパワフルです。
熊本を中心に九州各地で実績を積んでいく土本さんの姿がいつしか業界関係者の間で噂になり、日本のメーカーからも声がかかるようになります。今ではメーカーサイドから営業に来るほどになっているそうです。街を歩いていると今でもキャバクラからスカウトされたりするそうですが、土本さんは逆に営業をかけることもしばしばあるそうです。まだ電話でしか話したことのない仕入先の社長さんからもブログを見て、「全国的に見ても一番若いオーナーだ。頑張れ」と言われましたという程の活躍ぶりです。

そして、昨年のオンラインSHOPとリアル店舗「KINA」のオープン。「最初は、外販一本でやっていくつもりでした。お店を出すなんて全く考えていませんでした」と語る土本さん。「外販を続けているうちに、どうしても外販に行けないお客様がいらしたり、周りから店を出したらいいじゃないかとか、君ならできるよなんて言ってくれる方々がいて、じゃ、やってみようと思うようになったんです」。
出店資金は、昨年の5月に国民金融公庫からの融資を取り付けました。「自分で事業計画も作りました。最終的には税理士さんの助言を受けながらですけど・・・」と、立派な事業家です。オープンのときは、数多くのスタンド花が寄せられ、ショップのある3階から1階までの階段で納まりきれずに、光琳寺通りにまで並ぶほどだったそうです。取り扱い商品は、今では国内メーカーのものになっているそうです。なかでも、㈱HOT CLOTHING社の「R」、「WPC(WAY PAST COOL)」などは、仕入元と「KINA」の完全独占販売。
土本さんのモットーは、「お客様にあったドレスは必ず探し出します」ということ。「今の若い女性は細い人が多いんですよ。私よりもふたまわり位細いんです。そんなお客様にもピッタリのドレスや、逆に私よりふたまわり位大きいサイズのドレスなど、他所ではなかなか見つけられないものでも、私たちは必ず準備する自信があります」と、この点だけはやけに力が入っていました。さすがにオーナーです。
ちなみに土本さんは170cmの長身。しかもヒールを履いているので180cmには達していて、私には充分スリムに見えますし、サイズはM(9号)だそうです。彼女の言う、ふたまわり細いサイズとはSS。実物を見せてもらいましたが、実にか細いスーツでした。外販のみのころは、ドレス一本でしたが、店を構えるようになって、ダンス衣装、スーツ、パーティ用ドレスなどを求める顧客が増えたそうです。

土本さんにこれからの目標を聞きました。「売上の目標は特にありません。お金はどうでもいいんです。まずは、お客様に喜んでもらえるドレスやスーツを一着でも多く提供することです。そのためにオンラインやリアルのショップを充実させることです」。彼女の仕事上の立ち位置は、「無理はしないこと。自分で出来ることは自分でやる。できないことは、できる方にお願いすること」と、実に自然体です。
「学生のころは、心のどこかで自分の居場所がないと思っていました。バイトを掛け持ちしていたころは、一日が終わって、家に帰って寝るだけの毎日でした。楽しかったけれど、明日に希望なんて持っていませんでした。でも、今は忙しいんですが、今日そして、明日に希望が持てるようになりました。そして、ここに自分の居場所があることが何より幸せです」。
「今、引きこもりが話題になっていますけど、私には彼らの気持ちがわかるんです。でも、社会に出ることは私にもできたんだから、皆にも必ずできると思っています。特に自営業は、私がそうだったように、引きこもっている人に向いていると思うんです。一つの価値観ではなく、いろんな価値観があって、それをどう活かすかの自由があるからです。是非とも外の世界に一歩踏み込む勇気を持ってほしい」。
土本さんにこれまでの23年間を振り返ってもらうと、こんな言葉が返ってきました。忙しくなった、そんな彼女にとって今残念なことは、外販に行く機会が少なくならざるを得ないことでした。他県への外販では観光などする時間がない彼女ですが、他県の風景や人々に触れることが今でも新鮮で好きなのだそうです。
「人生の最期に、土本宏子ってどんな女性だったと言われたいですか?」とお聞きしました。「自由な人だった、と言われたいです」という返事でした。団体行動が嫌だったいう彼女が、自らの行動によって多くの顧客を得、それが今、全国に広がっていることに率直に驚きを感じます。しかし、束縛されない自らの行動が、今の土本宏子さんを活き活きと輝かせている。それがすべてを語っているのだと思いました。
土本さんが外販で培った人脈は更に広がり続け、オンラインSHOPで全国の顧客を掴み、リアルSHOPで地元の新たな顧客層を確実に掴みつつあります。土本さんは意識することもなく結果的にビジネスの基本を一歩一歩歩んでいます。インタヴューを終え、「KINA」を後にしながら表に出ると警察が火元の現場を検証中でした。自分の足元を見ると、靴が消火剤で真っ白でした。

ドレスSHOP「KINA」
〒860-0807
熊本市下通り1-12-3 高津ビル3F
TEL&FAX:096-355-2225
http://www.kina-kina.jp/
E-mail:shopmaster@kina-kina.jp
土本宏子さんのブログ
■熊本DRESS・SHOP『KINA』土本の思いつき日記
http://ameblo.jp/kina20050601/entry-10076292580.html
池田晴美さんのブログ
★熊本DRESS・SHOP『KINA』店長のブログ★
http://ameblo.jp/kinamoco/
2008年02月24日
新たな温泉ブランドを目指す、若き起業家・福田厚氏(12)
12回目のゲストは、第一回目の守屋尚さん、第三回目の松岡雄一さん、第六回目の田上菜穂美さんと同じ創業塾の塾生だった福田厚氏(36)さん。熊本県北部に位置し、2006年3月1日、菊水町と三加和町が対等合併した和水(なごみ)町で今年、福田さんは家族湯「湯亭 上弦の月」を開業予定です。翌日が地鎮祭というまさに一番忙しいときに時間をもらって話をうかがいました。

12年間東京でアパレル業界のMD(マーチャンダイザー)を勤めていた福田さんは、ご長男に続き二人目のお子様になるご長女の誕生を機に熊本に帰ることを決意され、昨年3月にUターン。和水町でお父様が経営されている不動産事業、更に町から嘱託されて支配人(H20年1月末で退職)を務められていた第三セクターを発展させた、民活と地域興しの両立という発想で「家族湯」事業を発案されました。創業塾の第一回目が昨年8/25でしたが、すでにそのときに青写真が出来ていました。
福田さんと私は創業塾では別グループだったので、福田さんが家族湯を事業にされようとしていることを知ったのは、塾終了後の懇親会でお会いしたときでした。そのときには事業計画書もほぼできあがり、金融機関との融資交渉が進んでいました。私の単純な興味は、福田さんがサラリーマンから転進していきなり事業計画書を書き上げ、金融機関との折衝まで漕ぎ着けているという俊敏さでした。Uターンした時は家族湯をするとは思っていなかった福田さんの事業の発案は昨年の7月だったといいます。
福田さんが戻ってみると、お父様は第三セクターの支配人としての仕事が忙しく、ご自分の会社はほったらかし状態に近く、福田さんが実質的に引継ぐことになりました。「縫製工場は業績不振で6年前に廃業。自社工場跡地を利用し不動産賃貸業に事業転換。現在は家賃収入で前事業の債務整理中。このままでいくと完済まで約20年掛かるため、新たな事業の柱が必要でした。会社の内容を整理しながら不動産事業とは別の収入源としてソフトバンクモバイル・Yahoo! BBの取扱店としての活動を拡大している最中でした」。

一方で、お父様を手伝うために第三セクターにたびたび出入りし、「ボランティアでイベントの手伝いなどしていると色々と企画のアイデアや事業プランなどが浮かんできたんですが三セクの性質上、実現がなかなか難しいんですね」。だったら自分の手で事業を起こそうというのが福田さんの気概。(写真は「三加和温泉ふるさと交流センター」)
お父様が縫製工場の経営者であったことから、ゆくゆくは自分が継ぐことになるだろうということで福田さんが就職されたのが前述のアパレルメーカーでしたが、このMDという仕事で彼が積んだキャリアがこの起業アクションの俊敏さを生んだのでした。「事業計画書は9月の時点ではラフ案でした。出来たものを順次銀行に見せながら、最終的な計画書は12月に提出。1月に1回目の融資が実行されました」と淡々と語られます。普通はここが一番難しいところですが、福田さんは一気に駆け抜けます。
「私がいたのは百貨店向けブランドも手がける中堅企業でしたが、そこではブランドが一つの会社と同じなんです。MDは、企画、原材料(素材)選び、デザイン、製造、物流、販売とエンドユーザーまでの流れにすべて関わっていました。この経験は貴重だったと思います」と福田さん。
家族湯の着想までの経緯をもう少し詳しくうかがうと、MDだった当時から福田さんにはぼんやりとではありながら、お客様とゆっくり対話できるような、サロン的な、くつろげる空間を造りたいという思いがありました。そこに、「家族湯」自体がもともとは近隣の山鹿市発祥であり、今では全国区になっている「平山温泉」が注目されていました。にも関わらず、和水町では民営二軒、町営二軒の四軒の温泉施設しかなく、温泉地として認知されない現状を何とか変えたいという着想になっていきます。
「あるとき、セミナーか本だったか忘れましたが、地域振興をする人は『若者、よそ者、ばか者』でなければならないということを聞いたんです。それが自分と重なると思ったんです」と福田さんは語ります。「ばか者」とはもちろん、「常識を超えられる者」という意味だと思いますが、おもしろい言葉だったので、ネットで検索してみると、ほぼ日刊イトイ新聞のリオ吉さんの次のような記事がありました。
「第2回 若者よそ者ばか者」(http://www.1101.com/amsterdam/2003-10-17.html)
前回、「アムステルダムほど自由なところはない」と、17世紀にデカルトさんが述べた(らしい)と書いたところで終わりましたが、どうしてそんな自由な雰囲気があったのかというと、やはりよそ者が入ってきて作り上げた街だからといえると思います。移民ですね、移民。しがらみがなく、ゼロから始める、移民。
もともとオランダのあるあたりは、海なのか陸なのかわからないような低地の湖沼地帯で、雨は多いし陽は照らないと、決して暮らしやすい土地とは呼べなかったところを、(プロテスタントと呼んでいいのでしょうか)新興階級とそれをささえる労働者が干拓で埋め立てて出来たところなんですね。新しいことは「若者で、よそ者で、ばか者」がやるといったのは邱(永漢)先生だったでしょうか、アムステルダムは、よそ者ばかりで作ったようなところなんです。
また、ある政治家のブログには次のような記述がありました。
「軽井沢をブランドの避暑地として掘り起こしたのは米国の伝道師、北海道のニセコをブランドスキー場にしたのはオーストラリア人です。私が美作で親しくしていただいている支援者の何人かは、一度美作を離れたことのある方々です。情報量が異なると、同じものをみる視点が異なるというのが、よそ者なのかなあ、とも思います。米国に8年間いたので、日本で気づいたこともあります。諸外国をまわったからこそ、わかることもあります」。
「若者、よそ者、ばか者」、福田さんは36歳、この町出身ですが12年間東京で暮らした「よそ者」。「『ばか者』」役(前述の意味で)は地元では多少影響力のある父に任せておけばいい」、というのが福田さんのこの事業に立ち向かうエネルギーです。そして、この「家族湯」というハードを、最高の「もてなし」というソフトで提供したいというのが福田さんの真骨頂です。福田さんは、地に足のついたホスピタリティを追求したいと語られました。

「国道443号の和水町内を走行すると道の南側に温泉街が見える。町内には、三加和温泉ふるさと交流センターとふれあいの森あばかん家の二つの施設がある。町営ではないが、ふるさと交流センター前のコンビニの中に天然温泉の家族風呂があり地元のテレビなどで紹介された。最近は、付近に家族風呂を備えた温泉がオープンしたり、隣の山鹿市の平山温泉などとともに注目されている」。
これは、「三加和温泉」に関する現在のウィキペディアの記事です。福田さんはきっとこの記事を書き換えたいはずです。この地に、本物のホスピタリティ空間を造る。その手段が当面は「家族湯「湯亭 上弦の月」。「三加和温泉」のこの最後の文章にはっきりと「全国でも有名になった」と前置きがされることを。
地鎮祭を終えればいよいよボーリングが始まります。福田さんは、温泉を掘り起こす期限を5月いっぱいと踏んでいます。12~14部屋の貸しきり温泉施設をできれば10月、遅くとも12月までのオープンさせることを目指しています。これからまさに時間との闘いだと思った私は、「これから胃の痛い日が続きますね」と打診すると、「いや、私は鈍感だから大丈夫だと思います」と応えられました。さすがです。
このブログでは、その後の進捗などをフォローできればと考えています。

12年間東京でアパレル業界のMD(マーチャンダイザー)を勤めていた福田さんは、ご長男に続き二人目のお子様になるご長女の誕生を機に熊本に帰ることを決意され、昨年3月にUターン。和水町でお父様が経営されている不動産事業、更に町から嘱託されて支配人(H20年1月末で退職)を務められていた第三セクターを発展させた、民活と地域興しの両立という発想で「家族湯」事業を発案されました。創業塾の第一回目が昨年8/25でしたが、すでにそのときに青写真が出来ていました。
福田さんと私は創業塾では別グループだったので、福田さんが家族湯を事業にされようとしていることを知ったのは、塾終了後の懇親会でお会いしたときでした。そのときには事業計画書もほぼできあがり、金融機関との融資交渉が進んでいました。私の単純な興味は、福田さんがサラリーマンから転進していきなり事業計画書を書き上げ、金融機関との折衝まで漕ぎ着けているという俊敏さでした。Uターンした時は家族湯をするとは思っていなかった福田さんの事業の発案は昨年の7月だったといいます。
福田さんが戻ってみると、お父様は第三セクターの支配人としての仕事が忙しく、ご自分の会社はほったらかし状態に近く、福田さんが実質的に引継ぐことになりました。「縫製工場は業績不振で6年前に廃業。自社工場跡地を利用し不動産賃貸業に事業転換。現在は家賃収入で前事業の債務整理中。このままでいくと完済まで約20年掛かるため、新たな事業の柱が必要でした。会社の内容を整理しながら不動産事業とは別の収入源としてソフトバンクモバイル・Yahoo! BBの取扱店としての活動を拡大している最中でした」。

一方で、お父様を手伝うために第三セクターにたびたび出入りし、「ボランティアでイベントの手伝いなどしていると色々と企画のアイデアや事業プランなどが浮かんできたんですが三セクの性質上、実現がなかなか難しいんですね」。だったら自分の手で事業を起こそうというのが福田さんの気概。(写真は「三加和温泉ふるさと交流センター」)
お父様が縫製工場の経営者であったことから、ゆくゆくは自分が継ぐことになるだろうということで福田さんが就職されたのが前述のアパレルメーカーでしたが、このMDという仕事で彼が積んだキャリアがこの起業アクションの俊敏さを生んだのでした。「事業計画書は9月の時点ではラフ案でした。出来たものを順次銀行に見せながら、最終的な計画書は12月に提出。1月に1回目の融資が実行されました」と淡々と語られます。普通はここが一番難しいところですが、福田さんは一気に駆け抜けます。
「私がいたのは百貨店向けブランドも手がける中堅企業でしたが、そこではブランドが一つの会社と同じなんです。MDは、企画、原材料(素材)選び、デザイン、製造、物流、販売とエンドユーザーまでの流れにすべて関わっていました。この経験は貴重だったと思います」と福田さん。
家族湯の着想までの経緯をもう少し詳しくうかがうと、MDだった当時から福田さんにはぼんやりとではありながら、お客様とゆっくり対話できるような、サロン的な、くつろげる空間を造りたいという思いがありました。そこに、「家族湯」自体がもともとは近隣の山鹿市発祥であり、今では全国区になっている「平山温泉」が注目されていました。にも関わらず、和水町では民営二軒、町営二軒の四軒の温泉施設しかなく、温泉地として認知されない現状を何とか変えたいという着想になっていきます。
「あるとき、セミナーか本だったか忘れましたが、地域振興をする人は『若者、よそ者、ばか者』でなければならないということを聞いたんです。それが自分と重なると思ったんです」と福田さんは語ります。「ばか者」とはもちろん、「常識を超えられる者」という意味だと思いますが、おもしろい言葉だったので、ネットで検索してみると、ほぼ日刊イトイ新聞のリオ吉さんの次のような記事がありました。
「第2回 若者よそ者ばか者」(http://www.1101.com/amsterdam/2003-10-17.html)
前回、「アムステルダムほど自由なところはない」と、17世紀にデカルトさんが述べた(らしい)と書いたところで終わりましたが、どうしてそんな自由な雰囲気があったのかというと、やはりよそ者が入ってきて作り上げた街だからといえると思います。移民ですね、移民。しがらみがなく、ゼロから始める、移民。
もともとオランダのあるあたりは、海なのか陸なのかわからないような低地の湖沼地帯で、雨は多いし陽は照らないと、決して暮らしやすい土地とは呼べなかったところを、(プロテスタントと呼んでいいのでしょうか)新興階級とそれをささえる労働者が干拓で埋め立てて出来たところなんですね。新しいことは「若者で、よそ者で、ばか者」がやるといったのは邱(永漢)先生だったでしょうか、アムステルダムは、よそ者ばかりで作ったようなところなんです。
また、ある政治家のブログには次のような記述がありました。
「軽井沢をブランドの避暑地として掘り起こしたのは米国の伝道師、北海道のニセコをブランドスキー場にしたのはオーストラリア人です。私が美作で親しくしていただいている支援者の何人かは、一度美作を離れたことのある方々です。情報量が異なると、同じものをみる視点が異なるというのが、よそ者なのかなあ、とも思います。米国に8年間いたので、日本で気づいたこともあります。諸外国をまわったからこそ、わかることもあります」。
「若者、よそ者、ばか者」、福田さんは36歳、この町出身ですが12年間東京で暮らした「よそ者」。「『ばか者』」役(前述の意味で)は地元では多少影響力のある父に任せておけばいい」、というのが福田さんのこの事業に立ち向かうエネルギーです。そして、この「家族湯」というハードを、最高の「もてなし」というソフトで提供したいというのが福田さんの真骨頂です。福田さんは、地に足のついたホスピタリティを追求したいと語られました。

「国道443号の和水町内を走行すると道の南側に温泉街が見える。町内には、三加和温泉ふるさと交流センターとふれあいの森あばかん家の二つの施設がある。町営ではないが、ふるさと交流センター前のコンビニの中に天然温泉の家族風呂があり地元のテレビなどで紹介された。最近は、付近に家族風呂を備えた温泉がオープンしたり、隣の山鹿市の平山温泉などとともに注目されている」。
これは、「三加和温泉」に関する現在のウィキペディアの記事です。福田さんはきっとこの記事を書き換えたいはずです。この地に、本物のホスピタリティ空間を造る。その手段が当面は「家族湯「湯亭 上弦の月」。「三加和温泉」のこの最後の文章にはっきりと「全国でも有名になった」と前置きがされることを。
地鎮祭を終えればいよいよボーリングが始まります。福田さんは、温泉を掘り起こす期限を5月いっぱいと踏んでいます。12~14部屋の貸しきり温泉施設をできれば10月、遅くとも12月までのオープンさせることを目指しています。これからまさに時間との闘いだと思った私は、「これから胃の痛い日が続きますね」と打診すると、「いや、私は鈍感だから大丈夫だと思います」と応えられました。さすがです。
このブログでは、その後の進捗などをフォローできればと考えています。
2008年02月16日
スタイリッシュな支援を、社会起業家・西梅彰容(011)(下)
「やっぱり動かずにはいられなかった」西梅さんのもっと奥にある動機は何だったのか?私はそれを探るためにまず、これまでの彼女の24年間を振り返ってもらうことにしました。
それは彼女が小6のとき。「世界のしくみ」に関することを書いた本に出会います。その本の中に、「ストリート・チルドレン」のことが書かれていました。自分には何不足ない環境があるのに世界にはこうした環境で暮らしている子供たちがいることを知り、心を痛めた彼女は、「ユニセフに入りたい」と思ったそうです。「この国連職員になるために、私はそのために勉強しよう」と。
その向学心は高校受験で成果を発揮し、授業料全額免除の成績で入学します。小学校教諭だったお母様が西梅さんにこう切り出します。「あなたのために準備した授業料がお蔭で必要なくなりました。ついてはこの一部を恵まれない国の子供たちに寄付したいと思います」。クリスチャンのお母様はいつも彼女に「子供は神様に一番近いところにいる」と教えていました。以来、西梅さんは自分で収入を得はじめてからは今でも「チャイルド・スポンサー」という「里親」であり続けています。現在の「里子」はウガンダとバングラディッシュの子供たちです。
16歳。YMCA主催のワークキャンプ(スタディ・ツアー)でタイに行きます。そこで幹線道路下のスラム街で暮らす家族にめぐり会います。その家族はもともとタイの農村で暮らしていました。しかし不作などによる生活苦によりバンコクに出てきてしかし仕事は無く、ゴミ捨て場から使えそうな物を拾って売り、家族4人で一日3~400円程で暮らしていました。そこで西梅さんは通訳を通じて「農村にいた頃と今ではどちらが幸せですか?」というシンプルな質問をします。「それは、もちろん農村にいた頃です。あの時は朝、目が覚めると『ああ、朝だな』、日が暮れると『夜のなったな』と感じることができた。でもここは、一寸の光も差し込まず、朝なのか昼なのかわからないから。でも、農村では暮らしていけないから帰ることはできな」という返答でした。彼女はこのことに衝撃を受けます。
彼らの暮らしぶりをまざまざと見て、「夜、安心して眠ることは、平和の象徴なんだ」と彼女は考えるようになります。この体験を契機に西梅さんは、「人間の存在って何だろう?人間の営みって何だろう?自分の生きて行く理由って何だろう?」と考えるようになります。そう思った彼女は、養老孟司さんの著書「唯脳論」などを通じて、生物学的視点、社会行動学的視点のクロスするところにその答えがある筈だという仮説を立てました。(16歳でここまで考えるとは・・・)

こういったことを大学でも学ぼうと思った西梅さんは目標にする大学探しを始めますが、いっこうに目当ての学部を見つけられませんでしたが、一つだけ該当する学部がありました。それは東京大学教養学部でした。目標が定まったその日から西梅さんの猛勉強が始まります。毎日12時間。しかし、このストイックなまでのハードな勉強が彼女の心を蝕んでいきました。そして、うつ病と診断されるまでに彼女の心は衰弱してしまったのです。
彼女の残る高校生活2年間は心の癒しへの時間に費やされることになりました。その間、西梅さんは、県主催の「少年の船」(http://ksfl-web.com/pc/)で沖縄へ何度か訪れます。他にも奄美や鹿児島、静岡、冬の長野、新潟を訪れている中で、自然と子供の関わりの大切さを感じ、同時に、この経験を通して、何の価値も見いだせなかった自分の中に「好奇心」があることを自覚します。
高校を卒業し19歳になった彼女は、何かに誘われるかのようにNGOの活動のためインド、バングラディシュへ。このときカルカッタでマザー・テレサの施設「死を待つ人の家」を訪れます。そこで、西梅さんは路上で死んでいく人たちを目の当たりにします。幼い頃から常に生と死について考えてきた彼女の中では、常に自殺願望がありました。しかし、この光景を見た彼女に「でも、犬死はしたくない」という気持ちが生まれたのです。

そして、数年後に旅行で訪れたベトナムでも衝撃を受けます。ベトナムの純朴な人々、肥沃なメコン川、美しい農村の風景、色とりどりに咲き乱れる野生の花々、木からもぎってすぐに食べられる果物、豊かで美しくてまるで天国のような場所だと感動します。そしてそのあと、西梅さんはベトナム戦争博物館を訪れるのです。ベトナム戦争の実態をはじめて知った彼女は放心状態になるほどの衝撃を受けます。こんな美しいところへ枯葉剤を撒き、あらゆる戦闘機器を駆使し罪のない人々を次々と殺戮し拷問し、そして意味のない戦いとして終わった。この事実に触れ、西梅さんは、自分は何もしないまま死んではいけない、と、世界にあふれる不条理をそのままにしてはいけないと強く思うのです。
その後、西梅さんは友達からの誘いで、熊本が本社でカフェを運営する会社に入ります。ここで4年間勤める中で、彼女はコーヒー豆の生産と流通に阻む経済格差問題を知ることになります。どうも彼女の目には普通の人では見過ごしそうなことも、透視をするようにはっきりとした形で異常な実態が映し出されるようです。農産物などにはこうした不公平な事態を是正すべく「フェア・トレード」というシステムがあることを学びます。
 既に熊本の三店舗、福岡の一店舗の運営指導の立場になっていた彼女は、「とのかく今、何かできることをしよう」と思い立ちます。コーヒー豆の生産と流通に潜む途上国と先進諸国の経済格差問題と、そのような不公平な事態を是正する「フェア・トレード」という新しい流通システムを知った彼女は全店舗のコーヒー豆に利用したものに切り換えることを経営サイドに提案し、GOサインをもらいます。了解は取ったものの、彼女の前には「コストを上げない、質を落とさない」というハードルが大きく立ちはだかりました。この難題に数ヶ月をかけて集中します。
既に熊本の三店舗、福岡の一店舗の運営指導の立場になっていた彼女は、「とのかく今、何かできることをしよう」と思い立ちます。コーヒー豆の生産と流通に潜む途上国と先進諸国の経済格差問題と、そのような不公平な事態を是正する「フェア・トレード」という新しい流通システムを知った彼女は全店舗のコーヒー豆に利用したものに切り換えることを経営サイドに提案し、GOサインをもらいます。了解は取ったものの、彼女の前には「コストを上げない、質を落とさない」というハードルが大きく立ちはだかりました。この難題に数ヶ月をかけて集中します。
苦労を重ねたのち、今年の5月にやっと全てがクリアになり準備が整いました。いよいよ明日からこの新しい豆に切り換えてスタートという日になんと突如、ストップがかかってしまったのです。苦渋の経営判断があったのです。そして、頓挫した計画とともにハードワークがたたり、西梅さんは倒れてしまいました。7月から12月まで休職を余儀なくされました。彼女にとって二度目の大きな挫折でした。
そして、この間に抜け殻化した彼女が出会ったのが、福岡の街頭で販売されていた一冊の雑誌、「ビッグイシュー」でした。ホームレスの人々の自立支援をするこの一冊が、西梅さんの再起を促すことになりました。
私はいつものようにこの事業の目標をうかがいました。「メディアから今回の『ビッグイシュー熊本』の立ち上げに関する取材でよく聞かれんですね。それは、まず現在販売員のお二人に自立してもらうことです。自分たちができる範囲で一歩一歩やっていこうと思っています」。
しかし西梅さんには「ビッグイシュー熊本」の活動を通じて、日本での市民活動のあり方を変えたいという大きな目標があります。彼女は次のように語ってくれました。
 「こういう支援活動を行うものは、どこか地味で、お人よし、宗教じみているという偏見があるんです。でも、私は消費社会を謳歌している人間です。買い物も好き、おしゃれも好き、おいしいものも食べたい、そんな人間です。ストイックなんて言葉とはかけ離れています。でも、私の個人的な希望は、お洒落なカフェでOLや子育て中のママさんが『私の里子がね・・・』って、日常会話で話されるような、そんなスタイリッシュな支援活動がなされる社会になること。これからの支援活動・社会活動は決してストイックである必要はないんだと思います。むしろこの消費社会の中ではその方が、多くの人の賛同を得られると思います。矛盾しているように思えるかもしれませんが、早く、一人でも多くの人を助けるためには、矛盾を飲み込むことも必要だと私は思っています」。
「こういう支援活動を行うものは、どこか地味で、お人よし、宗教じみているという偏見があるんです。でも、私は消費社会を謳歌している人間です。買い物も好き、おしゃれも好き、おいしいものも食べたい、そんな人間です。ストイックなんて言葉とはかけ離れています。でも、私の個人的な希望は、お洒落なカフェでOLや子育て中のママさんが『私の里子がね・・・』って、日常会話で話されるような、そんなスタイリッシュな支援活動がなされる社会になること。これからの支援活動・社会活動は決してストイックである必要はないんだと思います。むしろこの消費社会の中ではその方が、多くの人の賛同を得られると思います。矛盾しているように思えるかもしれませんが、早く、一人でも多くの人を助けるためには、矛盾を飲み込むことも必要だと私は思っています」。
自然体でこの「ビッグイシュー熊本」と歩んで生きたいと語る西梅さんに、私はそれでの天邪鬼的に将来の彼女を想像してもらいました。すると、「貧困問題に命を懸けて取り組めるようなジャーナリストになることです」という即答が返ってきました。穏やかではありません。しかし、これまで「死」といつも寄り添うように生きてきた西梅さん、そして「好奇心」「行動力」「犬死したくない」というキーワードがそこにピッタリとはまってしまうことに気づくのです。前半の記事を見た西梅さんから次のようなメッセージが届きました。
私には「後悔」という思考回路がないようです。だから、先の心配をあまりせずに動くことができるんでしょうね。私はクリスチャンではありませんが『すべては益にかえられる』『神様のなさることは時にかなってすべて美しい』という聖書の言葉を信じています。そして、「運命」は自分ではコントロールできないものだということを。私は、自分の運命を受け入れることができたとき、はじめて心に平穏が訪れました。
そして、自殺を何度も何度も考えたとき、「なぜ自分はこんなに死にたいんだろう」と一生懸命考えた結論が・・・滑稽かもしれませんが・・前世の私は自殺をしたのではなかろうかと、それを今世で克服するためにこんな「(精神的に)死と対峙する」試練を与えられているのではないかと。そうとしか思えないくらい死がいつもそばにありました。
だから、今世の私の一番の目標は自殺しないことです。天命を全うすることです。それできっといいんだろうと思っています。そして、自分にも人にも物事にも「素直」に接したい。とってもシンプルです。
「やっぱり動かずにはいられなかった」西梅さんのもっと奥にある動機は何だったのか?ここまで聞いて、私はちゃんとその動機を理解できたように思います。そして、最後にもうひとつ、しかし、「やっぱり動かずにはいられなかった」西梅さんのほんとうの動機は、福岡の路上でこの雑誌を買った山本さんが書いていてた一編の詩でした。そして、偶然にも時を同じくして『ビッグイシュー熊本』の設立の一週間後に山本さんは職を得て自立されたのです。
「真っすぐに」
走ることが 嫌になったら 歩けばいい
ゆっくり ゆっくり 歩けばいい
歩くことに 疲れたら ゆっくり ゆっくり
休めばいい
でも あなたを待っている人がいる
早く会いたいと 待っている人がいる
さあ 立ち上がり 走りだそう
あなたを待っている 人のところへ
まっすぐに まっすぐに 迷わずに
ただ まっすぐに
それは彼女が小6のとき。「世界のしくみ」に関することを書いた本に出会います。その本の中に、「ストリート・チルドレン」のことが書かれていました。自分には何不足ない環境があるのに世界にはこうした環境で暮らしている子供たちがいることを知り、心を痛めた彼女は、「ユニセフに入りたい」と思ったそうです。「この国連職員になるために、私はそのために勉強しよう」と。
その向学心は高校受験で成果を発揮し、授業料全額免除の成績で入学します。小学校教諭だったお母様が西梅さんにこう切り出します。「あなたのために準備した授業料がお蔭で必要なくなりました。ついてはこの一部を恵まれない国の子供たちに寄付したいと思います」。クリスチャンのお母様はいつも彼女に「子供は神様に一番近いところにいる」と教えていました。以来、西梅さんは自分で収入を得はじめてからは今でも「チャイルド・スポンサー」という「里親」であり続けています。現在の「里子」はウガンダとバングラディッシュの子供たちです。
16歳。YMCA主催のワークキャンプ(スタディ・ツアー)でタイに行きます。そこで幹線道路下のスラム街で暮らす家族にめぐり会います。その家族はもともとタイの農村で暮らしていました。しかし不作などによる生活苦によりバンコクに出てきてしかし仕事は無く、ゴミ捨て場から使えそうな物を拾って売り、家族4人で一日3~400円程で暮らしていました。そこで西梅さんは通訳を通じて「農村にいた頃と今ではどちらが幸せですか?」というシンプルな質問をします。「それは、もちろん農村にいた頃です。あの時は朝、目が覚めると『ああ、朝だな』、日が暮れると『夜のなったな』と感じることができた。でもここは、一寸の光も差し込まず、朝なのか昼なのかわからないから。でも、農村では暮らしていけないから帰ることはできな」という返答でした。彼女はこのことに衝撃を受けます。
彼らの暮らしぶりをまざまざと見て、「夜、安心して眠ることは、平和の象徴なんだ」と彼女は考えるようになります。この体験を契機に西梅さんは、「人間の存在って何だろう?人間の営みって何だろう?自分の生きて行く理由って何だろう?」と考えるようになります。そう思った彼女は、養老孟司さんの著書「唯脳論」などを通じて、生物学的視点、社会行動学的視点のクロスするところにその答えがある筈だという仮説を立てました。(16歳でここまで考えるとは・・・)

こういったことを大学でも学ぼうと思った西梅さんは目標にする大学探しを始めますが、いっこうに目当ての学部を見つけられませんでしたが、一つだけ該当する学部がありました。それは東京大学教養学部でした。目標が定まったその日から西梅さんの猛勉強が始まります。毎日12時間。しかし、このストイックなまでのハードな勉強が彼女の心を蝕んでいきました。そして、うつ病と診断されるまでに彼女の心は衰弱してしまったのです。
彼女の残る高校生活2年間は心の癒しへの時間に費やされることになりました。その間、西梅さんは、県主催の「少年の船」(http://ksfl-web.com/pc/)で沖縄へ何度か訪れます。他にも奄美や鹿児島、静岡、冬の長野、新潟を訪れている中で、自然と子供の関わりの大切さを感じ、同時に、この経験を通して、何の価値も見いだせなかった自分の中に「好奇心」があることを自覚します。
高校を卒業し19歳になった彼女は、何かに誘われるかのようにNGOの活動のためインド、バングラディシュへ。このときカルカッタでマザー・テレサの施設「死を待つ人の家」を訪れます。そこで、西梅さんは路上で死んでいく人たちを目の当たりにします。幼い頃から常に生と死について考えてきた彼女の中では、常に自殺願望がありました。しかし、この光景を見た彼女に「でも、犬死はしたくない」という気持ちが生まれたのです。

そして、数年後に旅行で訪れたベトナムでも衝撃を受けます。ベトナムの純朴な人々、肥沃なメコン川、美しい農村の風景、色とりどりに咲き乱れる野生の花々、木からもぎってすぐに食べられる果物、豊かで美しくてまるで天国のような場所だと感動します。そしてそのあと、西梅さんはベトナム戦争博物館を訪れるのです。ベトナム戦争の実態をはじめて知った彼女は放心状態になるほどの衝撃を受けます。こんな美しいところへ枯葉剤を撒き、あらゆる戦闘機器を駆使し罪のない人々を次々と殺戮し拷問し、そして意味のない戦いとして終わった。この事実に触れ、西梅さんは、自分は何もしないまま死んではいけない、と、世界にあふれる不条理をそのままにしてはいけないと強く思うのです。
その後、西梅さんは友達からの誘いで、熊本が本社でカフェを運営する会社に入ります。ここで4年間勤める中で、彼女はコーヒー豆の生産と流通に阻む経済格差問題を知ることになります。どうも彼女の目には普通の人では見過ごしそうなことも、透視をするようにはっきりとした形で異常な実態が映し出されるようです。農産物などにはこうした不公平な事態を是正すべく「フェア・トレード」というシステムがあることを学びます。
 既に熊本の三店舗、福岡の一店舗の運営指導の立場になっていた彼女は、「とのかく今、何かできることをしよう」と思い立ちます。コーヒー豆の生産と流通に潜む途上国と先進諸国の経済格差問題と、そのような不公平な事態を是正する「フェア・トレード」という新しい流通システムを知った彼女は全店舗のコーヒー豆に利用したものに切り換えることを経営サイドに提案し、GOサインをもらいます。了解は取ったものの、彼女の前には「コストを上げない、質を落とさない」というハードルが大きく立ちはだかりました。この難題に数ヶ月をかけて集中します。
既に熊本の三店舗、福岡の一店舗の運営指導の立場になっていた彼女は、「とのかく今、何かできることをしよう」と思い立ちます。コーヒー豆の生産と流通に潜む途上国と先進諸国の経済格差問題と、そのような不公平な事態を是正する「フェア・トレード」という新しい流通システムを知った彼女は全店舗のコーヒー豆に利用したものに切り換えることを経営サイドに提案し、GOサインをもらいます。了解は取ったものの、彼女の前には「コストを上げない、質を落とさない」というハードルが大きく立ちはだかりました。この難題に数ヶ月をかけて集中します。苦労を重ねたのち、今年の5月にやっと全てがクリアになり準備が整いました。いよいよ明日からこの新しい豆に切り換えてスタートという日になんと突如、ストップがかかってしまったのです。苦渋の経営判断があったのです。そして、頓挫した計画とともにハードワークがたたり、西梅さんは倒れてしまいました。7月から12月まで休職を余儀なくされました。彼女にとって二度目の大きな挫折でした。
そして、この間に抜け殻化した彼女が出会ったのが、福岡の街頭で販売されていた一冊の雑誌、「ビッグイシュー」でした。ホームレスの人々の自立支援をするこの一冊が、西梅さんの再起を促すことになりました。
私はいつものようにこの事業の目標をうかがいました。「メディアから今回の『ビッグイシュー熊本』の立ち上げに関する取材でよく聞かれんですね。それは、まず現在販売員のお二人に自立してもらうことです。自分たちができる範囲で一歩一歩やっていこうと思っています」。
しかし西梅さんには「ビッグイシュー熊本」の活動を通じて、日本での市民活動のあり方を変えたいという大きな目標があります。彼女は次のように語ってくれました。
 「こういう支援活動を行うものは、どこか地味で、お人よし、宗教じみているという偏見があるんです。でも、私は消費社会を謳歌している人間です。買い物も好き、おしゃれも好き、おいしいものも食べたい、そんな人間です。ストイックなんて言葉とはかけ離れています。でも、私の個人的な希望は、お洒落なカフェでOLや子育て中のママさんが『私の里子がね・・・』って、日常会話で話されるような、そんなスタイリッシュな支援活動がなされる社会になること。これからの支援活動・社会活動は決してストイックである必要はないんだと思います。むしろこの消費社会の中ではその方が、多くの人の賛同を得られると思います。矛盾しているように思えるかもしれませんが、早く、一人でも多くの人を助けるためには、矛盾を飲み込むことも必要だと私は思っています」。
「こういう支援活動を行うものは、どこか地味で、お人よし、宗教じみているという偏見があるんです。でも、私は消費社会を謳歌している人間です。買い物も好き、おしゃれも好き、おいしいものも食べたい、そんな人間です。ストイックなんて言葉とはかけ離れています。でも、私の個人的な希望は、お洒落なカフェでOLや子育て中のママさんが『私の里子がね・・・』って、日常会話で話されるような、そんなスタイリッシュな支援活動がなされる社会になること。これからの支援活動・社会活動は決してストイックである必要はないんだと思います。むしろこの消費社会の中ではその方が、多くの人の賛同を得られると思います。矛盾しているように思えるかもしれませんが、早く、一人でも多くの人を助けるためには、矛盾を飲み込むことも必要だと私は思っています」。自然体でこの「ビッグイシュー熊本」と歩んで生きたいと語る西梅さんに、私はそれでの天邪鬼的に将来の彼女を想像してもらいました。すると、「貧困問題に命を懸けて取り組めるようなジャーナリストになることです」という即答が返ってきました。穏やかではありません。しかし、これまで「死」といつも寄り添うように生きてきた西梅さん、そして「好奇心」「行動力」「犬死したくない」というキーワードがそこにピッタリとはまってしまうことに気づくのです。前半の記事を見た西梅さんから次のようなメッセージが届きました。
私には「後悔」という思考回路がないようです。だから、先の心配をあまりせずに動くことができるんでしょうね。私はクリスチャンではありませんが『すべては益にかえられる』『神様のなさることは時にかなってすべて美しい』という聖書の言葉を信じています。そして、「運命」は自分ではコントロールできないものだということを。私は、自分の運命を受け入れることができたとき、はじめて心に平穏が訪れました。
そして、自殺を何度も何度も考えたとき、「なぜ自分はこんなに死にたいんだろう」と一生懸命考えた結論が・・・滑稽かもしれませんが・・前世の私は自殺をしたのではなかろうかと、それを今世で克服するためにこんな「(精神的に)死と対峙する」試練を与えられているのではないかと。そうとしか思えないくらい死がいつもそばにありました。
だから、今世の私の一番の目標は自殺しないことです。天命を全うすることです。それできっといいんだろうと思っています。そして、自分にも人にも物事にも「素直」に接したい。とってもシンプルです。
「やっぱり動かずにはいられなかった」西梅さんのもっと奥にある動機は何だったのか?ここまで聞いて、私はちゃんとその動機を理解できたように思います。そして、最後にもうひとつ、しかし、「やっぱり動かずにはいられなかった」西梅さんのほんとうの動機は、福岡の路上でこの雑誌を買った山本さんが書いていてた一編の詩でした。そして、偶然にも時を同じくして『ビッグイシュー熊本』の設立の一週間後に山本さんは職を得て自立されたのです。
「真っすぐに」
走ることが 嫌になったら 歩けばいい
ゆっくり ゆっくり 歩けばいい
歩くことに 疲れたら ゆっくり ゆっくり
休めばいい
でも あなたを待っている人がいる
早く会いたいと 待っている人がいる
さあ 立ち上がり 走りだそう
あなたを待っている 人のところへ
まっすぐに まっすぐに 迷わずに
ただ まっすぐに
2008年02月09日
スタイリッシュな支援を、社会起業家・西梅彰容(11)(上)
昨年12月初旬、FMの朝の番組「SKY」を聞いていて、「ビッグイシュー」という運動のことを知りました。イギリス発祥の「THE BIG ISSUE」という雑誌をホームレスの人たちが販売し収入を得ることによって自立支援を促す運動で、目下のところ大阪、神戸、京都、東京での活動が中心だということでした。
そして、今月2日、「ホームレスの自立支援雑誌 熊本市でも」という記事が目に留まりました。それによると、任意団体である支援団体「ビッグイシュー熊本」を立ち上げたのが24歳の女性であることを知り、驚いたのでした。私は、即日に大阪の(有)ビッグイシュー本部へインタヴュー申込みのメールを送信。そして、7日、その「ビッグイシュー熊本」の代表・西梅彰容(あきよ)さん(24)とお会いしまた。

2日以降、「ビッグイシュー」そのものの運動と「ビッグイシュー熊本」については、各メディアで競うように報じられました。その概要については、下記にリンク先を添付しておきますので、そちらでチェックしていだだくとして、ここでは、24歳の西梅彰容さんがなぜ、全国で13番目となるこの支援団体を立ち上げようと思われたのかについてご紹介したいと思います。
西梅さんがこの「ビッグイシュー」という本に初めて出合ったのは、昨年5月に販売が開始された福岡・天神でした。カフェの運営指導という立場にある西梅さんは、その一店舗である福岡店を訪れた際に路上販売をする「ビッグイシュー」を手に取ったのでした。この雑誌の意味を知り、その後何度か雑誌を購入していた西梅さんは販売員である山本さんに、どこで夜寝ていらっしゃるのですか?と尋ねます。
「今はビッグイシューの収入があるのでネットカフェで毎日眠れています、シャワーもありますしね。でもお金を使わないように5時間パックなんかにしてると、シャワー浴びたりなんかしてたらすぐ過ぎちゃうんですけどね~」と山本さんは笑いながら話されたそうです。
その山本さんの笑顔を見た西梅さんは、「ビッグイシューは『夜、安心して眠る』チャンスを販売者に本当に提供してるんだ」と実感します。「自分の目の前にいる人が本当にビッグイシューに救われている、
ということをリアルに感じたら、やっぱり動かずにはいられなかったんですね」と。
それでも私には、腑に落ちないところがありました。私もこのビッグイシューのことを知り、この活動が彼らの自立を後押しているんだなと理解しました。しかし、私はそれをブログの中で語っただけでした。率先して私が手を上げようとは思いもしませんでした。単に私が物臭なのか、他人事だと頭の中で整理しただけなのか?今回のインタヴューで私は自分の器について改めて考える機会をもらいました。
「やっぱり動かずにはいられなかった」西梅さんのもっと奥にある動機を私は知りたくなりました。今回はこうした理由で、インタヴューを前半と後半に分けてお送りします。(続く)
<ビッグイシュー関連記事>
「『ビッグイシュー』熊本市でも ホームレスが雑誌販売 4日から収益で自立目指す」(2008/02/03付西日本新聞)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/kumamoto/20080203/20080203_002.shtml
「ビッグイシュー:あすから販売 /熊本」(2月3日16時1分配信 毎日新聞)
http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20080203ddlk43040358000c.html
「ホームレスが売る雑誌 ビッグイシュー」(asahi.com2008年02月05日)
http://mytown.asahi.com/kumamoto/news.php?k_id=44000000802050003
「ビジネス通じホームレスの自立を支援する『ビッグイシュー』」(後藤 愼一)
http://ameblo.jp/asongotoh/entry-10061322950.html
「ビッグイシュー日本版」(http://www.bigissue.jp/)

「社会起業家」。今回の記事で西梅さんのことをそう呼ばせていただきたいのです。西梅さんには釈迦に説法となるかもしれませんが、念のためにウィキペデキアでの次ぎの解説を引用しますね。
社会起業家は、「社会変革(英:Social change)の担い手(チェンジメーカー)として、社会の課題を、事業により解決する人のことを言う。社会問題を認識し、社会変革を起こすために、ベンチャー企業を創造、組織化、経営するために、起業という手法を採るものを指す。社会起業家(社会的企業家)により行われる事業は、社会的企業(ソーシャル・エンタープライズ、Social Enterprise)と表現されている)。
「ビジネスの起業家は、典型的には儲けと自分にどの程度報酬があったかで、その実績を計るのに対し、社会起業家は、社会にどれだけの強い効果を与えたかを成功したかどうかの尺度にしている。NPOや市民グループを通して働きかけを行うことが多いが、この分野で働く人は、企業や政府のセクターで働く人が多い。社会的企業家(ソーシャル・アントレプレナー, Social Entrepreneur)ともいわれ、「ソーシャル・イノベーション(Social Innovation)を起こす人」とも定義される。自ら団体・会社を始める人でも、組織内にあって改革を起こす人でも、いずれもありとされる」。
そして、今月2日、「ホームレスの自立支援雑誌 熊本市でも」という記事が目に留まりました。それによると、任意団体である支援団体「ビッグイシュー熊本」を立ち上げたのが24歳の女性であることを知り、驚いたのでした。私は、即日に大阪の(有)ビッグイシュー本部へインタヴュー申込みのメールを送信。そして、7日、その「ビッグイシュー熊本」の代表・西梅彰容(あきよ)さん(24)とお会いしまた。

2日以降、「ビッグイシュー」そのものの運動と「ビッグイシュー熊本」については、各メディアで競うように報じられました。その概要については、下記にリンク先を添付しておきますので、そちらでチェックしていだだくとして、ここでは、24歳の西梅彰容さんがなぜ、全国で13番目となるこの支援団体を立ち上げようと思われたのかについてご紹介したいと思います。
西梅さんがこの「ビッグイシュー」という本に初めて出合ったのは、昨年5月に販売が開始された福岡・天神でした。カフェの運営指導という立場にある西梅さんは、その一店舗である福岡店を訪れた際に路上販売をする「ビッグイシュー」を手に取ったのでした。この雑誌の意味を知り、その後何度か雑誌を購入していた西梅さんは販売員である山本さんに、どこで夜寝ていらっしゃるのですか?と尋ねます。
「今はビッグイシューの収入があるのでネットカフェで毎日眠れています、シャワーもありますしね。でもお金を使わないように5時間パックなんかにしてると、シャワー浴びたりなんかしてたらすぐ過ぎちゃうんですけどね~」と山本さんは笑いながら話されたそうです。
その山本さんの笑顔を見た西梅さんは、「ビッグイシューは『夜、安心して眠る』チャンスを販売者に本当に提供してるんだ」と実感します。「自分の目の前にいる人が本当にビッグイシューに救われている、
ということをリアルに感じたら、やっぱり動かずにはいられなかったんですね」と。
それでも私には、腑に落ちないところがありました。私もこのビッグイシューのことを知り、この活動が彼らの自立を後押しているんだなと理解しました。しかし、私はそれをブログの中で語っただけでした。率先して私が手を上げようとは思いもしませんでした。単に私が物臭なのか、他人事だと頭の中で整理しただけなのか?今回のインタヴューで私は自分の器について改めて考える機会をもらいました。
「やっぱり動かずにはいられなかった」西梅さんのもっと奥にある動機を私は知りたくなりました。今回はこうした理由で、インタヴューを前半と後半に分けてお送りします。(続く)
<ビッグイシュー関連記事>
「『ビッグイシュー』熊本市でも ホームレスが雑誌販売 4日から収益で自立目指す」(2008/02/03付西日本新聞)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/kumamoto/20080203/20080203_002.shtml
「ビッグイシュー:あすから販売 /熊本」(2月3日16時1分配信 毎日新聞)
http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20080203ddlk43040358000c.html
「ホームレスが売る雑誌 ビッグイシュー」(asahi.com2008年02月05日)
http://mytown.asahi.com/kumamoto/news.php?k_id=44000000802050003
「ビジネス通じホームレスの自立を支援する『ビッグイシュー』」(後藤 愼一)
http://ameblo.jp/asongotoh/entry-10061322950.html
「ビッグイシュー日本版」(http://www.bigissue.jp/)

「社会起業家」。今回の記事で西梅さんのことをそう呼ばせていただきたいのです。西梅さんには釈迦に説法となるかもしれませんが、念のためにウィキペデキアでの次ぎの解説を引用しますね。
社会起業家は、「社会変革(英:Social change)の担い手(チェンジメーカー)として、社会の課題を、事業により解決する人のことを言う。社会問題を認識し、社会変革を起こすために、ベンチャー企業を創造、組織化、経営するために、起業という手法を採るものを指す。社会起業家(社会的企業家)により行われる事業は、社会的企業(ソーシャル・エンタープライズ、Social Enterprise)と表現されている)。
「ビジネスの起業家は、典型的には儲けと自分にどの程度報酬があったかで、その実績を計るのに対し、社会起業家は、社会にどれだけの強い効果を与えたかを成功したかどうかの尺度にしている。NPOや市民グループを通して働きかけを行うことが多いが、この分野で働く人は、企業や政府のセクターで働く人が多い。社会的企業家(ソーシャル・アントレプレナー, Social Entrepreneur)ともいわれ、「ソーシャル・イノベーション(Social Innovation)を起こす人」とも定義される。自ら団体・会社を始める人でも、組織内にあって改革を起こす人でも、いずれもありとされる」。
2008年02月07日
笑顔あふれる日本一のレストランを目指す、坂田孝行(10)
先日雑誌を見ていて、あるレストランの写真が目に入り気になってHPで内容を見ると、ただならぬ高級レストランのたたずまい。これはと思い、意を決して飛び込みでインタヴューの申込みを願い出ました。すると、唐突で怪しげな依頼にも関わらず、スタッフの方に実に丁寧な対応をしていただきました。「支配人に伝えますので後日、連絡をいただけますでしょうか?」ということで先週連絡を取り、昨日が初対面でのインタヴューとなりました。

そんな訳で、第10回目のゲストは、あのMarry Graceの支配人、坂田孝行(35)さんです。重厚な扉を開け、中に入ると、先日対応してくれたスタッフの男性が再び応じてくれました。二階の部屋に通してもらう間にも、見ず知らずの私にもスタッフの自然な笑顔と挨拶。きわめて自然です。そして、出されたお茶をいただく前に坂田さんが登場。
東バイパスと浜線バイパスの交差点の県庁寄りに位置するMarry GraceがMarry Gold(佐土原町)の姉妹店としてオープンしたのは、H16年の3月。オープンにあたって2名の新規採用枠に対して、応募者が100名以上という人気ぶり。採用の決め手は何だったのかうかがうと、キャリアよりも人柄だったそうです。実際、現在のスタッフは前職が金融関係、ディーラー営業、保育士さんなどということでした。
その坂田さんの入社経緯が面白いんですね。それまで置き薬の営業マンだった坂田さんは、H12年に結婚されます。そして、挙式をあげるその会場がMarry Goldでした。当初は奥様主導で進む打合せにお付き合い程度だった心境の坂田さんでしたが、Marry Goldのスタッフが働く姿を見て、ここで働けたらいいだろうなと思うようになります。そんな思いで何回か打合せを重ねるうちに、当時担当プランナーだった支配人との打合せが楽しくなる中で意気投合し、入社を決意することに。
当時打合せでMarry Goldを訪れる際、夏場だったこともあって、坂田さんはよく庭の草花に水をかけているおじさんを見かけていました。間もなく後に、坂田さんはなんと、その「ガーデニング担当のおじさん」の面接を受けることになりました。そのおじさんが社長の山崎茂さんだったのです。坂田さんがMarry Goldに入社されたのは、挙式から2ヵ月後のH13年1月でした。今では数店舗の経営を行う山崎社長は各地を飛び回る毎日ですが、店に立ち寄られると今も手入れの時間だけは惜しまれないそうです。

入社7年目の坂田さん。Marry Graceのオープニングスタッフとして1年を過ごした後、このレストランの支配人に昇格。以来、3年。それだけに坂田さんの夢は、このMarry Graceとともにあります。それはこのレストランを日本一のレストランにすること。「それは売上とか、グレードではなく、スタッフは勿論のこと、来てくださったお客様の笑顔にあふれたレストランであることです」と坂田さんは語られました。
この大きな目標に向かって、社是には次の三点があげられています。①喜びを力にしよう、②答えはいつもお客様から出そう、③お客様もスタッフも家族。この社是を具体的に示すようにMarry Graceでは社員ではなく家族と呼ばれます。退職は卒業。そしてスタッフ全員が営業マン。営業部ではなく「創夢部」と名づけられました。一人ひとりが歯車でなく、エンジン、動力でないとこの目標は達成できないとも語られました。
坂田さんは、Marry Graceを楽しんでいただくためには、「破格なランチタイムもお勧めですが、是非ディナーにお越しいただきたい」と語られました。私も近いうちにお邪魔させていただこうと思います。ちなみに昨年のクリスマスは12月初旬には予約で一杯になったそうです。今年のクリスマス・ディナーをMarry Graceでとお考えの方は、遅くもとも11月中でないと席の確保が難しいようです。

Marry Graceはレストランだけではなく、ハウスウェディングの県内での草分け的な存在であるMarry Goldの姉妹店でもあります。坂田さんにとっての最大のライバルは、このMarry Gold。その目標への達成度は50%だと語られました。これまでのレストランや挙式でのエピソードについてうかがいましたが、「たくさんありすぎて絞りきれません。寧ろ、思うようなサービスに至らなかったことを反省するばかりです」とホスピタリストとしての片鱗をうかがわされました。
Marry Grace;
096-370-7001
<所> 熊本市出水8・572・1
<営>11:30~14:00/18:00~OS21:00
<休>第2・4火曜
<席>テーブル48席
<駐> 90台
http://www.marrygrace.com/

そんな訳で、第10回目のゲストは、あのMarry Graceの支配人、坂田孝行(35)さんです。重厚な扉を開け、中に入ると、先日対応してくれたスタッフの男性が再び応じてくれました。二階の部屋に通してもらう間にも、見ず知らずの私にもスタッフの自然な笑顔と挨拶。きわめて自然です。そして、出されたお茶をいただく前に坂田さんが登場。
東バイパスと浜線バイパスの交差点の県庁寄りに位置するMarry GraceがMarry Gold(佐土原町)の姉妹店としてオープンしたのは、H16年の3月。オープンにあたって2名の新規採用枠に対して、応募者が100名以上という人気ぶり。採用の決め手は何だったのかうかがうと、キャリアよりも人柄だったそうです。実際、現在のスタッフは前職が金融関係、ディーラー営業、保育士さんなどということでした。
その坂田さんの入社経緯が面白いんですね。それまで置き薬の営業マンだった坂田さんは、H12年に結婚されます。そして、挙式をあげるその会場がMarry Goldでした。当初は奥様主導で進む打合せにお付き合い程度だった心境の坂田さんでしたが、Marry Goldのスタッフが働く姿を見て、ここで働けたらいいだろうなと思うようになります。そんな思いで何回か打合せを重ねるうちに、当時担当プランナーだった支配人との打合せが楽しくなる中で意気投合し、入社を決意することに。
当時打合せでMarry Goldを訪れる際、夏場だったこともあって、坂田さんはよく庭の草花に水をかけているおじさんを見かけていました。間もなく後に、坂田さんはなんと、その「ガーデニング担当のおじさん」の面接を受けることになりました。そのおじさんが社長の山崎茂さんだったのです。坂田さんがMarry Goldに入社されたのは、挙式から2ヵ月後のH13年1月でした。今では数店舗の経営を行う山崎社長は各地を飛び回る毎日ですが、店に立ち寄られると今も手入れの時間だけは惜しまれないそうです。

入社7年目の坂田さん。Marry Graceのオープニングスタッフとして1年を過ごした後、このレストランの支配人に昇格。以来、3年。それだけに坂田さんの夢は、このMarry Graceとともにあります。それはこのレストランを日本一のレストランにすること。「それは売上とか、グレードではなく、スタッフは勿論のこと、来てくださったお客様の笑顔にあふれたレストランであることです」と坂田さんは語られました。
この大きな目標に向かって、社是には次の三点があげられています。①喜びを力にしよう、②答えはいつもお客様から出そう、③お客様もスタッフも家族。この社是を具体的に示すようにMarry Graceでは社員ではなく家族と呼ばれます。退職は卒業。そしてスタッフ全員が営業マン。営業部ではなく「創夢部」と名づけられました。一人ひとりが歯車でなく、エンジン、動力でないとこの目標は達成できないとも語られました。
坂田さんは、Marry Graceを楽しんでいただくためには、「破格なランチタイムもお勧めですが、是非ディナーにお越しいただきたい」と語られました。私も近いうちにお邪魔させていただこうと思います。ちなみに昨年のクリスマスは12月初旬には予約で一杯になったそうです。今年のクリスマス・ディナーをMarry Graceでとお考えの方は、遅くもとも11月中でないと席の確保が難しいようです。

Marry Graceはレストランだけではなく、ハウスウェディングの県内での草分け的な存在であるMarry Goldの姉妹店でもあります。坂田さんにとっての最大のライバルは、このMarry Gold。その目標への達成度は50%だと語られました。これまでのレストランや挙式でのエピソードについてうかがいましたが、「たくさんありすぎて絞りきれません。寧ろ、思うようなサービスに至らなかったことを反省するばかりです」とホスピタリストとしての片鱗をうかがわされました。
Marry Grace;
<所> 熊本市出水8・572・1
<営>11:30~14:00/18:00~OS21:00
<休>第2・4火曜
<席>テーブル48席
<駐> 90台
2008年02月06日
人との新たな「間(ま)」を築きたい、建築家・長野聖二(9)

第九回目のゲストは、第四回目の黒田恵子さん、前回の渡辺真希子さんが店舗を構え、所属する「河原町文化開発研究所」の代表であり、「人間建築探検處」の代表である建築家・長野聖二さんです。長野さんは、大分県杵築市山香町生まれの36歳。熊本大学の建築学科卒業後、2001年に独立され、2004年の12月にこの河原町にオフィスを構えられました。
まず、頂いた名刺が一風変わったものでした。表裏が透けていて、どちらからも読めるようになっています。ここに長野さんのポリシーを感じた私は、この名刺について聞いてみました。すると、「表も裏もない人間関係、ヒトとモノ、コトの関係を築きたいということでしょうか」と応えてくれました。このポリシーを現すかのように長野さんのオフィスはご覧のようにガラス張りでした。

また、「人間建築探検處」という屋号も一風変わっています。「建築は機能、価値観、地域、環境等の様々な要素を複合して出来るものです。建築を通じて人間と社会、環境、コト、モノとの従来にない新しい関係を築きたいと考えています」(同社HP)という長野さんの思い。人間と建築の関係、「間」を探検(サーベイ)しながら、泥臭く考える「處」(ところ)という思いが込められています。
この町にオフィスを構えるに至ったのは、平成14年度事業としてインキュベータのモデル事業として始まった旧免許センターにあるインキュベーション施設への入居からでした。この施設での入居が半年と決まっていたことから、入居早々次の場所を検討しなければいけなかった長野さんは、当時すでに動きつつあった河原町のプロジェクトを知り、施設の仲間とこの場所を訪れ、ここの佇まいが気に入ったということです。
河原町文化開発研究所の立ち上げは、先行して進んでいた広告代理店を経営する方によるプロデュースを受ける形で行われ、代表の役回りを引き受けることになったそうです。この界隈を毎月第二土曜日に行われる「アートの日」を通じ、若き芸術家たちの街にして、彼らの芸術を楽しみにやってくる人々を増やすこと。それがこの研究所の目標の一つであり、代表の大変な役割。
今回も強引にインタヴューさせていただいた感じですが、お話をうかがって意外なご縁があることがわかりました。まず、奥様が私の出身高校の後輩にあたること、そして、私が今塾生となっている「くまもと まち育て塾」の塾長である愛知産業大学大学院教授の延藤安弘さんの熊大時代の教え子が長野さんでした。
長野さんは、コーポラティブハウス、コレクティブハウスといった集合住宅、高齢者や障害者などが介護スタッフとともに地域の中で自立的な共同生活をするグループホームといった社会的弱者のための環境づくりにも力を入れられていますが、熊本市で1992年に竣工したコーポラティブハウス・Mポートに関わられたのが延藤教授でした。
ヒトと住宅の関係は、気候、太陽、風、近隣住民、モノ、コトとの「間」が重要なファクターだと語る長野さん。そんな長野さんへのアクセスは下記。これからマイホームを考えているという方は、一度相談してみてはいかがでしょうか?

「人間建築探検處」
熊本県熊本市河原町2
TEL&FAX;096-354-1007
E-mail;fieldworks@zcmain.jp
http://fieldworks.main.jp





